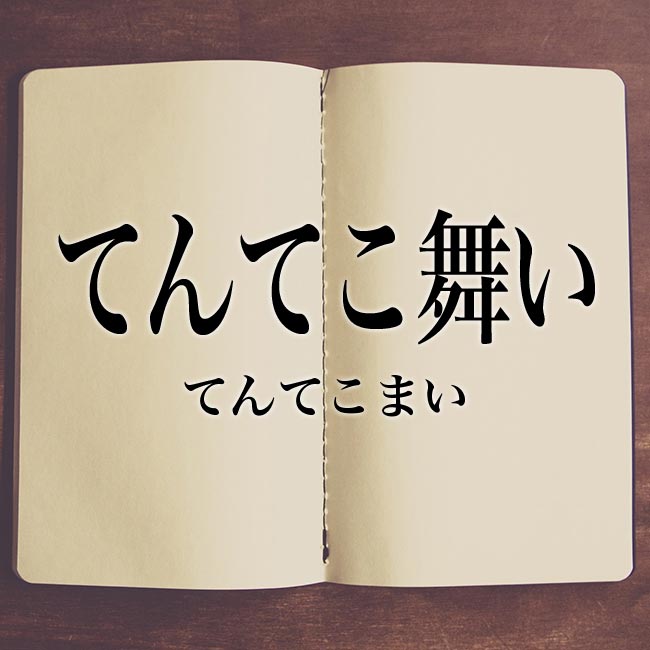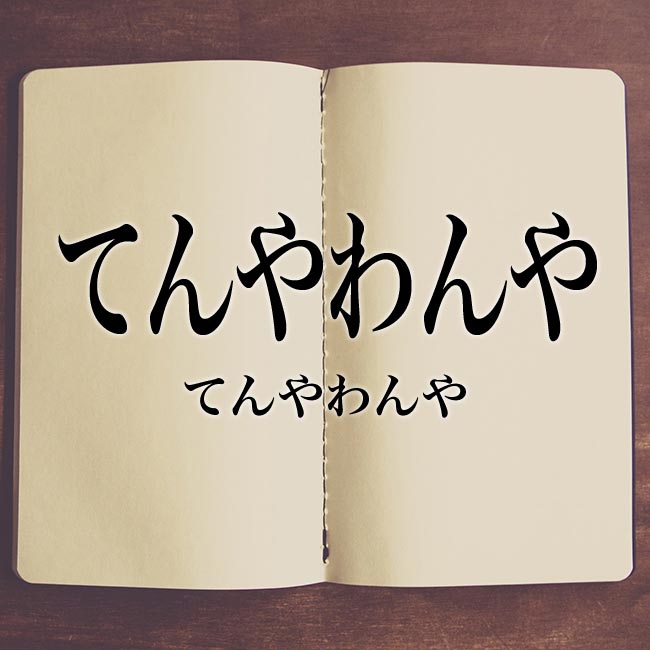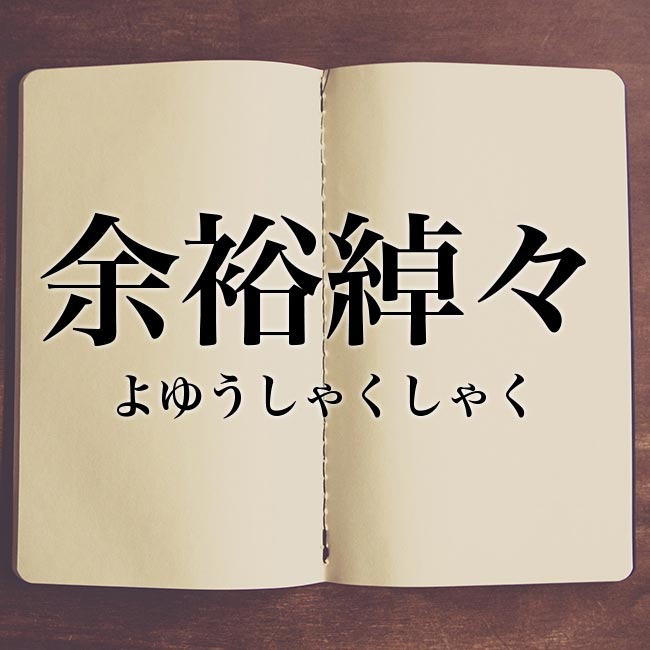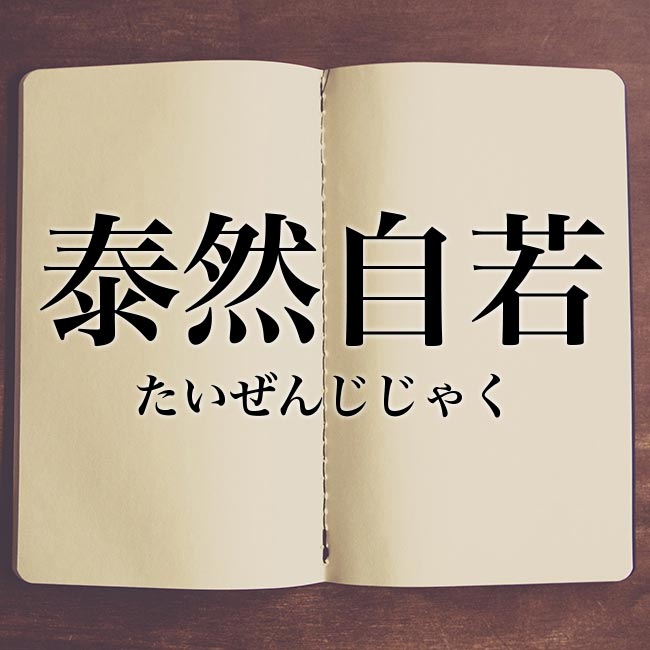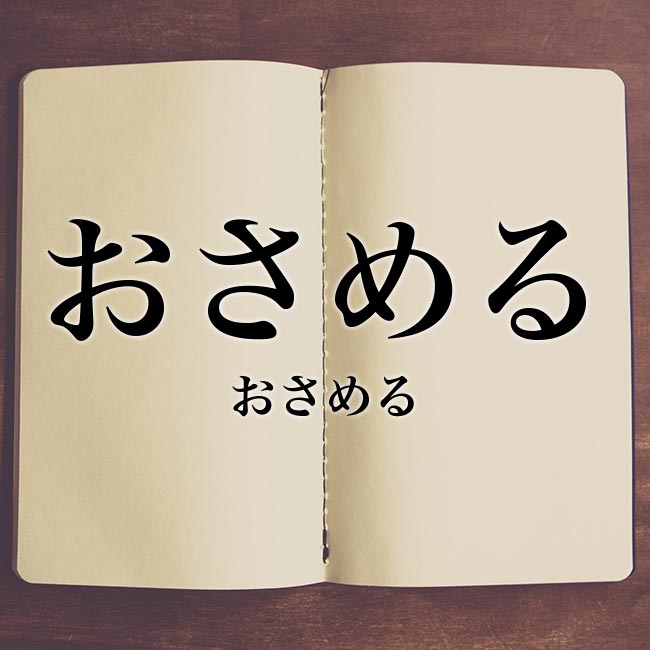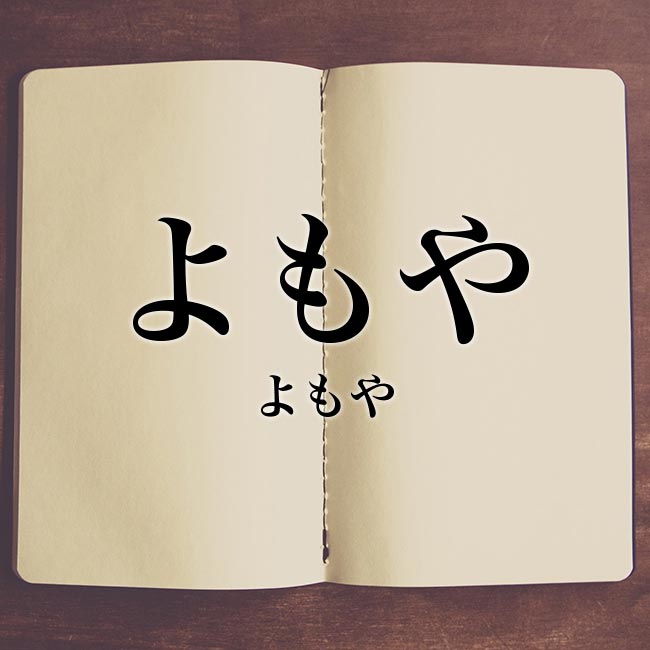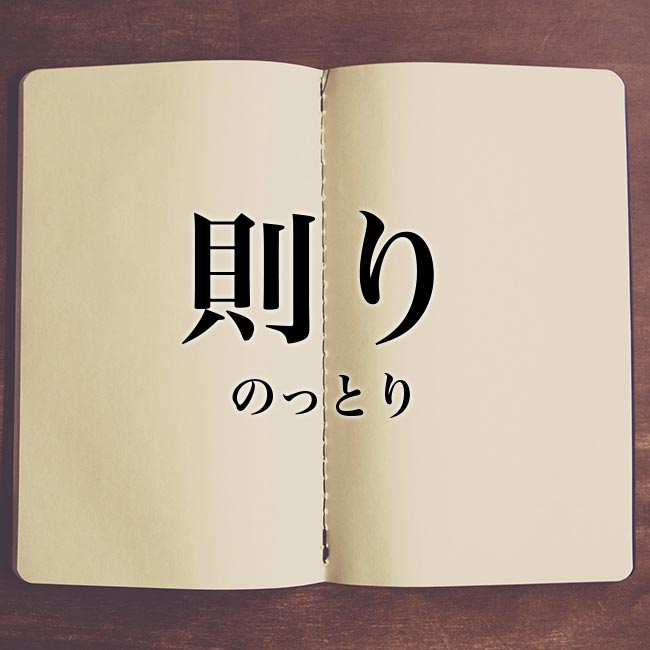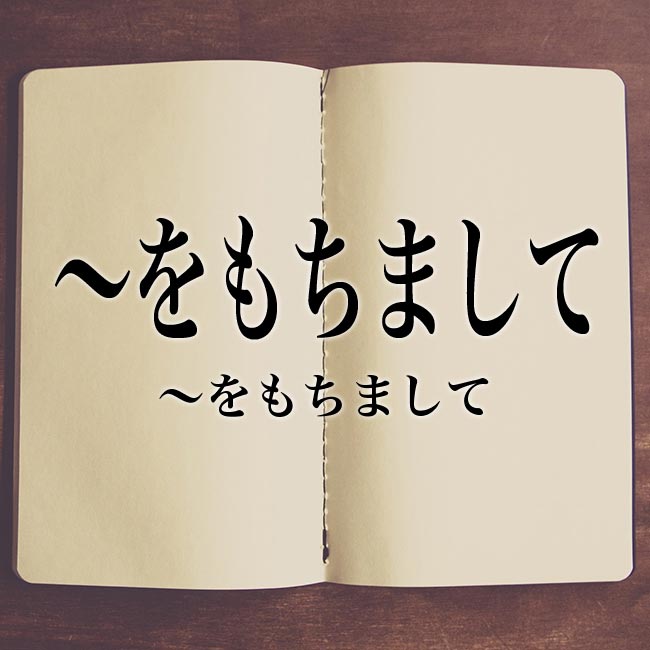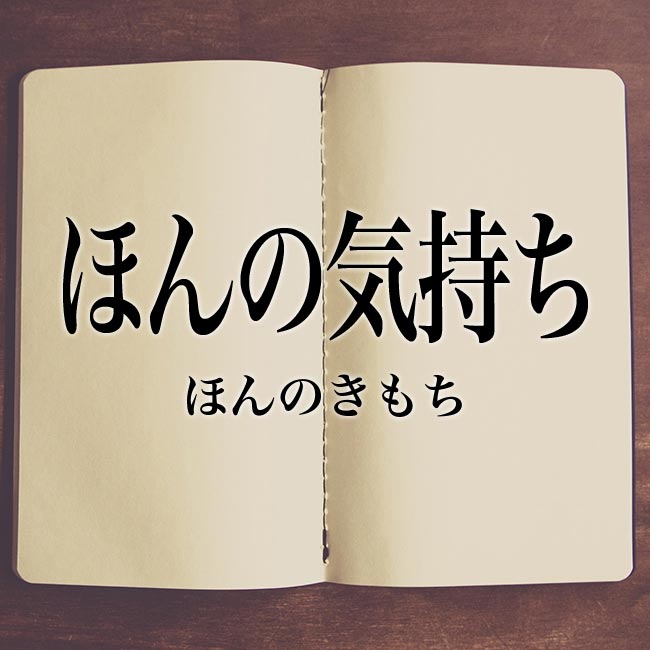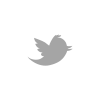「大わらわ」とは?意味や使い方!例文や解釈
人が忙しそうにしている時に「大わらわ」という表現をすることがあります。
一体どの様な意味なのか、意外な語源なども併せて紹介します。
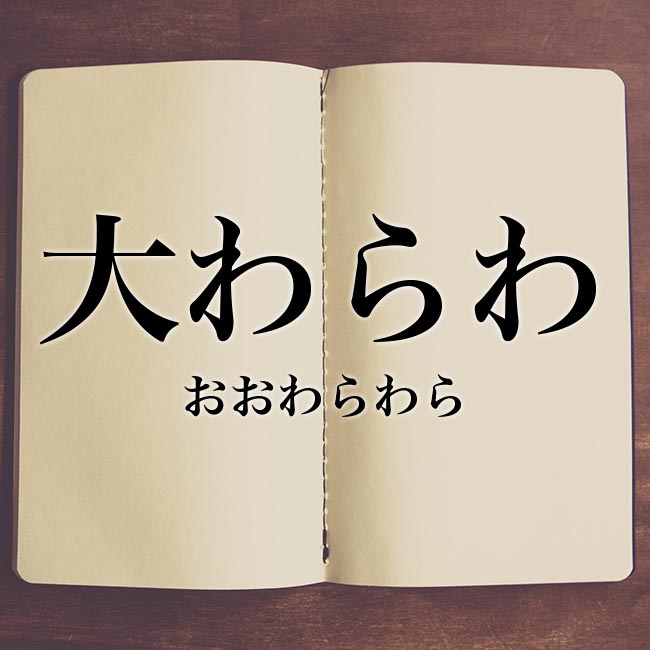
目次
- 「大わらわ」とは?
- 「大わらわ」の表現の使い方
- 「大わらわ」の類語や類似表現や似た言葉
- 「大わらわ」を使った例文や短文など(意味を解釈)
- 「大わらわ」の反対語
- 「大わらわ」の英語と解釈
「大わらわ」とは?
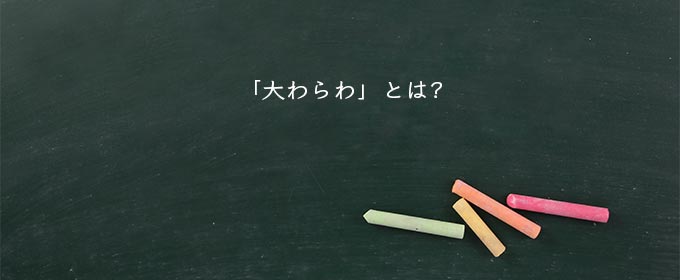
「大わらわ」の概要について紹介します。
- 「大わらわ」の読み方
- 「大わらわ」の意味
- 「大わらわ」の語源や由来
「大わらわ」の読み方
「大わらわ」は「おおわらわ」と読みます。
とてもシンプルな言葉ですが、つい勢いで「おおわらわら」と言わない様にしましょう。
「大わらわ」の意味
「大わらわ」も意味は「やることに追われて余裕がなく動き回る様子」です。
仕事が忙しい時に、周囲を顧みる余裕がない程そのものごとに集中して、ひたすら動き回っていることを言います。
他の人が何をやっているのか、或いは自分が今人からどの様に見られているのかなど気にしていられません。
切羽詰まった状況を切り抜けようと必死に行動する時の表現です。
「大わらわ」の語源や由来
「大わらわ」は漢字で書くと「大童」となり、これが語源です。
「大童=大きな童」、つまり大きな子供という意味からきているのです。
「童」は「わらわ」「わらべ」と読み、昔は元服前の子供のことでした。
元服とはその子供が成人になったことを表す通過儀礼のひとつで、男の子は年齢12歳〜16歳位、女の子は18歳〜20歳でしたが、中にはもっと早かったり遅かったりする人もいました。
昔の子供は小さい頃はおかっぱ頭だったのですが、元服すると髪を結ってちょんまげになります。
時代劇ではちょんまげはかなりしっかりと結われていますが、これはカツラであるからで、実際には鬢付油で形を整えてあるだけでした。
戦が起きると兜をかぶって馬に乗って動き回るのですから、ちゃんまげもバラバラになってしまいます。
よく「落ち武者」などと言われる両側に髪の毛が垂れ下がり風になびいている姿になるのです。
この姿がまるで小さい子供が髪を振り乱して遊んでいる様だ、というとで「大きな童=大童」と言われる様になったのです。
ところが江戸時代になり戦が減ると、武士が髪を振り乱して動き回る機会もなくなりました。
そこで段々と言葉の意味が変化して、「大人が髪を振り乱す位忙しい状況」を「大童」と言う様になったのです。
この頃になると「大童」は比喩的表現となり、実際に髪は乱れていなくてもそれくらいに忙しいという意味で使われる様になりました。
「大わらわ」の表現の使い方
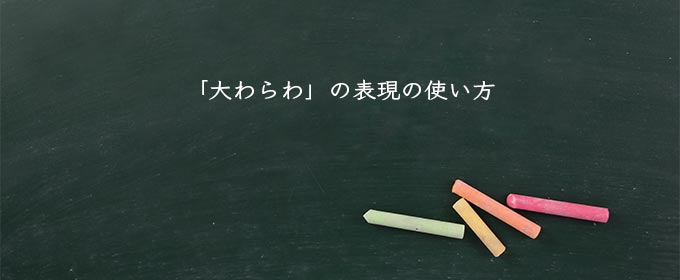
「大わらわ」の使い方についてポイントを紹介します。
- 名詞として使う
- 非常に忙しい状態に使う
名詞として使う
「大わらわ」は名詞なので「大わらわだった」「大わらわで〜した」など動詞を伴って使います。
「大わらわな一日」「大わらわな様子」など、名詞を修飾する使い方もできます。
非常に忙しい状態に使う
「大わらわ」は、「髪の毛を振り乱すほど忙しい」状態の時に使います。
普通にやるべきことがあって忙しいだけの状態には使いません。
「大わらわ」の類語や類似表現や似た言葉
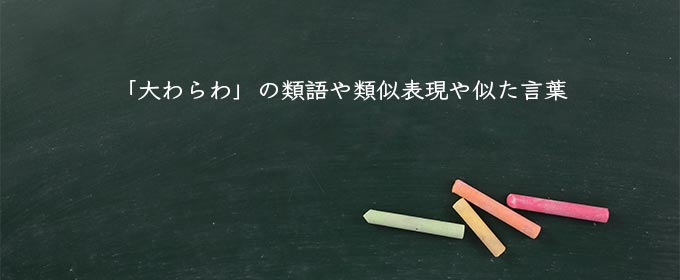
「大わらわ」の類語を紹介します。
- 「てんてこ舞い」【てんてこまい】
- 「きりきり舞い」【きりきりまい】
- 「てんやわんや」【てんやわんや】
「てんてこ舞い」【てんてこまい】
「非常に忙しくて休む暇もない様子」という意味です。
「てんてこ」とはお祭りで小太鼓が小気味よく「てんてこ」と鳴る様子を表した擬声語です。
この音に合わせて舞う姿が小刻みで忙しそうに見えたことから「てんてこ舞い」と言われる様になりました。
「きりきり舞い」【きりきりまい】
こちらも「非常に忙しくて休む暇もない様子」という意味です。
「きりきり」とはコマがくるくると回る様子を表した擬態語です。
まるでコマの様にきりきりと速く回りながら踊る様子から「きりきり舞い」と言われる様になりました。
「てんやわんや」【てんやわんや】
「ひとりひとりが勝手に行動して騒ぎ立てることで、その場のまとまりがなくなる様子」という意味です。
大勢の人が集まった時に、秩序が守られずにその場が混乱してしまうことを言います。
「てんやわんや」の語源は大阪弁の「てんでん+わや」で、「てんでん」は「手に手に」「わや」は「無茶」という意味があります。
「手に手に無茶をする=それぞれが無茶なことをする」という意味で使われる様になりました。
「大わらわ」を使った例文や短文など(意味を解釈)
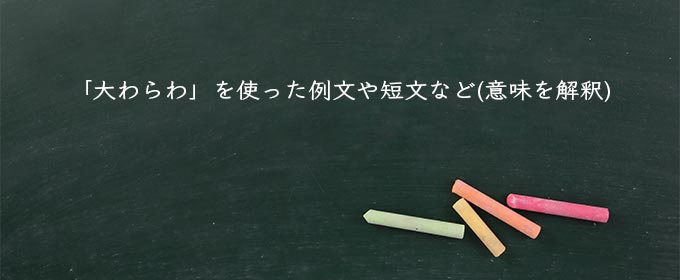
「大わらわ」を使った例文と解釈を紹介します。
- 「大わらわ」を使った例文1
- 「大わらわ」を使った例文2
「大わらわ」を使った例文1
「急に社長が視察に来ると連絡が来て職場が大わらわだった」
普段は本社にいて滅多に顔を見せない社長が、急にその職場を視察に来るとの連絡があり、職場全員が片づけやお茶出しの準備に追われている様子を表します。
普段だらだらとした雰囲気のオフィスだと思わぬ叱責を受ける可能性があるので、目に見える場所は整理整頓をして、理想の理想のオフィスを演出しようとしているのです。
「大わらわ」を使った例文2
「急に転勤が決まって大わらわだった」
会社で転勤が決まると、部署によっては「来週から来てほしい」と言われることもあります。
転勤は勤務先が変わるだけではなく引越しも伴いますので、持ち家の人は家や車をどうするかまで考えなくてはいけません。
仕事の引き継ぎと引越しの準備で手いっぱいになっている様子を表しています。
「大わらわ」の反対語
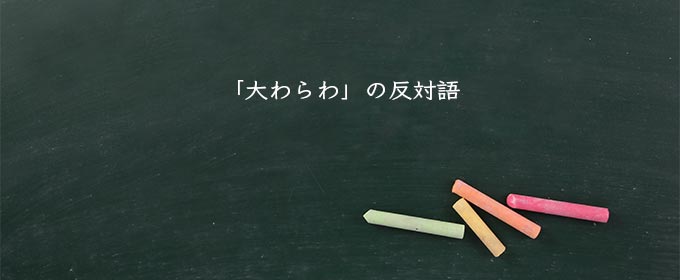
「大わらわ」の反対語を紹介します。
- 「余裕綽々」【よゆうしゃくしゃく】
- 「泰然自若」【たいぜんじじゃく】
「余裕綽々」【よゆうしゃくしゃく】
意味は「焦らずにゆとりを持ち、ゆったりと落ち着いている様子」です。
「綽々」とは「落ち着いてゆったりとしている様子」という意味です。
「泰然自若」【たいぜんじじゃく】
意味は「常に落ち着いていて、平静を失わない様子」です。
「泰然」も「自若」も「落ち着いている様子」という意味で、2つつなげることで意味を強調しています。
「大わらわ」の英語と解釈
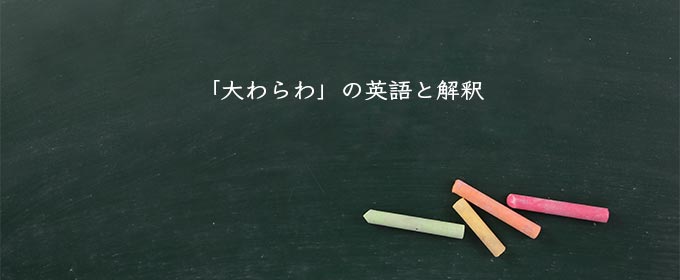
“I had a hectic day.”
「今日は大わらわだった」になります。
「hectic=死ぬほど忙しい=大わらわ」という意味になり、オフィスでネイティブの人が良く使うフレーズです。
「大わらわ」は「やることに追われて余裕がなく動き回る様子」という意味です。
仕事やプライベートでとにかく忙しくて落ち着いて座っていられない状態の時に使ってみましょう。