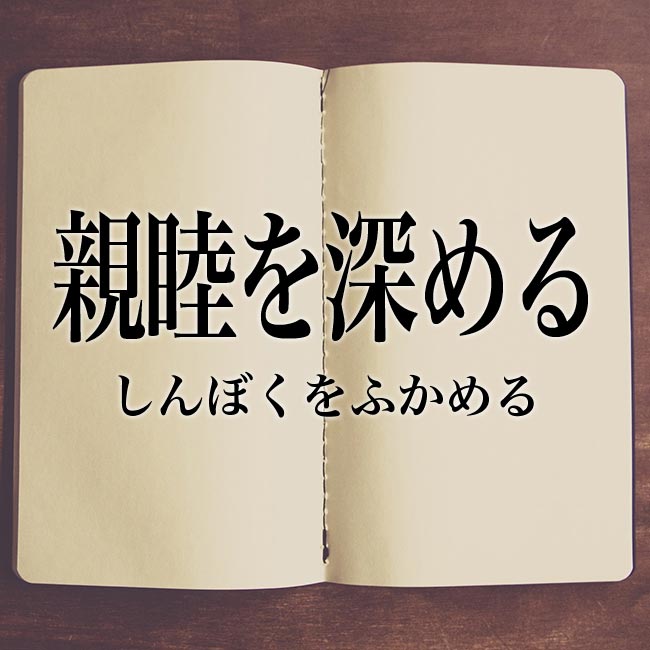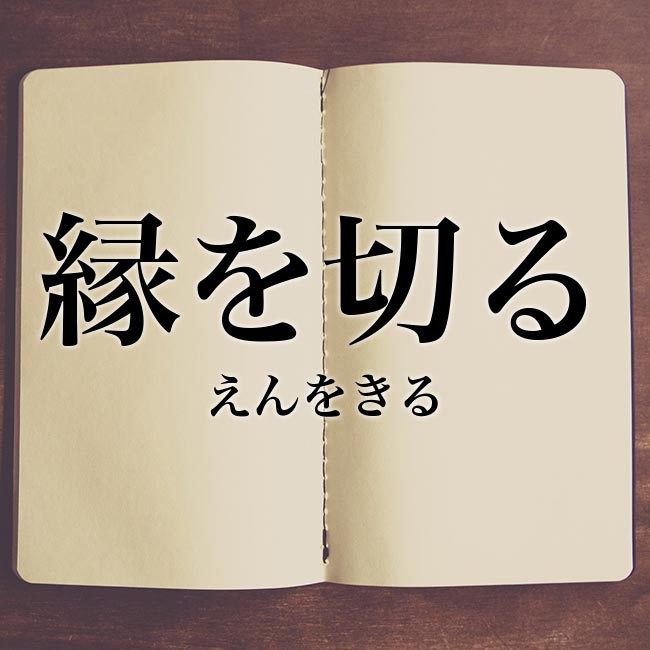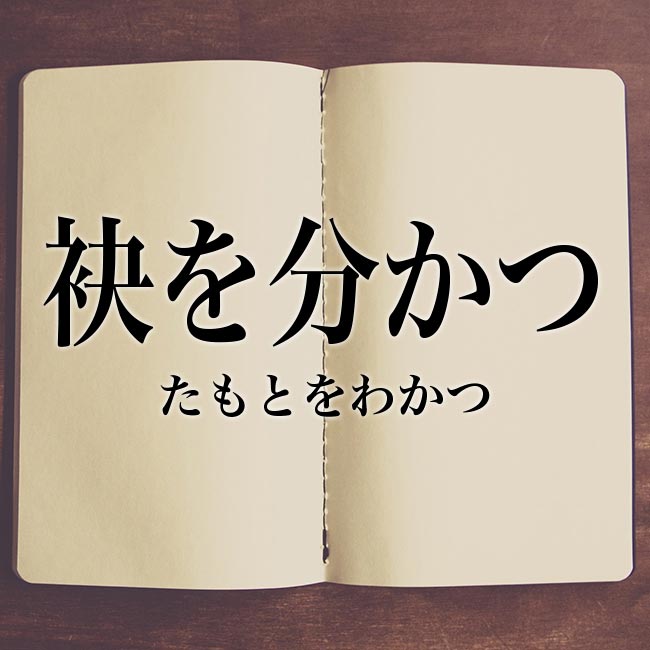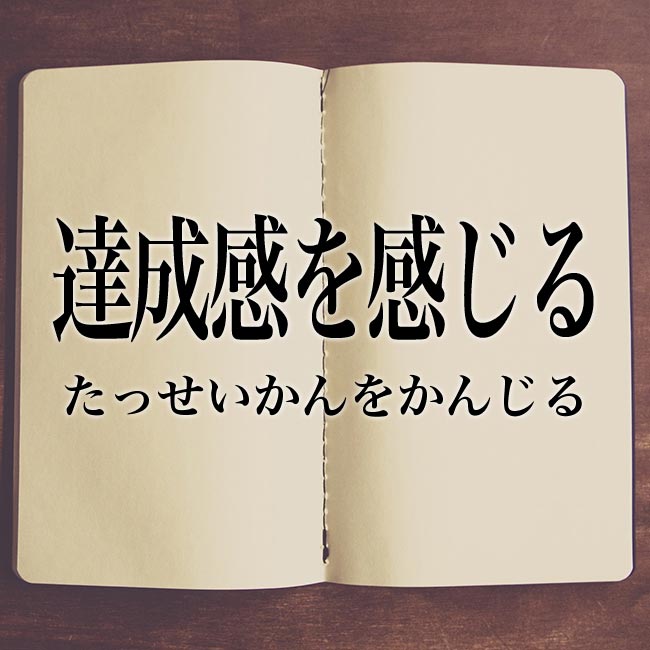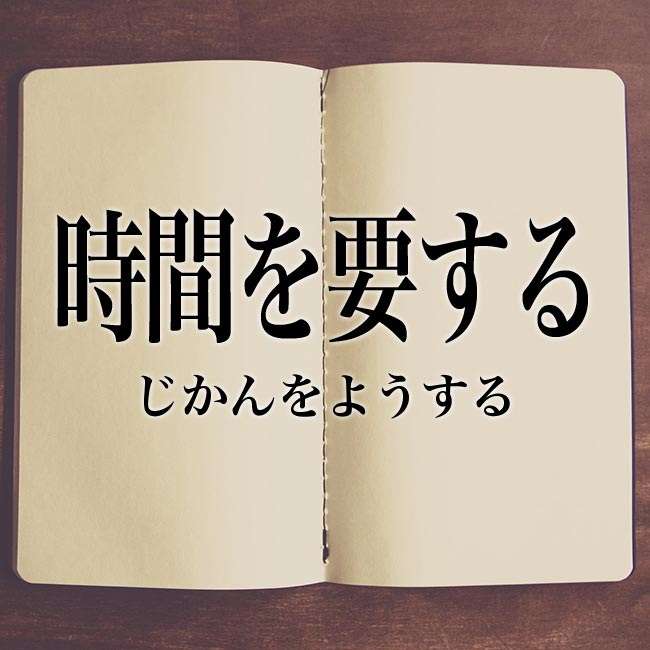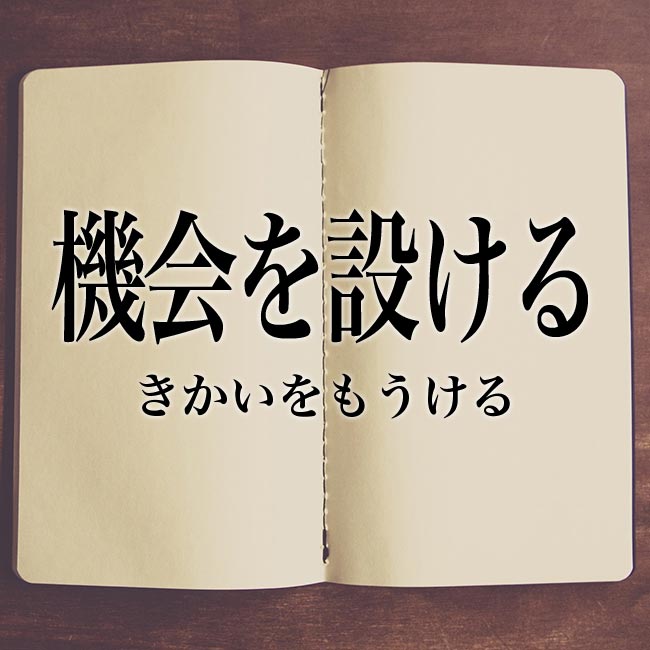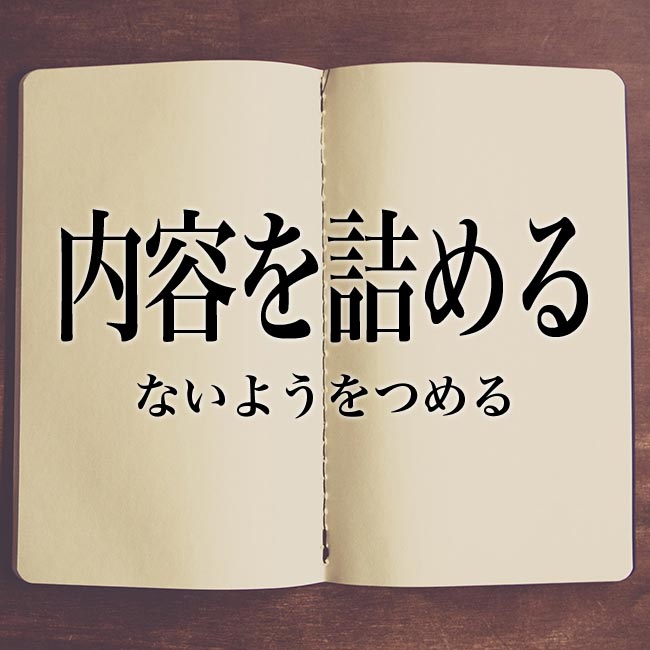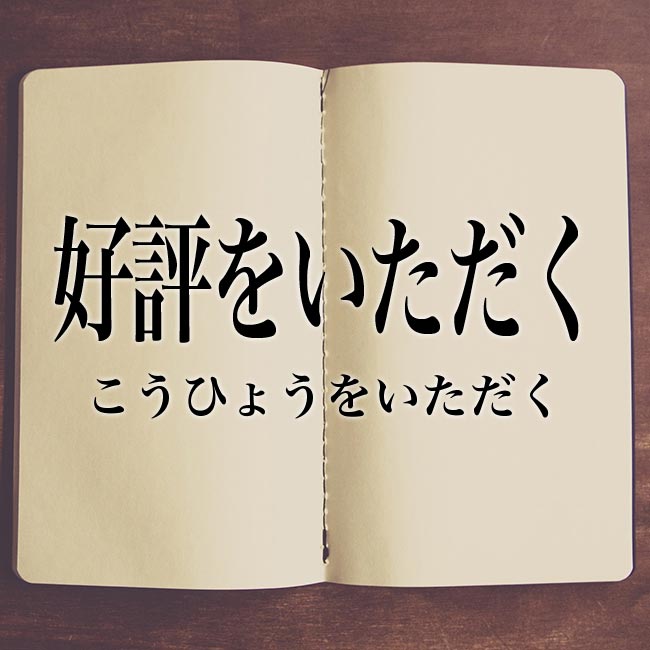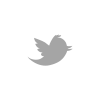「盃を交わす」とは?意味や使い方!例文や解釈
「盃を交わす」という何とも硬派なイメージの言葉があります。
一体どのような意味なのか、語源なども併せて紹介します。
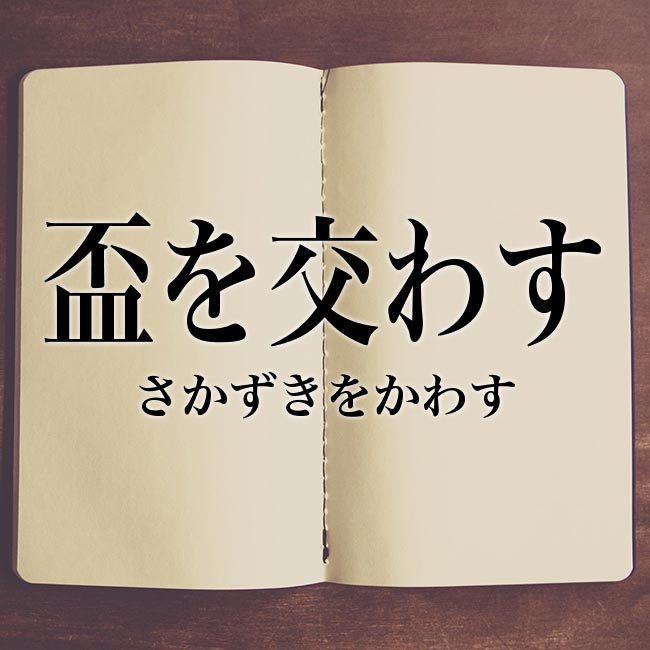
目次
- 「盃を交わす」とは?
- 「盃を交わす」の表現の使い方
- 「盃を交わす」の類語や類似表現や似た言葉
- 「盃を交わす」を使った例文や短文など(意味を解釈)
- 「盃を交わす」の反対語
- 「盃を交わす」の英語と解釈
「盃を交わす」とは?
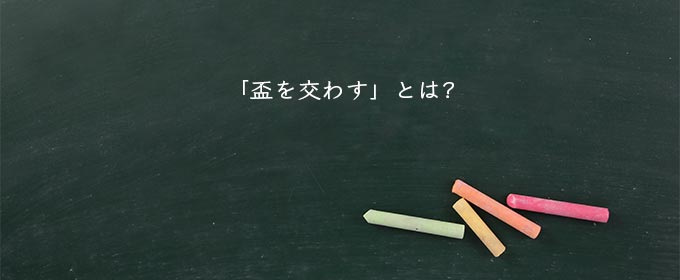
「盃を交わす」の概要について紹介します。
- 「盃を交わす」の読み方
- 「お酒を飲み交わして信頼を深める」の意味
- 「お酒を飲み交わして絶対裏切らないことを誓う」の意味
- 「盃を交わす」の語源や由来
「盃を交わす」の読み方
「盃を交わす」は「さかずきをかわす」と読みます。
「はいをかわす」と読む人もいますが、正しくは「さかずき」です。
「お酒を飲み交わして信頼を深める」の意味
「盃を交わす」の意味は「お互いの信頼を深める為にお酒を飲み交わすこと」という意味です。
人はお酒を飲むと酔っ払い、無防備になるものです。
相手に対して気を許せる状態で話をするには、余程信頼できる関係になる必要があります。
その様な状態を作る為に誘い合ってお酒を飲むことを言います。
「お酒を飲み交わして絶対裏切らないことを誓う」の意味
こちらは昔から武士や暴力団の間で行われてきた儀式のこです。
お酒を酌み交わすことで、兄弟の様に結束の固い関係になり、お互い絶対に裏切らないことを誓う時の儀式です。
血縁関係がなくてもお互いにお酒を注いで飲み交わすことで義兄弟となる約束をするのです。
一般の人達にはあまり縁がない言葉ですが、映画やドラマなどで知られています。
「盃を交わす」の語源や由来
「盃を交わす」の語源は「式三献(しきさんこん)」という契約の儀式からきています。
昔は武士が出陣する時に、主従の結束を誓い勝利を願うという儀式でした。
これが段々と一般庶民の間に広まり、人と人の間で約束を取り交わす時の儀礼として使われる様になったのです。
そして時代が流れるに連れて、祝言の場で行われる「三々九度」に変化していきました。
「三々九度」とは、大きさが3種類ある盃を用いて、最初に男性が三度飲み、次に女性が三度飲み、再度男性が三度のみ、合計で九回飲む儀式のことです。
庶民の間では人と人が信頼関係を結び、忠誠を誓う為の儀礼として浸透していき、現在では更にカジュアルな場で使われる様になっています。
因みに、飲み会に遅れてくると「駆けつ三杯」と言われることがありますが、これは「式三献」の名残です。
遅れてきた人は三度お酒を飲んでから参加するというしきたりが残っているのでしょう。
「盃を交わす」の表現の使い方
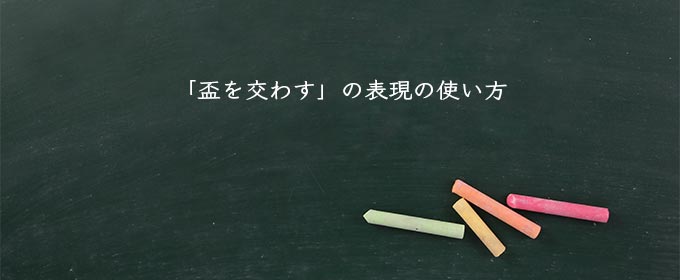
「盃を交わす」が使われるシーンを紹介します。
- 「兄弟盃」として
- 結婚式で
- 接待や同僚との飲み会で
「兄弟盃」として
「盃を交わす」と言って最もイメージし易いのが暴力団の「兄弟盃」です。
任侠映画では「兄弟の契りを交わす」と言ってお酒を飲み交わすシーンがありますが、暴力団の世界だけではありません。
歴史小説では武士が同じ野心を抱く同士と「盃を交わす」シーンの描写もあります。
「三国志演義」では、劉備玄徳と関羽、張飛の三人が「我ら生まれる日は違っても死ぬ日は同じとする」と言って義兄弟の契りを結び盃を交わした様子を「桃園の誓い」と表現しています。
結婚式で
上記の語源の章で述べましたが、「盃を交わす」が使われるシーンで最も多いのが結婚式です。
新郎新婦がお酒を酌み交わして「二人で末永く仲睦まじく生きていくこと」や「子孫繁栄」を願う儀式として伝わっています。
接待や同僚との飲み会で
仕事で同じチームとして力を合わせている者同士が飲みに行き、お互いの信頼を深める時に「盃を交わす」と言います。
また、接待ではお互いの会社の上司がお酒を注ぎ交わしながら飲み、今後も協力し合っていくことを話し合う時に「盃を交わす」と言います。
ただ飲みに行くだけではなく、より良い関係を築く為にお酒を飲み交わすという意味があるのです。
「盃を交わす」の類語や類似表現や似た言葉
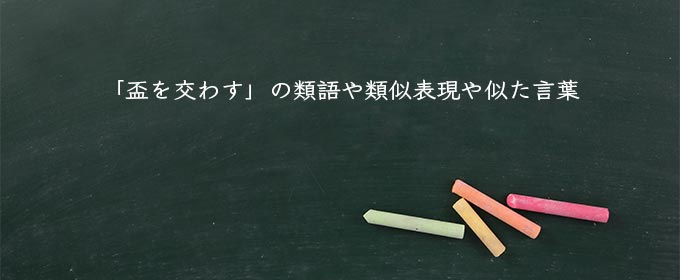
「盃を交わす」の類語は以下の通りです。
- 「親密になる」【しんみつになる】
- 「義理立てを誓う」【ぎりだてをちかう】
- 「親睦を深める」【しんぼくをふかめる】
「親密になる」【しんみつになる】
「今までより更に打ちとけて仲良くなること」を言います。
「お酒を飲む」という意味はありませんが、「盃を交わす」ことでより親しくなるという結果を表しています。
「義理立てを誓う」【ぎりだてをちかう】
「お互いが裏切らずに、親族の様に強い関係を結ぶこと」です。
この誓いをする時にお酒を飲む行為がついてくることが多くなります。
「親睦を深める」【しんぼくをふかめる】
「お互いに親しくなること」という意味で、「親睦会」というと大抵飲食が入ります。
「盃を交わす」を使った例文や短文など(意味を解釈)
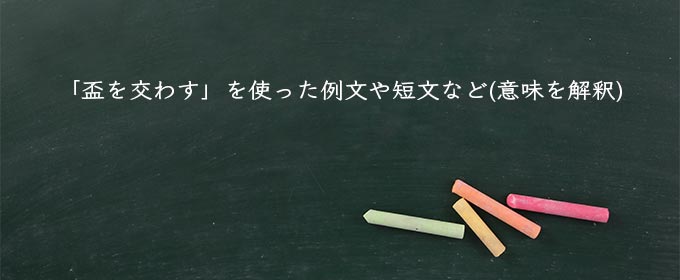
「盃を交わす」を使った例文と解釈を紹介します。
- 「盃を交わす」を使った例文1
- 「盃を交わす」を使った例文2
「盃を交わす」を使った例文1
「神前式で結婚式を挙げて三々九度の盃を交わした」
その夫婦は神社で結婚式を挙げて、三々九度の盃を交わしました。
あくまで儀式ですので、お酒が飲めない人は盃に口を付けるだけでも構いません。
最近では最初から水を入れてくれるところもあります。
「盃を交わす」を使った例文2
「同僚とプロジェクトの成功を願って杯を交わした」
仕事で同僚と同じプロジェクトの担当になりました。
これからお互い協力して目標を達成できる様に、信頼関係を深めるべく飲みに言ったことを表しています。
「盃を交わす」の反対語
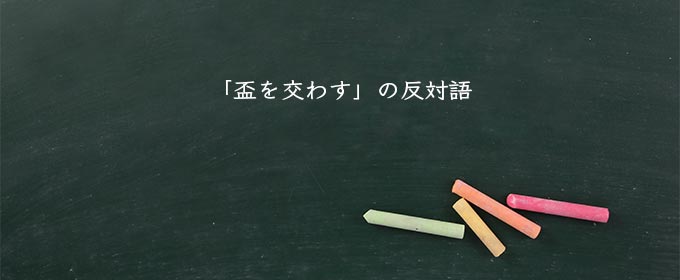
「盃を交わす」の反対語は以下の通りです。
- 「縁を切る」【えんをきる】
- 「袂を分かつ」【たもとをわかつ】
「縁を切る」【えんをきる】
「血縁関係や、あるものごととの関係を断つこと」という意味です。
お互い全く連絡を取り合わなくなる状態を表しています。
「袂を分かつ」【たもとをわかつ】
「たもとをわかつ」と読みます。
意味は「今まで一緒に行動していた人と関係を断つこと」です。
「たもと」は元々「手元」が語源で、「すぐそば」という意味があります。
自分のすぐそばにいる人と別れるという意味で使われる様になりました。
「盃を交わす」の英語と解釈
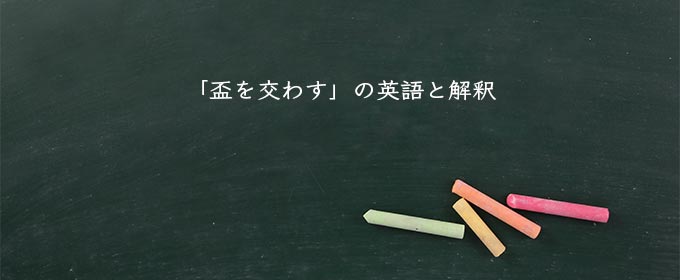
“We drunk to deepen engage of each other.”
「お互いの関係を深める為に盃を交わした」になります。
“engage”というと日本人には「婚約」というイメージが強いのですが、英語では「絆」「関係」などより幅広い意味で使われます。
「盃を交わす」は「お酒を飲み交わして信頼を深める」「お酒を飲み交わして絶対裏切らないことを誓う」の2つの意味があります。
暴力団の儀式だけではなく結婚式でも使われる、歴史的な意味のある言葉です。
相手との関係を深める為に飲む時に使ってみると良いでしょう。