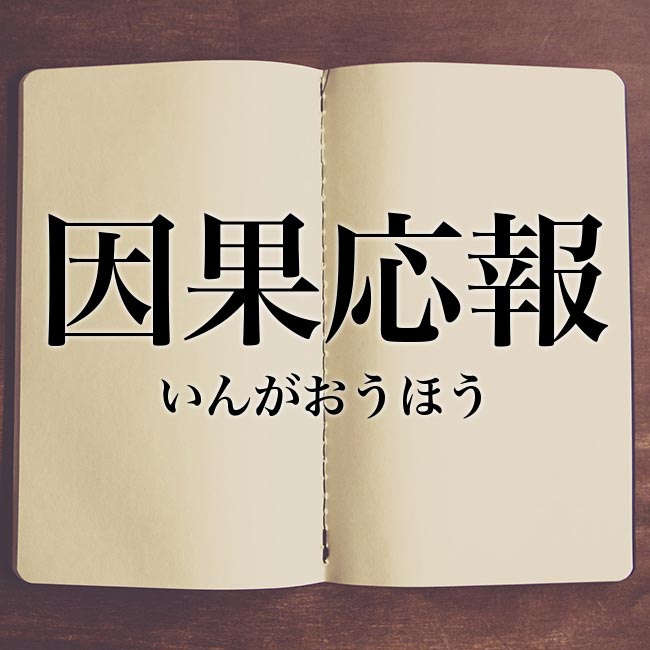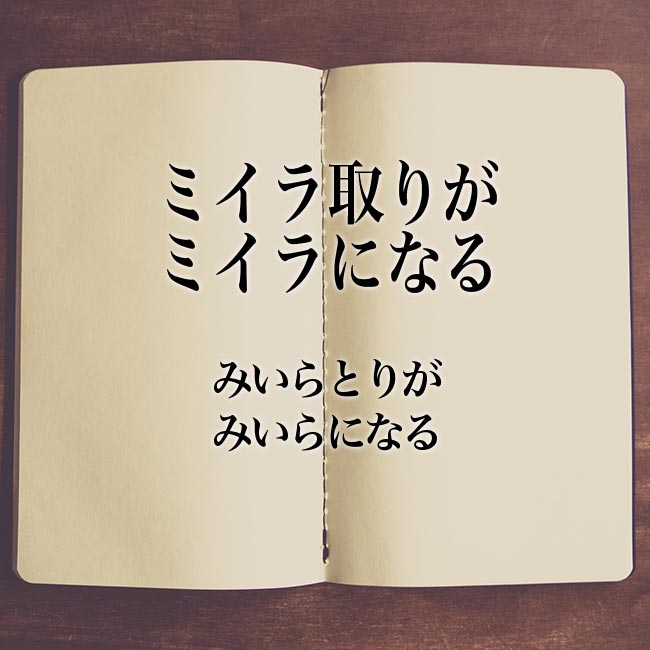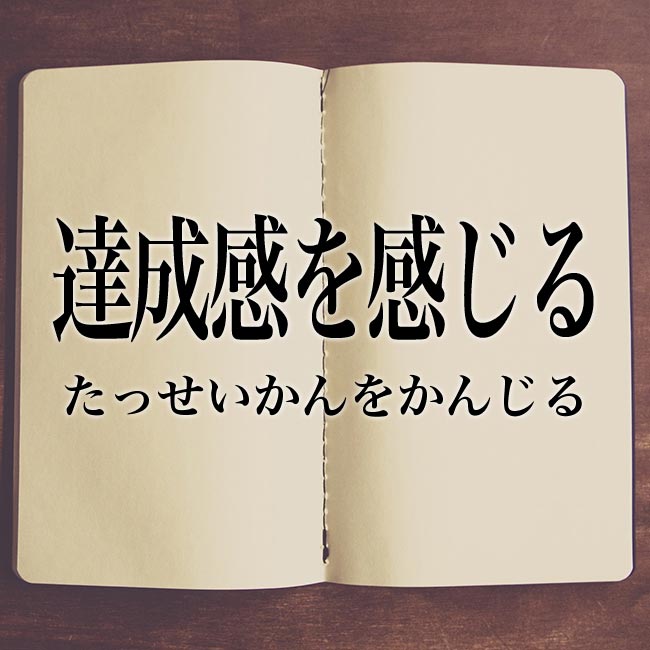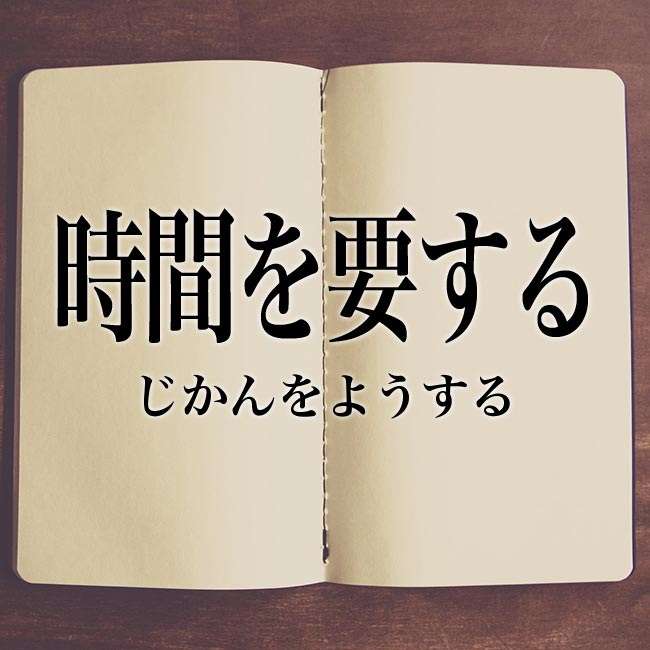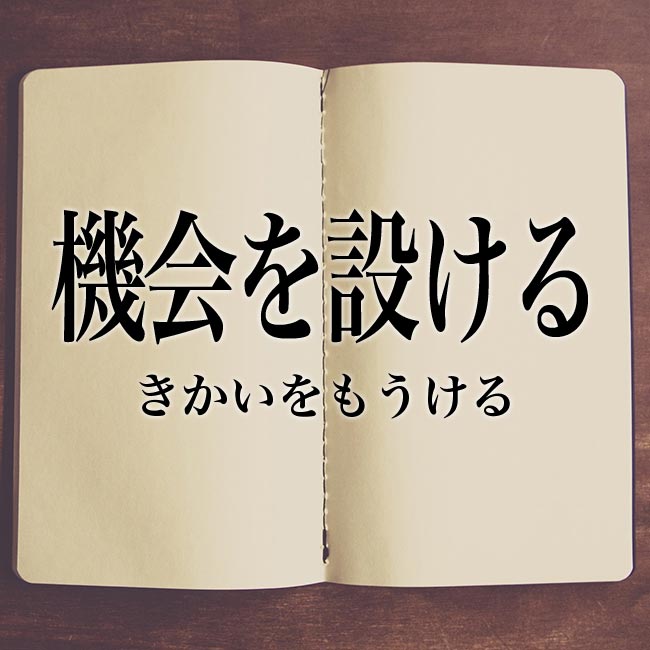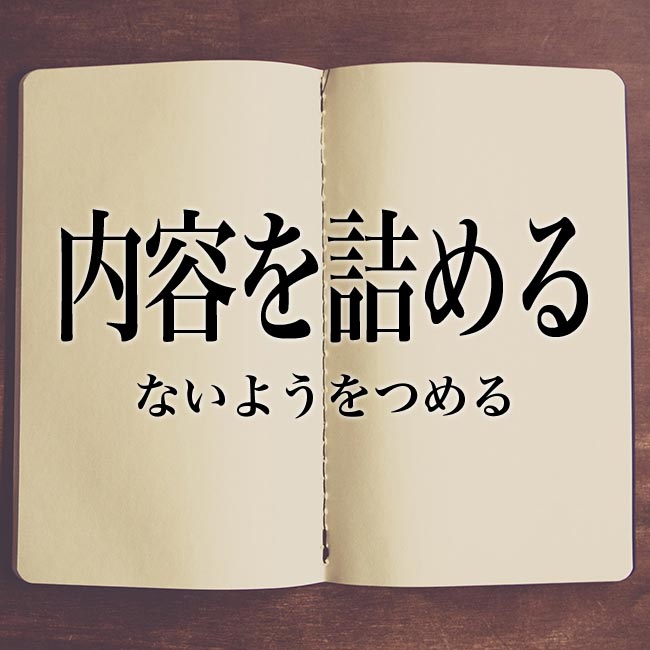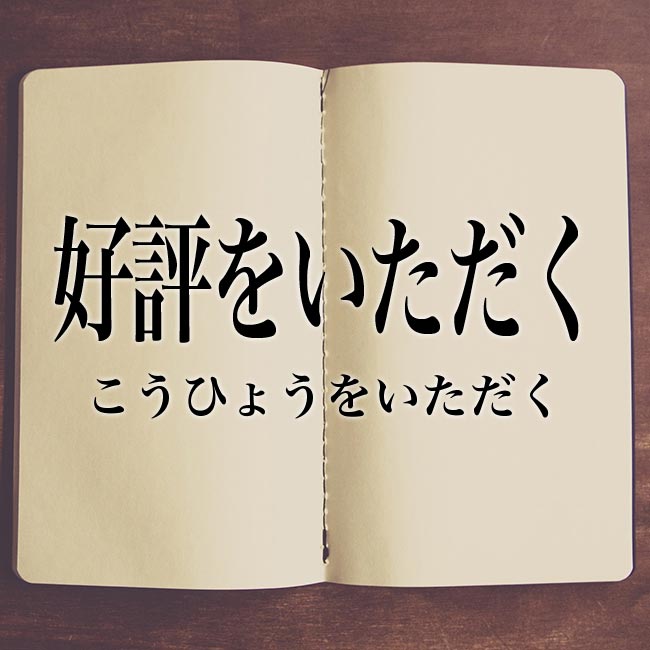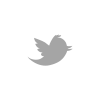「罰が当たる」の意味とは?類語、使い方や例文を紹介!
自分自身が何か後ろめたい事をしたり、悪い事をしてしまった時に「バチが当たるかも。」と思った事はないでしょうか。
またはニュースなどで不快な事件が流れたら、見も知らぬ犯人に対し「そのうちバチが当たるよ」や「バチが当たればいい」と思った事があるかもしれません。
何気なく使い、子供の頃から聴き慣れている、この「バチが当たる」という言葉について今回はお話ししたいと思います。
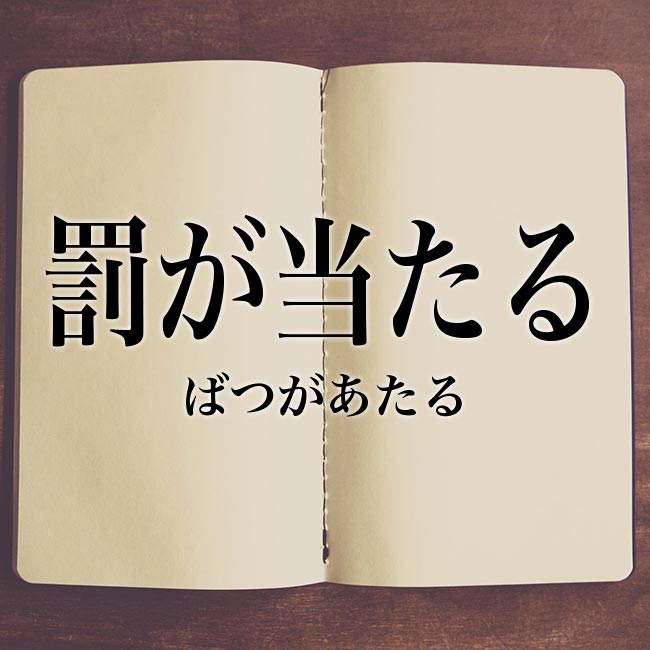
目次
- 「罰が当たる」の意味とは?
- 「罰が当たる」の類語や似たことわざ
- 「罰が当たる」の使い方
- 「罰が当たる」を使った例文
- 「罰が当たる」の反対語や対照語・対義語
- 「罰が当たる」のバチとは
「罰が当たる」の意味とは?
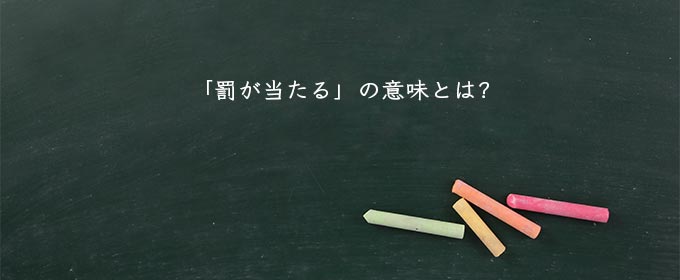
「罰が当たる」は「バチがあたる」と読みます。
普通に読むと「バツがあたる」になると思いますが、この「バチがあたる」の「バチ」は呉音と呼ばれるもので、音読みの一種になります。
音読みには漢音と呉音があり、呉音とは方言のようなものになります。
六朝時代の中国の呉と交流のあった朝鮮の百済人が日本に伝えたもので中国南方系の字音に基づくといわれていますが、現在では殆どが仏教関係の用語として用いられています。
そしてこの「罰が当たる」とは神仏において悪事を懲らしめるための償いや報いを受ける事を表しています。
罰と罪ひ表裏一体であり、人によってその罪深さや罪の種類は違いますが、どんなものであろうと反省をしその罪を認め償わなければいけません。
人間は完璧ではないので必ず間違いを起こしますし、ミスを犯します。
ですから罪を犯してしまう事は仕方がないところがありますが、そのままでは言い訳ではないので、償い省みるためにも「罰」があるのです。
ですから「罰が当たる」という気持ちを持つ事や、この言葉を使い表現をするという事は心の中に良心があるという事であり、そもそも何も考えず自分の事だけを考えている人や、倫理観や道徳観を持っていない人はこの言葉を使う事もないでしょうし、このような感覚もないかもしれません。
「罰が当たる」の類語や似たことわざ
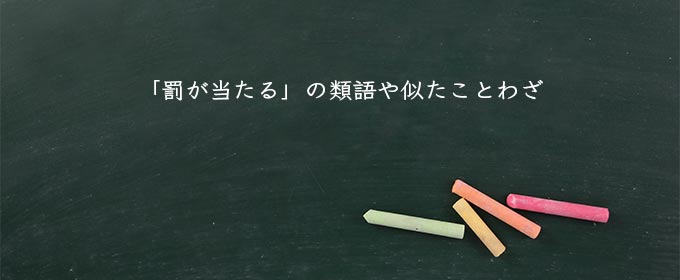
- 「天罰が下る」【てんばつがくだる】
- 「因果応報」【いんがおうほう】
- 「ミイラ取りがミイラになる」【みいらとりがみいらになる】
「天罰が下る」【てんばつがくだる】
神仏が下す罪への報いの事を言います。
または自らが行った悪事に対し罰が降りかかる事をいいます。
また同じような意味や言い方に「天誅【てんちゅう】を下す」という場合があります。
「因果応報」【いんがおうほう】
因果応報とは仏教用語であり、本来は善い行いも悪い行いも、自分に起こる全ての物事は自分が行なった事が原因という意味ですが、一般に浸透している意味は"悪事をした時"のみに返ってくるものだと思われています。
因果応報の意味は深く、物事には必ず原因と結果があり何もないところには何も生まれないという意味になります。
世の中に原因のないものはなく、分からない事はあっても、「ない」ものから生まれる結果はないという考え方になります。
つまり「罰が当たる」も原因がないと当たるはずがない事なので、考え方としては同じになります。
「ミイラ取りがミイラになる」【みいらとりがみいらになる】
ミイラ取りがミイラになるとは、人を連れ戻す為に出向いた者が、その目的を果たすどころか帰ってこなくなることをいいます。
もしくは人を説得しようとした者が、逆に相手に説得され同調してしまうことをいいます。
そしてこの言葉の語源の"ミイラ''とは、ミイラ“mirra”という死体に塗る防腐処理に使われた樹脂(没薬/もつやく“myrrh”)のことで、布にこの薬を塗布したものを"死体"(ミイラ)に巻き棺に入れると腐敗が防げるといわれていました。
ですからこの"ミイラ''を採りにいく為に人々が砂漠を渡ったり、お墓に入ったりする必要があったため、本人が命を落とし"ミイラ''になる場合があったところから来ているといわれています。
ミイラになってしまう事自体は「罰が当たる」という事に該当する訳ではありませんが、自分のした事がそっくりそのまま返ってくる、もしくはなんらかの形で返るという意味では同じ意味合いがあると言えるでしょう。
「罰が当たる」の使い方
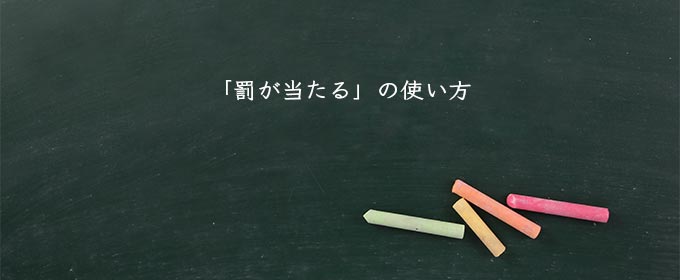
「罰が当たる」は自分に対しても使いますが、他人に対しても使います。
人の気持ちや行為を顧みない行動を取ったり、感謝がなく、そうなって当たり前だと思っているような人物や状況などにも使います。
そしてもちろん誰かを傷付けたり、騙したり、嫌がる事を平気でする様な相手に対しても使います。
「罰が当たる」を使った例文
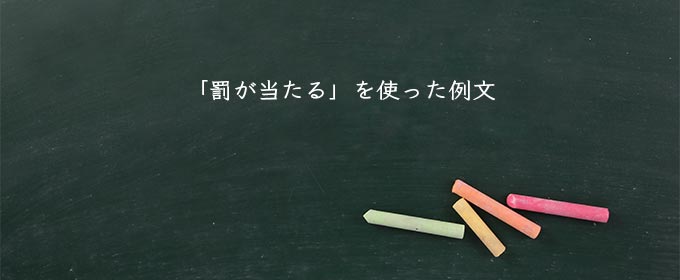
- 「最後まできちんと食べなさい。ご飯を残すと罰が当たるわよ。」
- 「あんなに良くしてもらったのに裏切るなんて、きっと罰が当たるに違いないし、当たった方がいい。」
- 「こんな事して罰が当たったらどうしよう。」
- 「そんなに綺麗な顔でスタイルもいいのに文句を言うなんて罰があたるよ。」
「罰が当たる」の反対語や対照語・対義語
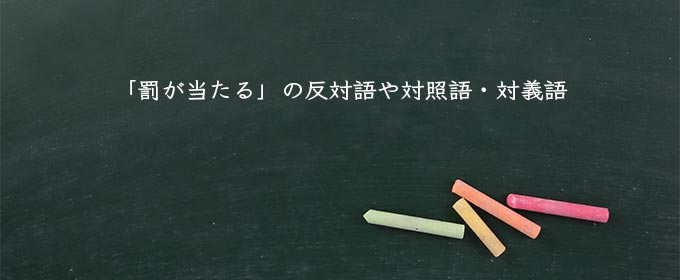
- 「御加護」【ごかご】
- 「御利益」【ごりやく】
「御加護」【ごかご】
神仏から守ってもらえる事をいいます。
特にキリスト教の方は、「あなたに神のご加護がありますように」と挨拶として使う事があります。
「御利益」【ごりやく】
神仏から受けられる恩恵、恵の事になります。
物理的なものから精神的な事まで多岐に渡ります。
「罰が当たる」のバチとは
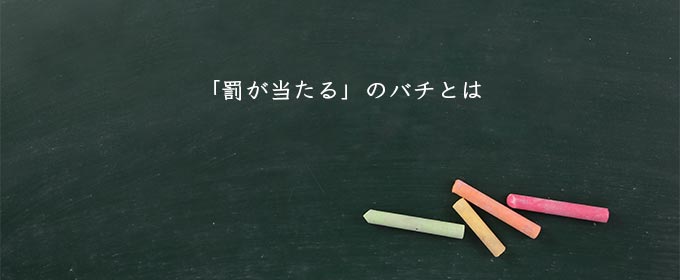
- バチにも種類がある
- 感覚的なバチ
- スピリチュアルな面から見たバチ
バチにも種類がある
「罰が当たる」のバチとは先述した通り「罰」の事であり、自分が行った事に対する天からの報いを受ける事や償う事をいいます。
ですがバチとは、本人に良心の呵責があり物事の道理をわかっていないと意味がありません。
何が起きても反省せず、責任転嫁し、悪事を平気で行う人はたとえバチが当たっても気付かず、その時でさえ他人の責任にするでしょう。
「何で自分がこんな目に遭わなければいけないんだ」と開き直ったり、思い当たる節があったとしても自分の責任とは思わず、周りの人や環境のせいにしてしまうでしょう。
一見するとこんな人には「バチの意味なんてない」と思ってしまいそうですが、冷静に客観視してみるとそのような人に心を許し、いざという時に助けてくれる人などいるかどうかがわかる筈です。
また利害関係で助けた仲は継続性は低いのではないでしょうか。
人間は一人では生きていけないので、必ずどんな形であれ大小問わず他人の力を借りているのですが、その力とは知性や知恵、情報なども含まれます。
つまりバチとは目に見えて痛い目に遭うだけではなく、徐々にと追い込まれたり、自覚はないけど気付いたら自分だけが取り残されているという事もバチにあたるのではないでしょうか。
感覚的なバチ
例えば同じサービスでクォリティが受けられるものが半額になっていたとします。
その情報を普段から「バチが当たればいいのに」と思っている相手に伝えるでしょうか。
通常は仲良しの人やお世話になっている人など一緒に幸せを感じたい人に対して、情報を提供したり共有するのではないでしょうか。
つまり一人の一出来事としては影響力は小さいものでも、それが何人もいたり、継続的に行われた場合を考えると損害は大きくなるはずです。
そしてこれがビジネスや緊急時になると大変な事になりますし、命に関わってくるかもしれません。
一つずつは小さな事柄でも、積み重ねることで人脈にも影響が出てきますし、チャンスを失うことにも繋がるのです。
バチとは自分がしたことに対する報いを受ける事なので、形や種類、期間や質などは関係ありません。
むしろどんな形で返ってくるか分からないからこそ、良心がある人には怖い事なのだと思います。
もちろんバチに当たりたくないからという理由は不順になりますが、バチを怖がる事は大切な事なので、気付いたら何もなくなっていたという場合もバチが当たったからかもしれません。
スピリチュアルな面から見たバチ
スピリチュアルな面から見るとバチは当たらないといわれています。
正確にいえば本人が気付かなければバチにはならないのです。
また天や神仏、ましてや人は人に対しバチを与える事が出来ないと考えられています。
それはバチがネガティブなものであり、そのマイナスのパワーを他人に与えるという事は、自分に向かって返ってくる事に繋がるからです。
ましてや過ちを犯す事が当然である人間が、人間に対して「罰が当たればよい」と思う事自体が非常に罰当たりな事だと考えられるからです。
そんな他人に対するネガティブなエネルギーは自らの肉体や精神を蝕み、マイナスオーラを放ち纏う事になってしまいます。
結局は他人の人生ではなく自分の人生を狂わす事になってしまうのです。
では実際には何も変わらないのかといえばそうではありません。
自分がネガティブなエネルギーを持てばそのオーラを纏うと述べましたが、それは本人の意思に関係なくそうなるものだと考えられるので、逆を言えば、自分のオーラに気付いていない場合も多々あるという事になります。
まず罰当たりな事を平気で行い、悪事に対し何とも思わない人物は、自分が纏うオーラ、顔付きなどに気付いていない場合が少なくありません。
胡散臭さや嘘っぽさ、その人物から滲み出る何とも言えない負のエネルギーというものは他人が感じる事ですし、たとえ指摘を受けたり、自ら気付いても直しようがありません。
その人が生きてきた価値観や人生そのものが現れているものなので、考え方を改めたり価値観や倫理観など全てを見直さない限り染み付いたものは取る事が出来ないのです。
そしてまた人間は自分と同じような波動を持つ人と付き合い、仲を深めるものです。
類は友を呼ぶと言いますが、似た者同士ではないと疲れてしまうので、胡散臭く道徳観がない人には同じような人物が周りを固める事になるでしょう。
つまり「罰が当たる」とはバチに値する事柄を自ら引き寄せている事になります。
胡散臭いネガティヴなところに穢れのない純粋でポジティブな人は寄ってくる事はないように、結局は自らが気付かない限りバチの中に居続ける事になるでしょう。
「罰が当たる」と思う行為の程度は人それぞれ違うので、心配性の人と大雑把な人とでは捉え方は違ってくるでしょう。
ですが大切な事は誰かを傷付けたり、自分の事しか考えていないと一瞬でも感じたのであれば、バチが当たるかもしれないという事ではないでしょうか。
痛い目に遭いたくないから悪事をしないという発想は根本的にずれてはいますが、悪事はバチが下るに等しい事だと分かっているのであれば、バチが当たる・当たらないを気にしないような生き方をしたいものです。