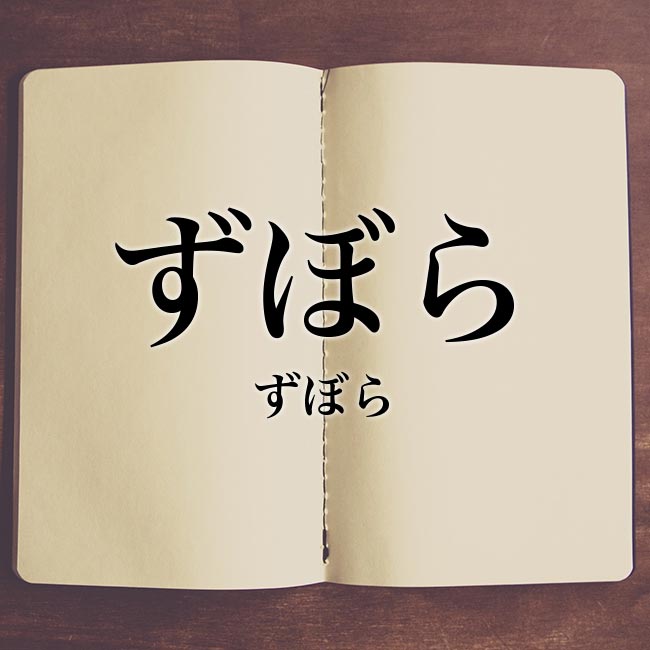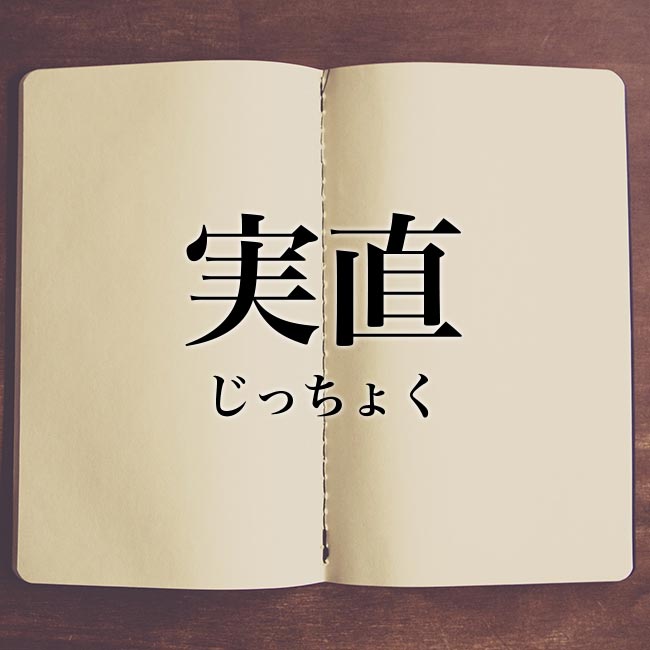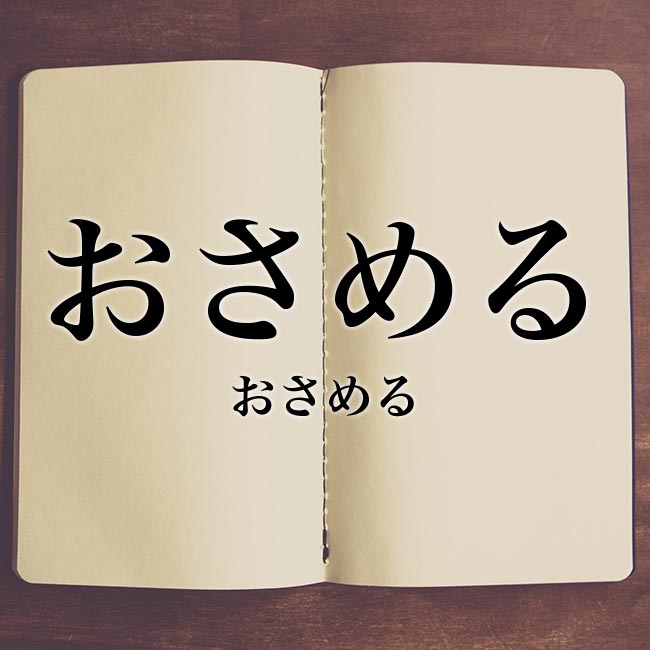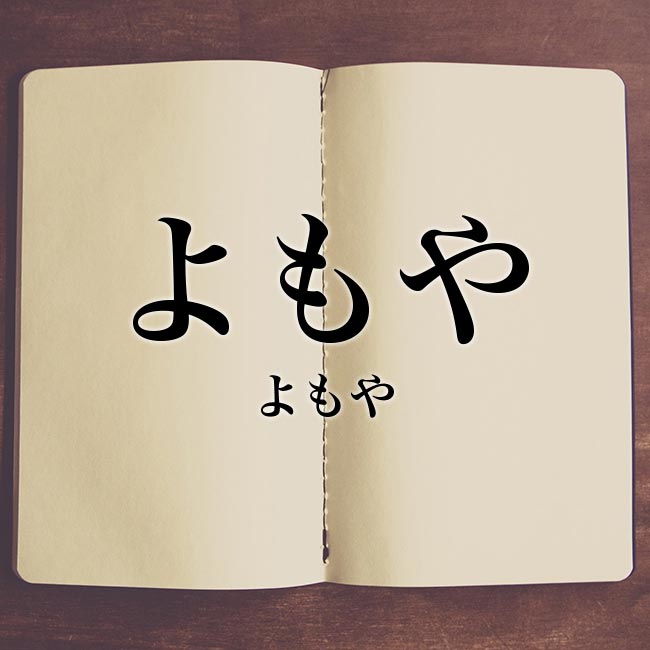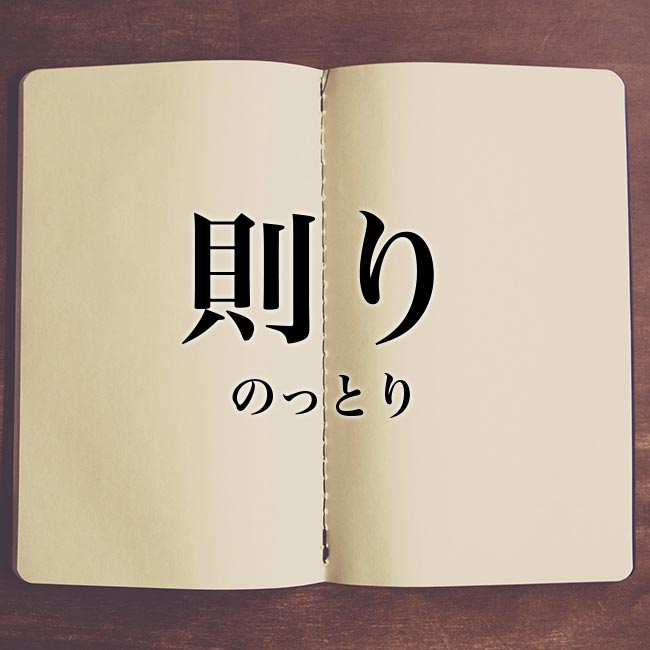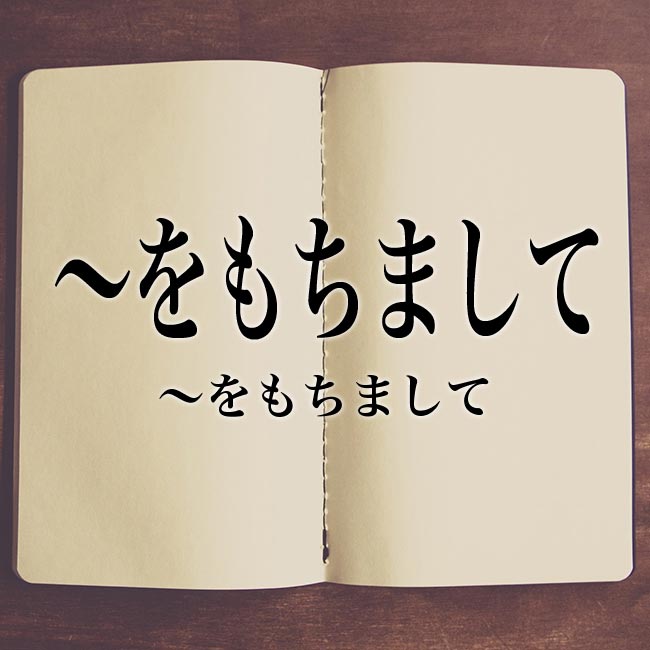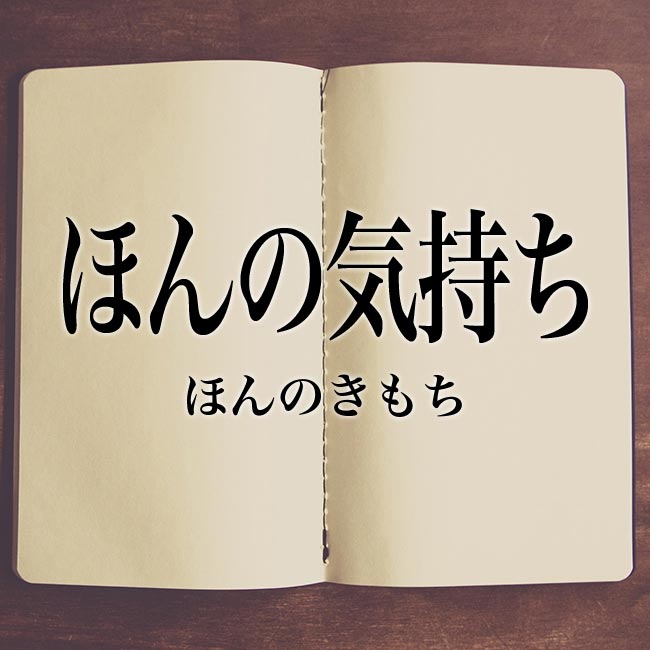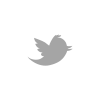「律儀」とは?意味や類語!例文と解釈
ビジネスや日常会話で「律儀」という言葉が使われることがあります。
一体どの様な意味なのか、類語や例文なども併せて紹介します。
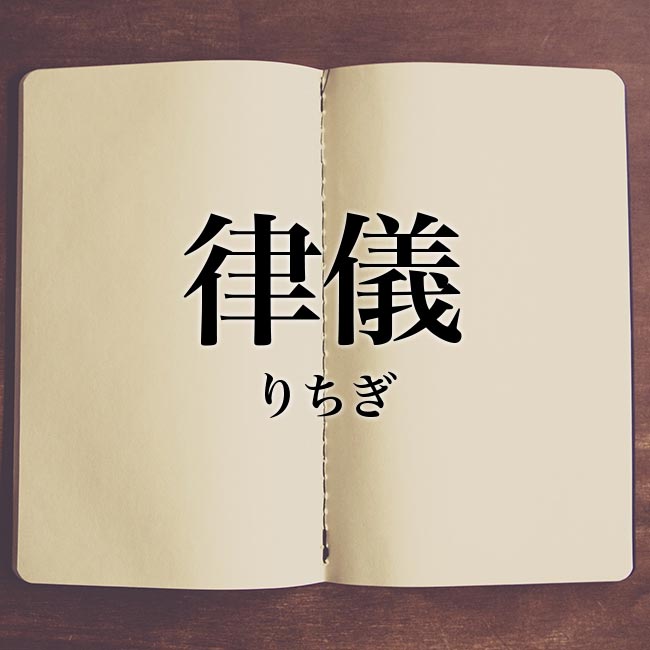
目次
- 「律儀」とは?
- 「律儀」の表現の使い方
- 「律儀」の対義語
- 「律儀」を使った例文と意味を解釈
- 「律儀」の類語や類義語
「律儀」とは?
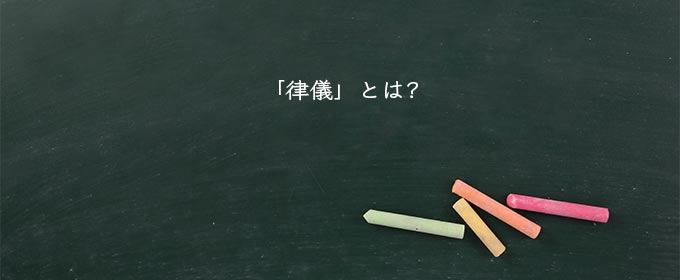
「律儀」の意味は、「極めて真面目て義理堅い人のこと」です。
世の中には人と接する上での礼儀やルールなどがありますが、個性が尊重される現代では礼儀が欠ける人も増えています。
その様な人達の中で、あくまで礼儀を重んじて常にきちんと行動する人のことを言います。
具体的には「約束は必ず守る」「社会のルールを守る」「自分の損得を考えて行動しない」など、基本的なことですが、いざ守ろうとするとエゴが出てしまい難しいことが挙げられます。
全てにおいてきちんとやり遂げる性格で、周囲から見れば少し堅苦しくて付きあいにくいと思う面もあります。
- 「律儀」の読み方
- 「律儀」の言葉の成り立ち
「律儀」の読み方
「律儀」の読み方は「りちぎ」になります。
「りつぎ」と読み間違えない様にしましょう。
「律儀」の言葉の成り立ち
「律儀」の「律」は、「りつ」と読む時には「社会で秩序立った行動をする為のおきて」という意味で、「りち」と読む時には「おきてや決まりに従うこと」という意味があります。
「儀」は「姿が整っている様子」「正しい作法」「手本」「模型」「その件に関する事柄」という意味があります。
これらの言葉が組み合わさり「形式の整った正しい作法の決まりに従うこと」として使われています。
「律儀」の表現の使い方
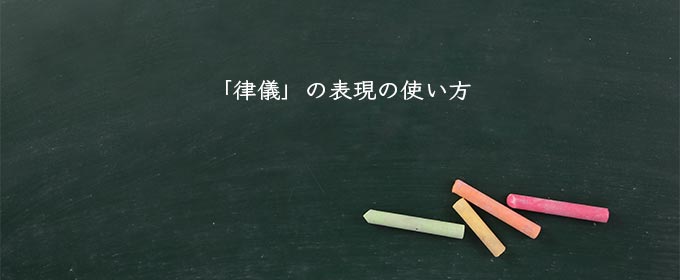
「律儀」の表現の使い方を紹介します。
- 文法的な使い方
- ビジネスでは良いイメージ
文法的な使い方
「律儀」は名詞であり、文末に使う時には形容動詞として「律儀だ・である」となります。
形容詞として使う時には「律儀な〇〇」になり、副詞として使う時には「律儀に」になります。
ビジネスでは良いイメージ
「律儀」はプライベートであまり真面目過ぎると堅苦しい人というイメージですが、ビジネスでは「信頼できる人」という良いイメージになります。
「義理堅く約束は必ず守る」という点で、顧客から信頼される要素になり、面接などで自己PRとして使える言葉です。
「律儀」の対義語
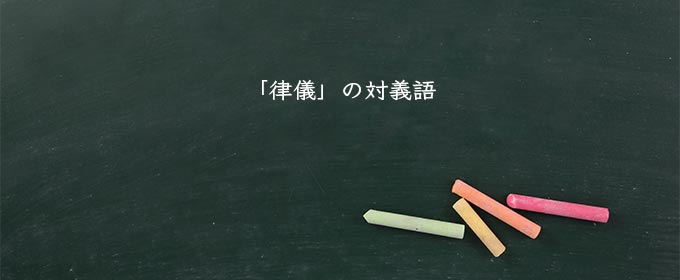
「律儀」の対義語を紹介します。
- 「ずぼら」【ずぼら】
- 狡猾【こうかつ】
「ずぼら」【ずぼら】
「するべきことをしなかったり、だらしのない性格のこと」という意味です。
語源は関西地方の方言で、「凹凸がなくつるつるな様子」を意味する「ずんべらぼん」「ずんぼらぼん」が変化した言葉です。
狡猾【こうかつ】
「ずる賢くて、常に自分だけ利益を得ようと悪知恵を働かせる人のこと」という意味です。
「律儀」を使った例文と意味を解釈
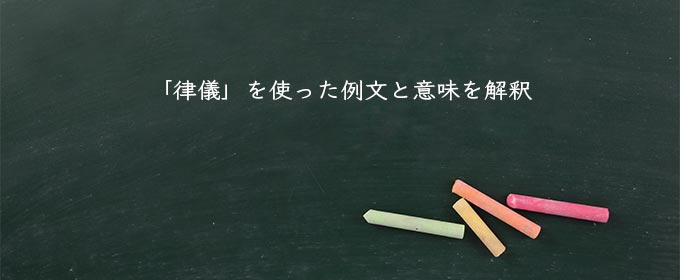
「律儀」を使った例文と解釈を紹介します。
- 「律儀」を使った例文1
- 「律儀」を使った例文2
「律儀」を使った例文1
「彼は非常に律儀な人で、毎年必ずお歳暮を送ってくる」
昔何かで世話をしたり、会社の部下だったなどの関係がある人が、その関係が解除されても恩義を忘れずにずっとお歳暮を贈り続けていることを表しています。
「律儀」を使った例文2
「あの人は約束を必ず守る律儀な人だ」
「行けたらいく」などとあいまいな返事をしたり、ドタキャンなどはせずに、「イエス・ノー」をはっきりと言い、約束をしたら必ず守る人のことを言っています。
非常に信頼がおける人物であることを表しています。
「律儀」の類語や類義語
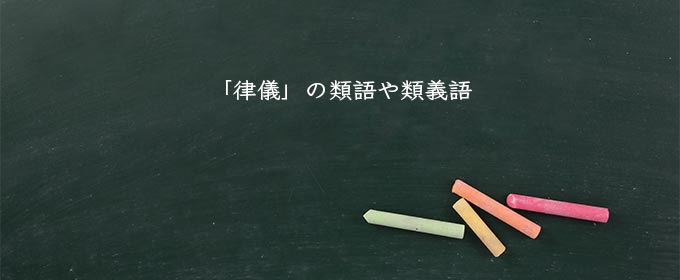
「律儀」を使った類語と類義語を紹介します。
- 「実直」【じっちょく】
- 「堅気」【かたぎ】
「実直」【じっちょく】
「誠実で性格に表裏がなく、真面目にものごとに対応する人」という意味です。
「堅気」【かたぎ】
「真面目でブレない心を持っていること」「人に対して恥じない職業や生活をしていること」という意味です。
「律儀」は「極めて真面目て義理堅い人のこと」という意味です。
決まりや約束をきちんと守り、損得勘定なしで行動する人に対して使いましょう。