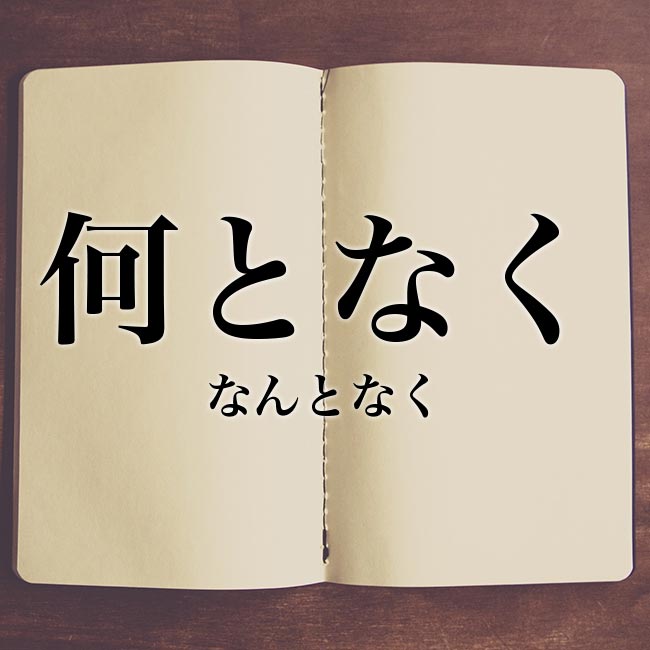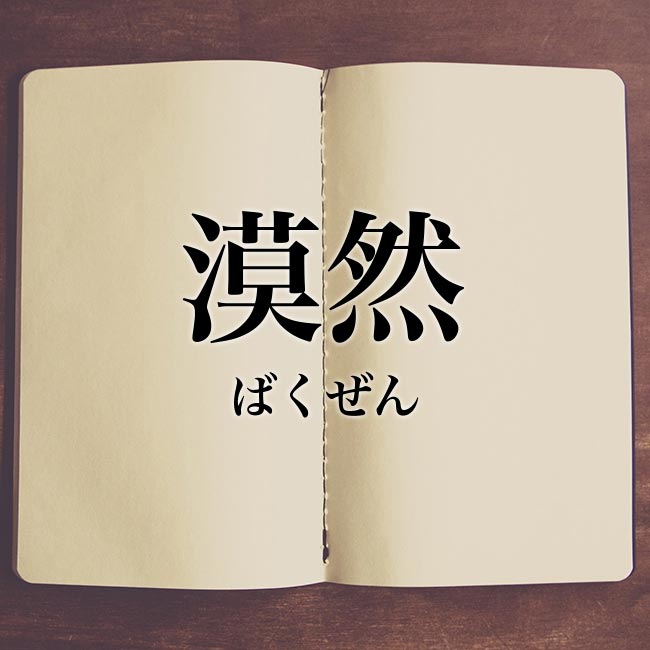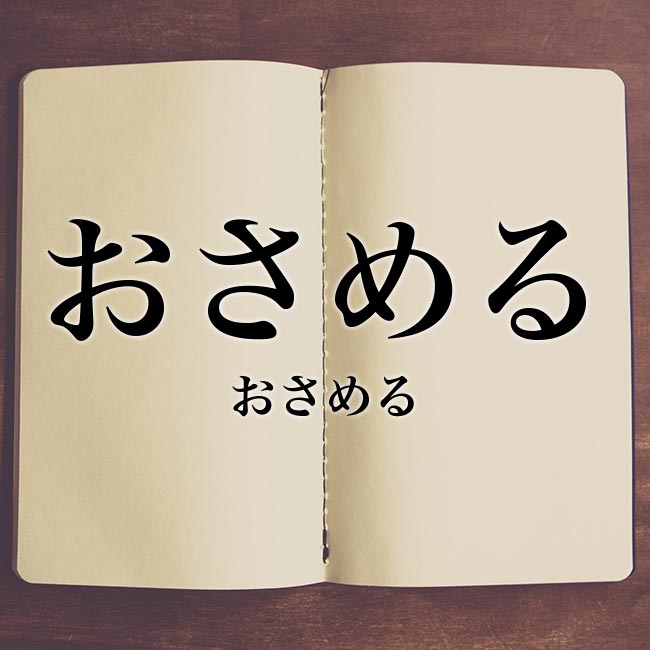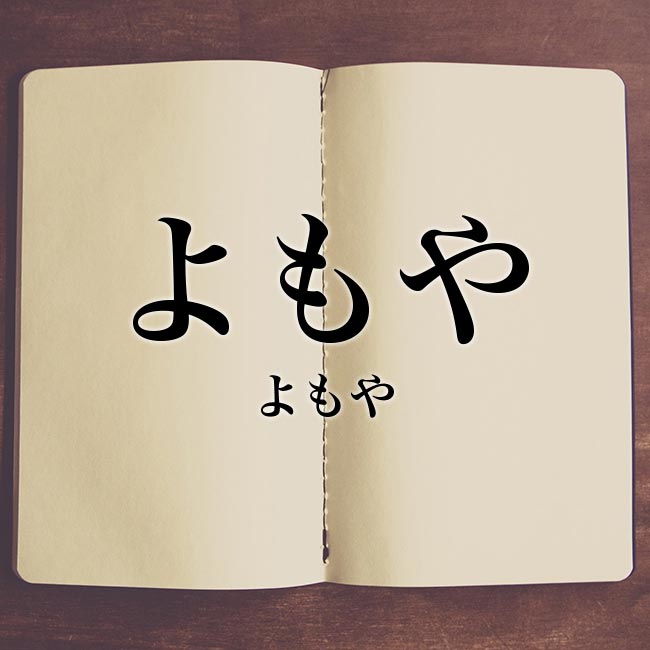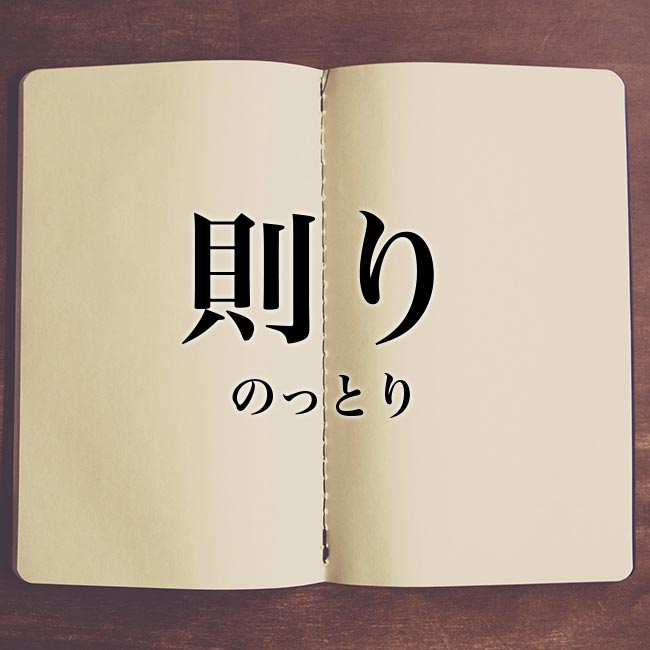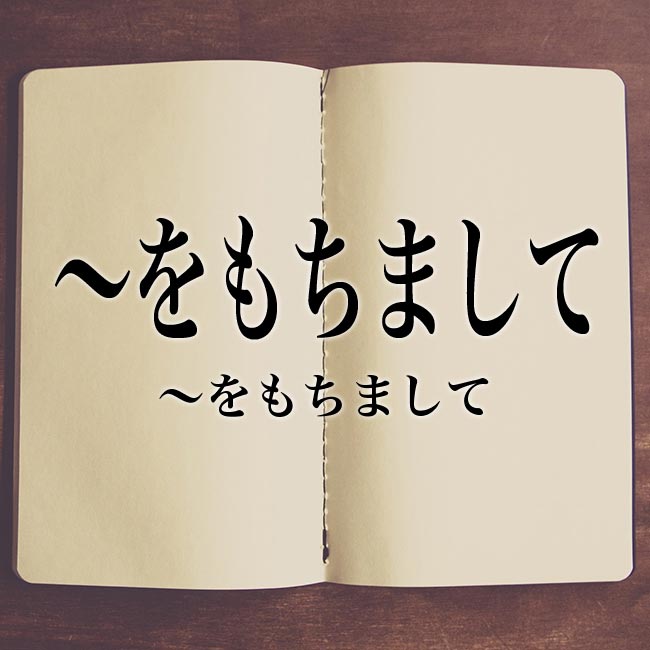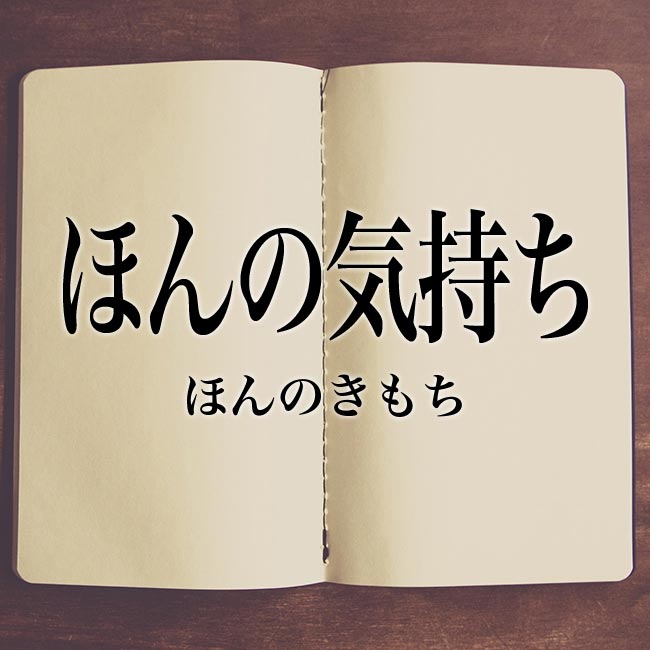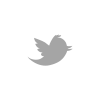「そこはかとない」の意味とは!類語や例文など詳しく解釈
文学小説などで「そこはかとない」という言葉をみかけることがあります。
一体どの様な意味なのか、語源や使い方なども併せて紹介します。
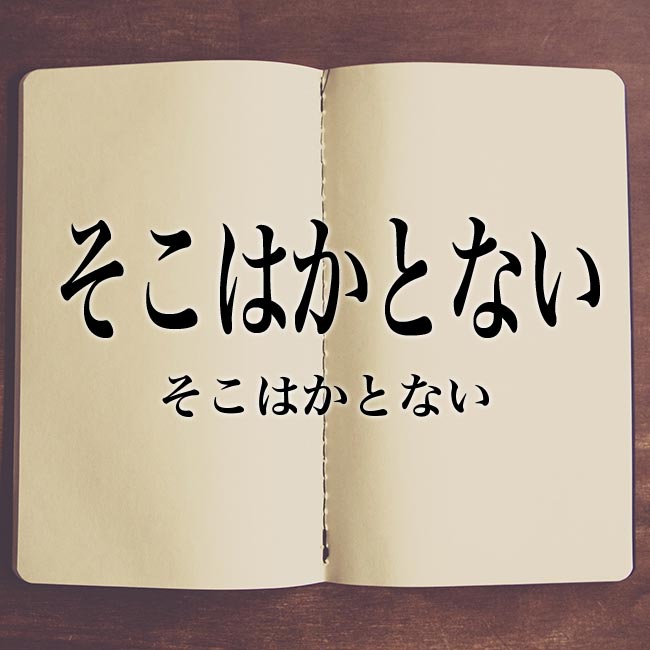
目次
- 「そこはかとない」とは?
- 「そこはかとない」の表現の使い方
- 「そこはかとない」を使った例文と意味を解釈
- 「そこはかとない」の類語や類義語
「そこはかとない」とは?
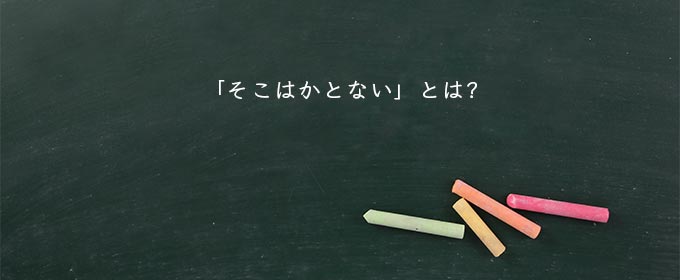
「そこはかとない」の意味と語源について紹介します。
- 「はっきりしないけれども感じられること」の意味
- 「とりとめもない」の意味
- 「際限がない」の意味
- 「そこはかとない」の語源
「はっきりしないけれども感じられること」の意味
その理由や場所がはっきりしないのですが、全体的にその様に感じられることを言います。
取り立ててどこがどうと指摘できないのですが、全体像からそのものの本質や性質を理解できる時の表現です。
「とりとめもない」の意味
まとまりや結論がなく、特に重要性もないことを言います。
要点がはっきりしない軽い内容のことを表します。
「際限がない」の意味
古文ではこちらの意味で使われていましたが、現代で使われることは殆どありません。
「そこはかとない」の語源
「そこはかとない」の語源は、平安時代の文学作品「堤中納言物語」に記された「そこはかとなき物語しのびやかにして」という文が最初と見られています。
また、最も知られている文として鎌倉時代に書かれた「徒然草」の中の「そこはかとなく書きつくれば」があります。
どちらも「まとまりがない」「際限がない」という意味で使われていて、段々と「ぼんやりとしている」「はっきりとしない」という意味に変わっていったのです。
「そこはかとない」の表現の使い方
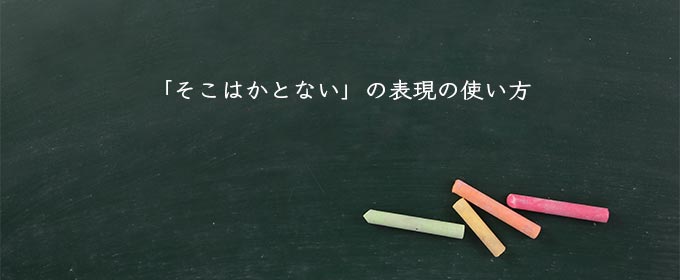
「そこはかとない」は「自分ではそう思うが上手く説明できない」という時に使われます。
ただ「何となく感じる」と言うのでは味気ない時に「そこはかとなく感じる」と言うと、非常に風流なイメージになります。
古来からある言葉で「論理的ではない」という意味を含むので、ビジネスで使うのには不向きでしょう。
「そこはかとない」を使った例文と意味を解釈
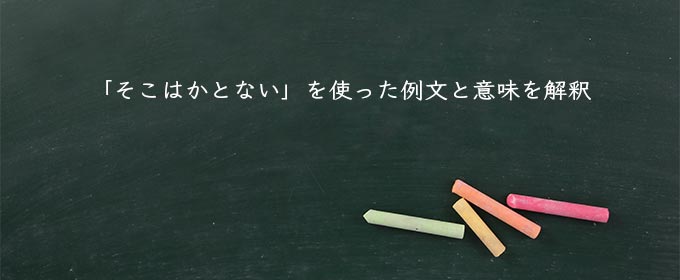
「そこはかとない」を使った例文と解釈を紹介します。
- 「そこはかとない」を使った例文1
- 「そこはかとない」を使った例文2
「そこはかとない」を使った例文1
「そこはかとない良い香りがする」
人の家の庭を通りかかった時に、柵で中は見えないものの、季節の花々が咲き乱れているので良い香りが漂ってきていることを表しています。
「そこはかとない」を使った例文2
「そこはかとない懐かしい雰囲気の街並みだ」
レトロな造りの家があったり、駄菓子屋があったりなど、下町の雰囲気がする街並みで、懐かしいと感じることを表しています。
「そこはかとない」の類語や類義語
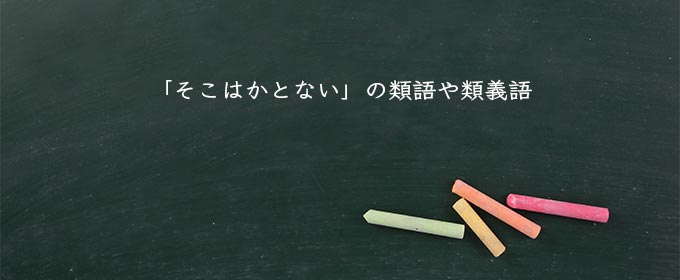
「そこはかとない」の類語を紹介します。
- 「何となく」【なんとなく】
- 「漠然」【ばくぜん】
「何となく」【なんとなく】
「はっきりとした理由なくその様に感じたり思ったりすること」という意味です。
シンプルですが「そこはかとない」の言い換えとして使われます。
「漠然」【ばくぜん】
「あいまいで不確かなこと」という意味です。
ぼんやりとしていてはっきりと分からない時に使われます。
「そこはかとない」は「はっきりしないけれども感じられること」「とりとめもない」「際限がない」という3つの意味があります。
非常に風流な言葉ですので、日常会話で使える様にしておくとオシャレです。