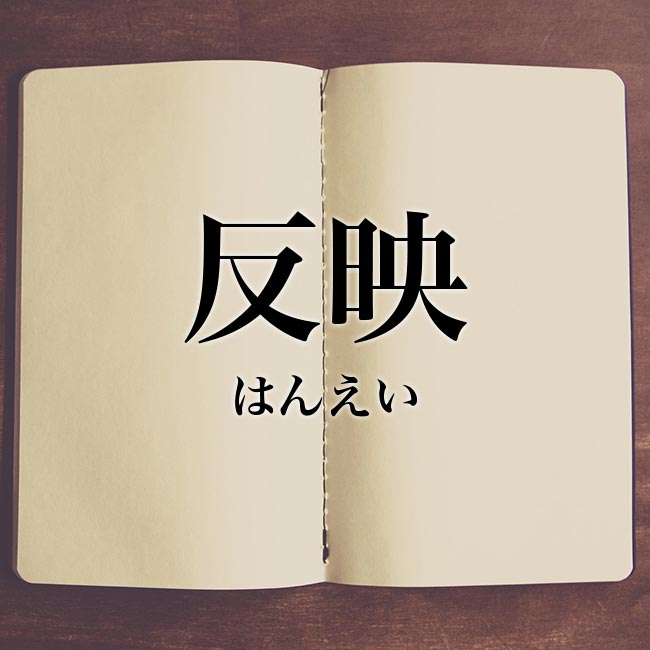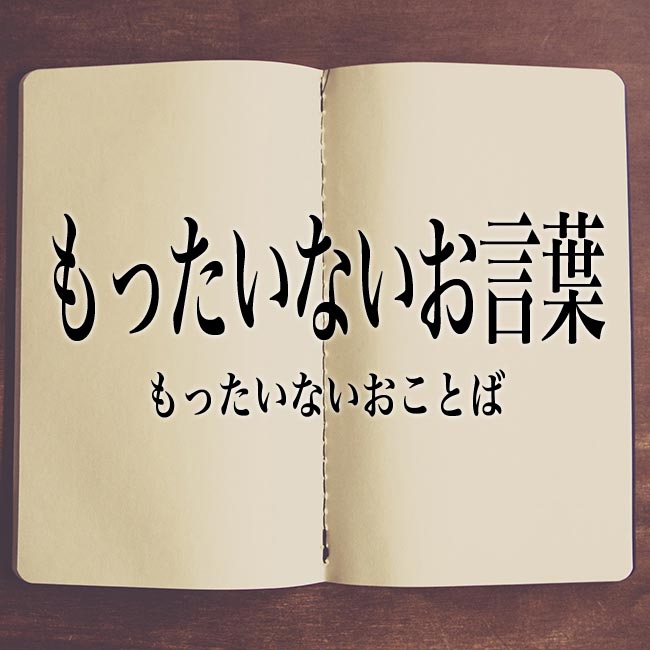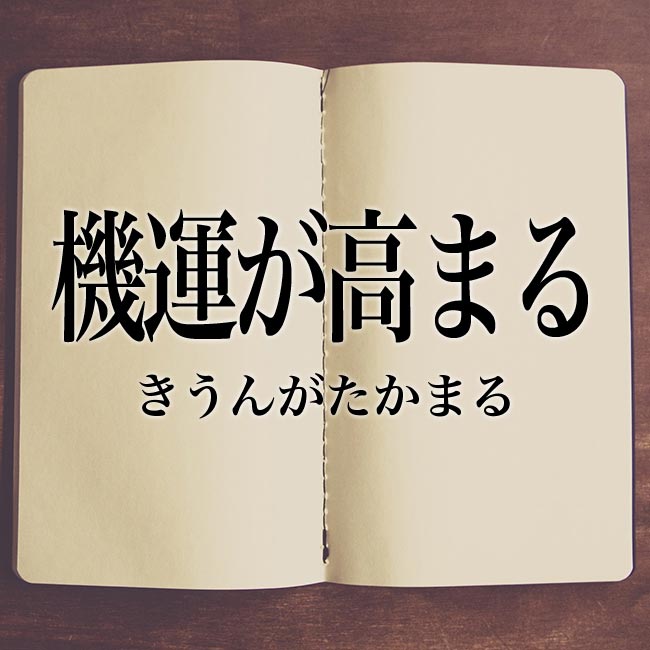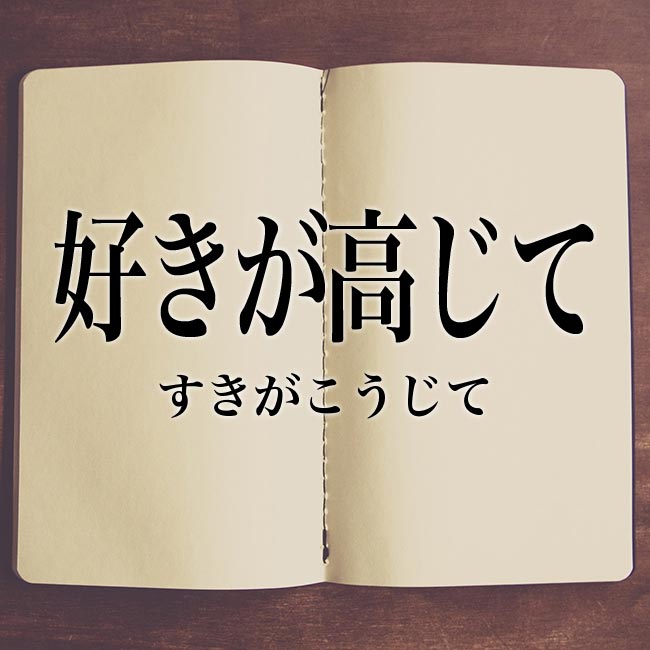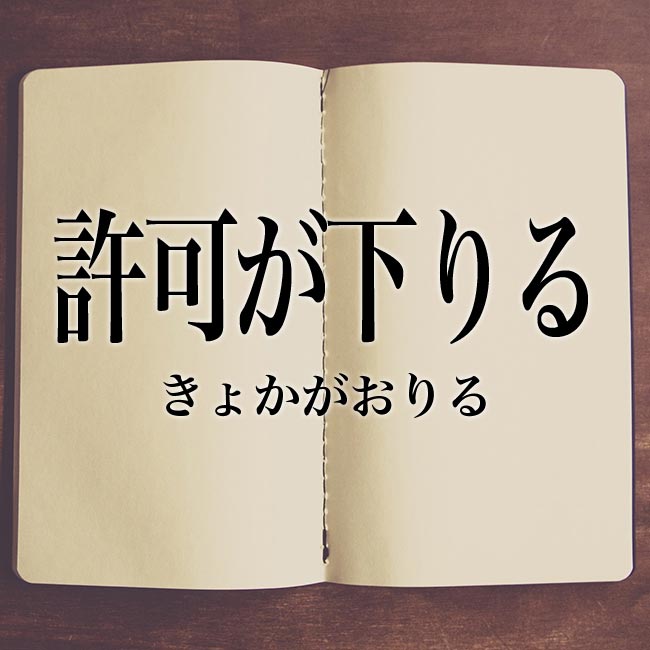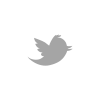「三文役者」とは?意味!類語や言い換え
この「三文役者」は、あまり聞かない表現ですが、このタイトルの映画も存在しており、現在でも使われることがある言葉です。
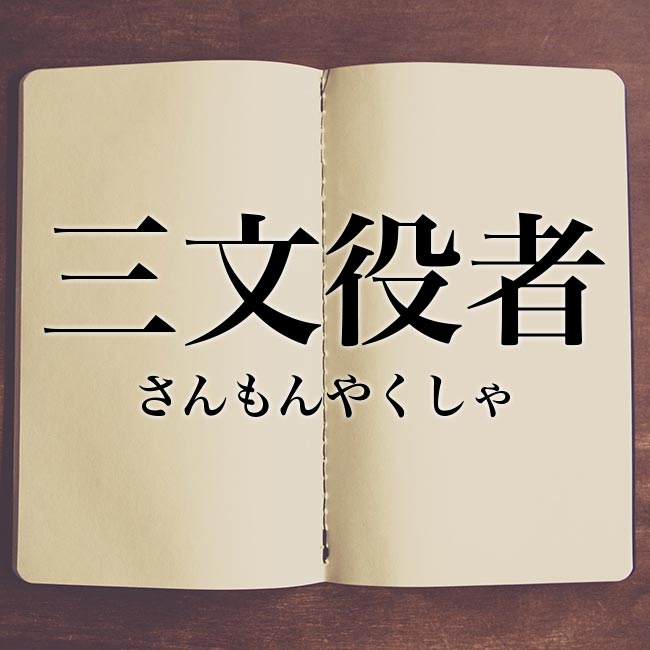
目次
- 「三文役者」とは?
- 「三文役者」の三文とは?
- 「三文役者」を使った例文と意味を解釈
- 「三文役者」の類語や言い換え
「三文役者」とは?
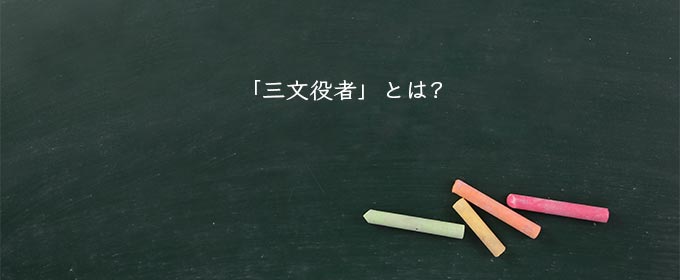
三文役者(さんもんやくしゃ)とは、演技の下手な役者のことを指して使います。
演劇用語なので、一般にはあまり見聞きする機会はありませんが、明らかに芝居掛かっていると分かる場合に、「まるで三文役者のようだ」などと使うことができます。
お芝居の世界でこのように呼ばれてしまうのは、演者として侮辱されたことになります。
その為、そうだと思っても本人の前で直接使えるのは、主に監督やプロデューサーなどのその演者より立場が上の人だけです。
自ら「俺はいつまで経っても三文役者だ」などと自嘲的に使う場合は何も問題ありません。
「三文役者」の三文とは?
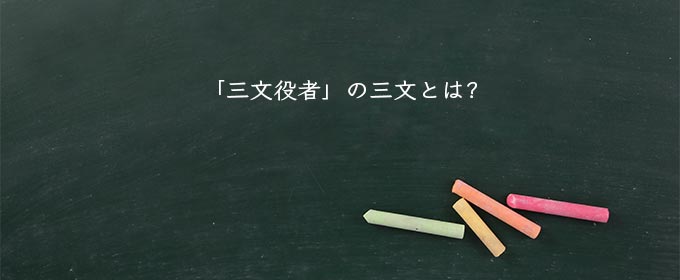
「三文」は、値段を考えることもないほど安い、価値がないといった意味で広く使われる表現です。
この「三文役者」では、演技が下手で演者としての価値がないという意味で使っており、その他にも、「三文芝居」(さんもんしばい、お金を払う気にもなれないつまらない芝居)、「三文判」(さんもんばん、簡単に購入できる判子)のような言葉に使われています。
尚、この三文の「文」は江戸時代の通貨の単位で、現在の貨幣価値にすると、三文で100円程度です。
「三文役者」を使った例文と意味を解釈
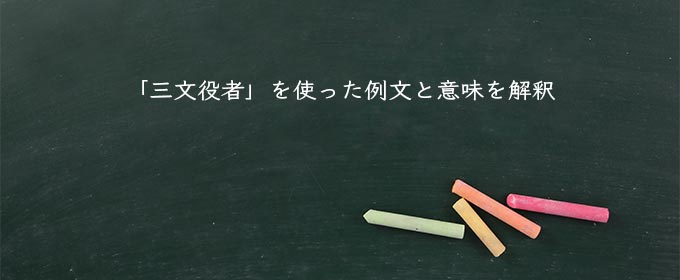
三文役者を使った例文と、その意味の解釈です。
芝居で使っている例と、一般で使う場合の例の両方を挙げていきます。
- 「三文役者」を使った例文1
- 「三文役者」を使った例文2
「三文役者」を使った例文1
「デビューしたての頃は三文役者と揶揄された彼だが、今や一端の縁者だ」
「一端の」は、一般にも認められるほどと捉えていい表現です。
大スターとまではいかないものの、縁者としてそれなりの立場にまで成長したと表現しています。
「三文役者」を使った例文2
「肝心な時のあいつの三文役者ぶりには困ったものだ」
肝心な時に、いかにも芝居掛かっているような素振りになってしまうことに対して苦言を呈しています。
ビジネスの世界では、時には芝居掛かることも必要ですが、それが明らかに分かるような素振りでは、当然相手にそれが分かってしまい、いい結果とはならないでしょう。
「三文役者」の類語や言い換え
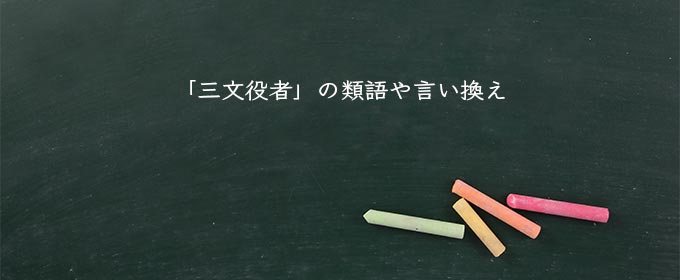
三文役者と同様の意味で使える言葉です。
こちらの方は、聞いたことがある人も多いでしょう。
- 「大根役者」【だいこんやくしゃ】
「大根役者」【だいこんやくしゃ】
三文役者と同じ意味で使う事ができる言葉です。
こちらは何故「大根」と表現するのかと言えば、大根が白いことから、「素人」(しろうと)と掛けている為です。
実質的に「三文役者」と同様に使われる言葉で、一般にはこちらの方が有名な表現です。
「三文役者」は、「大根役者」と同じ意味だと考えると分かりやすいでしょう。
新人のうちは仕方ありませんが、いつまで経ってもこのように呼ばれているようでは、芝居で大成するのは難しいと言わざるを得ないでしょう。