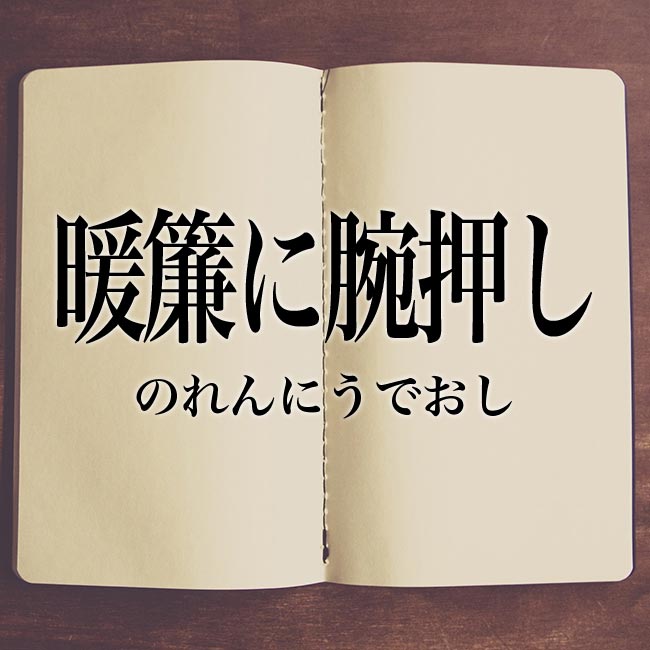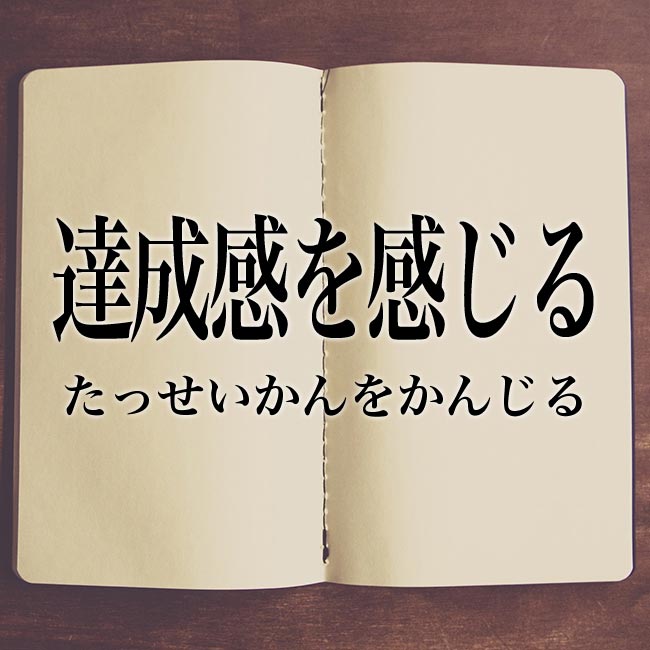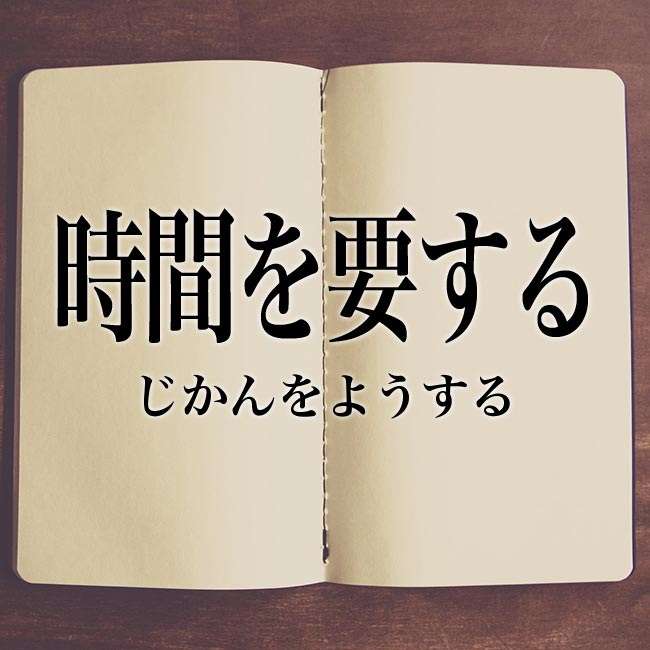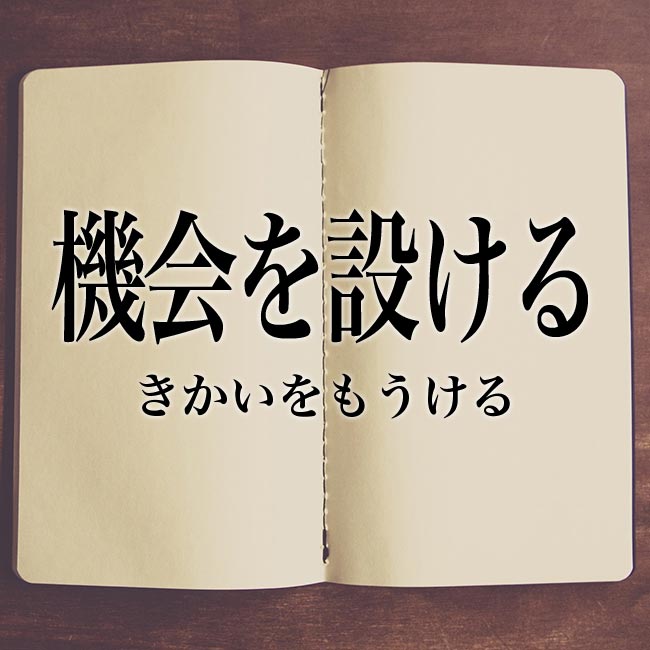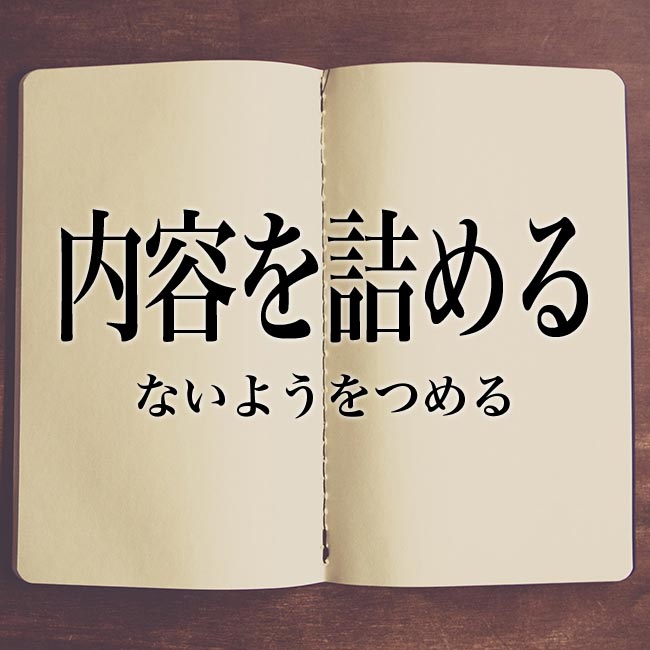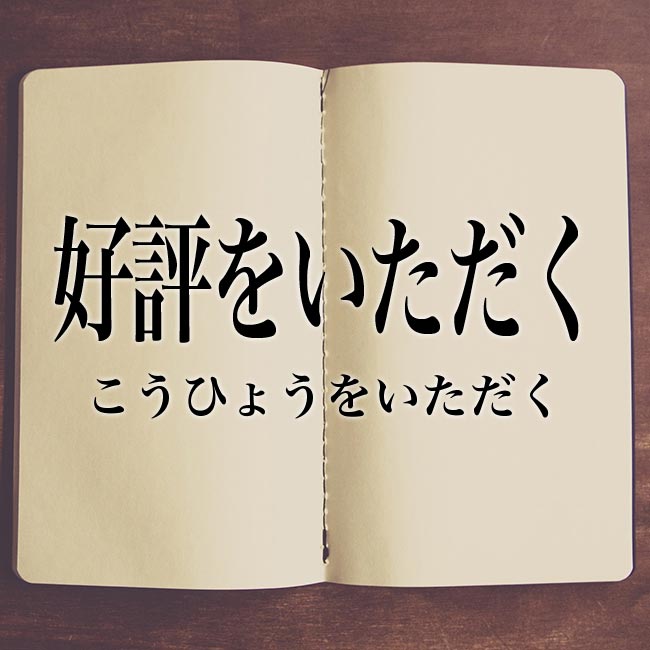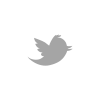「糠に釘」の意味・読み方・同じ意味のことわざ【使い方や例文】
「糠に釘」とは、「柔らかい糠に釘を打つように、何の手応えもないこと」や「全く効き目・変化がないこと」です。
「糠に釘」の「意味・読み方・同じ意味のことわざ・使い方・例文と解釈・英語・語源・釘を使ったその他のことわざ」などについて、詳しく説明していきます。
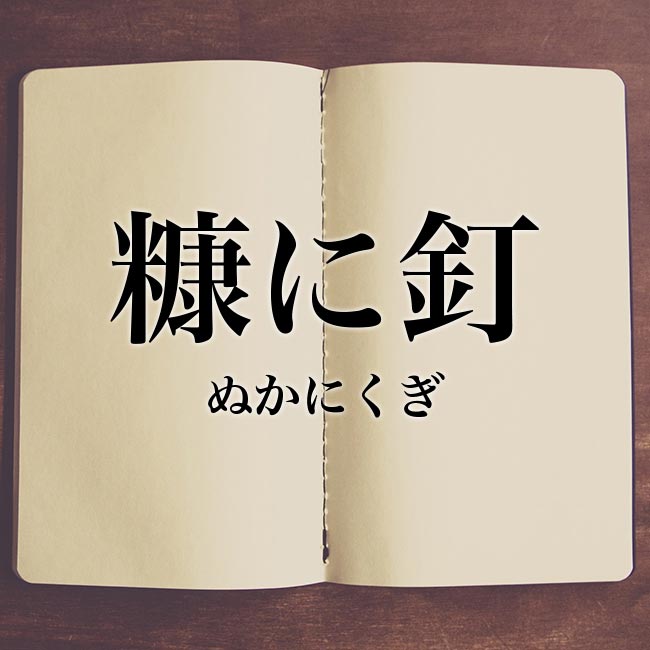
目次
- 「糠に釘」の意味とは?
- 「糠に釘」と同じ意味のことわざ
- 「糠に釘」の言葉の使い方
- 「糠に釘」を使った例文や短文(解釈)
- 「糠に釘」の英語
- 「糠に釘」のことわざと「ぬか床に釘をいれる漬け方」は全く関係ない?
- 「糠に釘」の語源や由来
- その他の「釘」を使ったことわざと意味を解釈
「糠に釘」の意味とは?
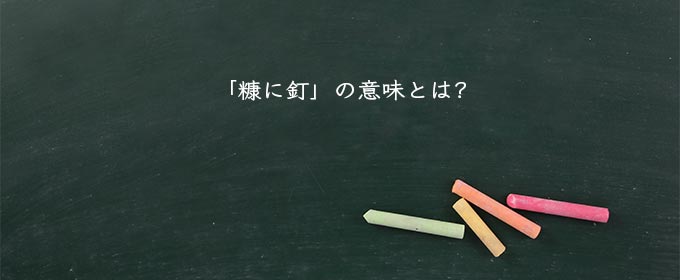
「糠に釘」の意味は、「柔らかい糠に釘を打つように、何の手応えも影響もないこと」や「どんなに働きかけても、全く効き目・変化がないこと」になります。
「糠(ぬか)」というのは、玄米を精白する時に搗(つ)かれて出てくる種皮や胚芽の粉末(混合物)のことで、水に溶かすとべちゃべちゃとして柔らかくなります。
「糠に釘」は省略して「糠釘(ぬかくぎ)」と呼ばれることもありますが、どんなに努力や工夫、継続をしても全く効き目や手応えがない事柄に対して使われることわざになっています。
あるいは、「糠に釘」ということわざは、どんなに熱心に説明・説得・注意などをしても「聞く耳を持たない人+話の内容を理解することができない人」のことを意味しているのです。
- 「糠に釘」の読み方
「糠に釘」の読み方
「糠に釘」の読み方は、「ぬかにくぎ」になります。
「糠に釘」と同じ意味のことわざ
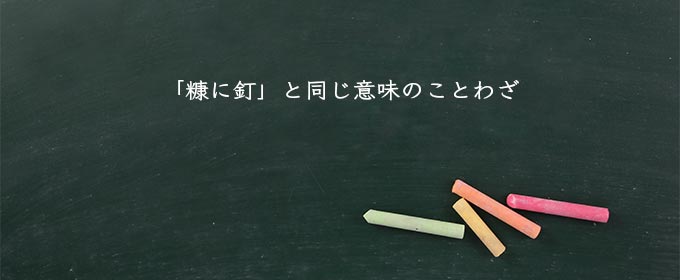
「糠に釘」とほぼ同じ意味を持つことわざには、どのようなものがあるのでしょうか?「糠に釘」と同じ意味のことわざについて紹介します。
- 「暖簾に腕押し」【のれんにうでおし】
- 「豆腐に鎹」【とうふにかすがい】
- 「沼に杭」【ぬまにくい】
「暖簾に腕押し」【のれんにうでおし】
「糠に釘」と同じ意味のことわざとして、「暖簾に腕押し(のれんにうでおし)」があります。
「暖簾に腕押し」ということわざの意味は、ひらひらとして押すことができない暖簾(のれん)をいくら腕で押してみても、何の効果(効き目)も変化の手応えもないということです。
「糠に釘」も柔らかい糠に釘を打っても効き目や手応えがないという意味を持っています。
そのため、「糠に釘」と「暖簾に腕押し」はほぼ同じ意味を持つことわざと言えるのです。
「豆腐に鎹」【とうふにかすがい】
「糠に釘」と同じ意味のことわざとして、「豆腐に鎹(とうふにかすがい)」があります。
「豆腐に鎹」ということわざの意味は、柔らかい豆腐に鎹を差し込むように、何の手応えも効き目もないということです。
「鎹(かすがい)」というのは、「子は鎹」ということわざもありますが、「二つの木材を接続する金属製のコの字型の特殊な釘」のことです。
「糠に釘」と「豆腐に鎹」は、ほとんど同じ意味を持ったことわざになっています。
「沼に杭」【ぬまにくい】
「糠に釘」と同じ意味のことわざとして、「沼に杭(ぬまにくい)」があります。
「沼に杭(ぬまにくい)」ということわざの意味は、ずぶずぶと物を飲み込んでいく沼に杭(くい)を打ち込むように、効き目や手応えが全くないことです。
「糠に釘」ということわざも、全く効き目や手応えがないことを意味しています。
そのことから、「糠に釘」と同じ意味を持つことわざとして、「沼に杭」を上げることができるのです。
「糠に釘」の言葉の使い方
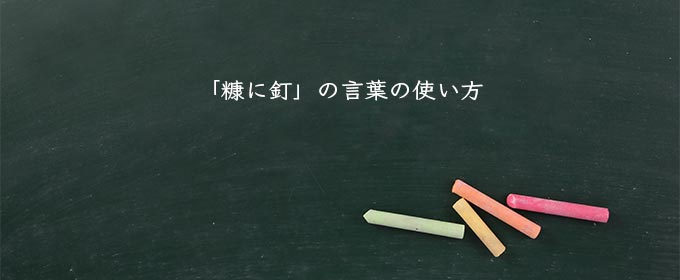
「糠に釘」の言葉の使い方は、どんなに意見や説得をしても何の反応も効き目もない人物に対して使うという使い方がまずあります。
「人の話を聞かない相手+人の話を理解できない相手」に、説明・説得をしても無駄であるという意味を持つ他のことわざとして、「馬耳東風(ばじとうふう)」や「馬の耳に念仏」があります。
「糠に釘」ということわざのもう一つの使い方として、どんなに努力・工夫をしても何の効き目もない事柄、どんなに地道に働きかけても全く手応えのない事象(物事)に対して使うということがあります。
例えば、「自分なんかが東大の二次試験の勉強をいくらしても、糠に釘である」といった使い方をすることができます。
「糠に釘」を使った例文や短文(解釈)
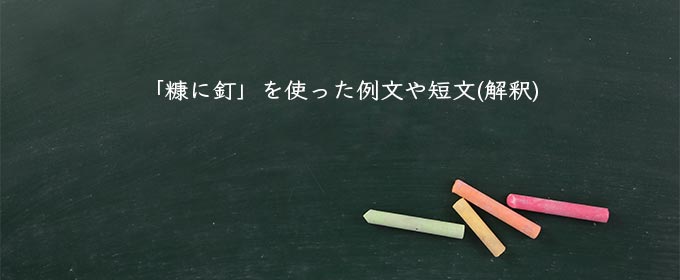
「糠に釘」を使った例文・短文を紹介して、その意味を解釈していきます。
- 「糠に釘」の例文1
- 「糠に釘」の例文2
- 「糠に釘」の例文3
「糠に釘」の例文1
どんなに厳しい口調で注意をしても、聞く気のない相手には糠に釘である。
この例文における「糠に釘」は、相手の注意をはじめから聞くつもりがない相手に対して、いくら厳しい口調や大声で注意をしても、何の効き目も変化もないということを意味しています。
「糠に釘」の例文2
幼い子供を相手に理屈・論理で説教をしても、糠に釘だろう。
この例文における「糠に釘」は、幼い子供にはそもそも難しい理屈や論理的な内容を理解するだけの知的能力がないので、いくら高度な理屈で小難しい説教をしても何の効果も意味もないことを意味しています。
「糠に釘」の例文3
うすら笑いを浮かべる糠に釘の生意気な生徒の態度を前にして、普段は温厚な先生が声を荒らげた。
この例文における「糠に釘」は、温厚な先生がいくら指導や注意をしてもまったく効き目がないこと、あるいは生意気な生徒が先生の言葉を聞くつもりがないことを意味しています。
「糠に釘」の英語
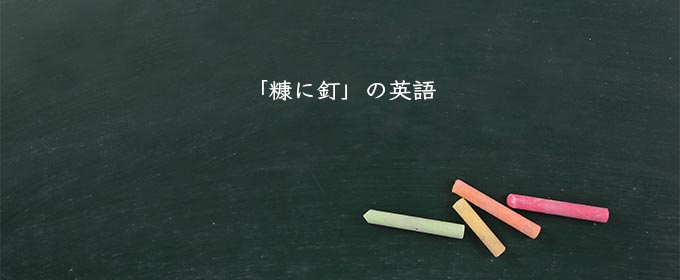
「糠に釘」のことわざの意味(効き目がない・手応えがない)に相当する英語の格言・表現には、以下のようなものがあります。
“Bolt the door with a boiled carrot.”(ゆでた人参でドアに鍵をかけようとする。)
“It is quite useless.”(まったく役に立たない=糠に釘だ。)
“It will have no effect.”(まったく効き目がないだろう=糠に釘だろう。)
“All is lost that is given to a fool.”(愚か者に与えられるものは全て失われることになる。)
「糠に釘」のことわざと「ぬか床に釘をいれる漬け方」は全く関係ない?
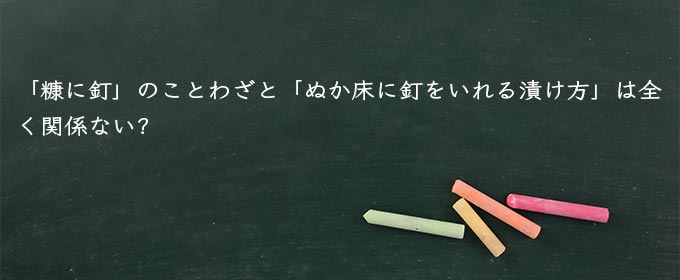
「糠に釘」のことわざと「ぬか床に釘をいれる漬け方」に関係があるかということですが、この二つには関係はありません。
「糠に釘」は柔らかいべちゃべちゃとした糠に釘を打ち込んでも、糠に埋もれていくだけで意味・効果がないということです。
「ぬか床に釘をいれる漬け方」というのは、「ぬか漬けを美味しくする方法+ぬか漬けの見栄えを良くするテクニック」として良く言われるものです。
ぬか床に古釘(錆びた釘)を数本入れておくと、鉄分の働きによってぬか床による野菜(ナス・キュウリ・大根など)の変色を防いでくれて、ぬか床にまろやかな風味が加わるとされています。
美味しくて色が綺麗なぬか漬けを作るためのテクニックですが、「糠に釘」ということわざの由来と関係しているわけではないのです。
「糠に釘」の語源や由来
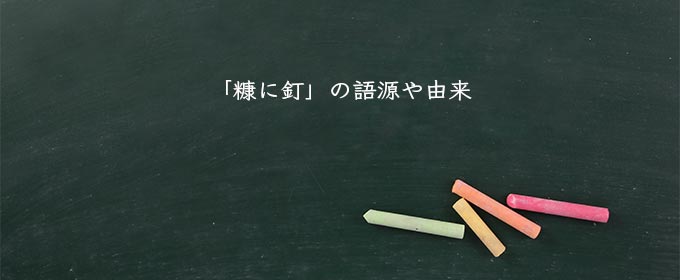
「糠に釘」の語源・由来は、木材に打ち込むことによって木材同士を接続する役割を果たす「固い釘(くぎ)」が、「柔らかい糠」に対して打ち込むことができないという事実に由来しています。
「糠(ぬか)」というのは、玄米を搗いて(ついて)精白する時に出てくる種皮・胚芽の粉末(混合物)のことで、水に溶かすとべちゃべちゃして柔らかくなる特性を持っています。
そんな柔らかい糠に、いくら固い釘を打ってもまったく効き目も手応えもないということが「糠に釘」の語源になっているのです。
その他の「釘」を使ったことわざと意味を解釈
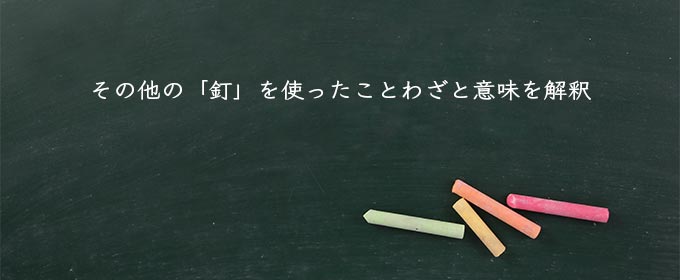
「糠に釘」以外の「釘」を使ったことわざとその意味を解釈していきます。
- 「火事あとの釘拾い」【かじあとのくぎひろい】
- 「年寄りと釘頭は引っ込むが良し」【としよりとくぎがしらはひっこむがよし】
「火事あとの釘拾い」【かじあとのくぎひろい】
「火事あとの釘拾い」ということわざの意味は、大損・浪費をした後になって、コツコツと節約・貯蓄をしても何の足しにもならないということです。
火事で家・屋敷を完全に焼失してしまった後で、何の役にも立たない焼け釘を拾うということが語源になっています。
「火事あとの釘拾い」のことわざは、「焼け跡の釘拾い」とも言います。
「年寄りと釘頭は引っ込むが良し」【としよりとくぎがしらはひっこむがよし】
「年寄りと釘頭は引っ込むが良し」ということわざの意味は、打ち込んだ釘の頭は引っ込んでいる方がいいように、年寄り(高齢者)もいたずらに出しゃばって後進(若者)の邪魔をしない方がいいということです。
年寄りは年寄りらしく前面にでて出しゃばるのではなく、後進となる現役の若い人たちを見守る方が良いという意味になっています。
「糠に釘」ということわざについて徹底的に解説しましたが、糠に釘には「柔らかい糠に釘を打つように、何の手応えもないこと」や「全く効き目・変化がないこと」などの意味があります。
糠に釘に似た意味のことわざとしては「暖簾に腕押し(のれんにうでおし)」「豆腐に鎹(とうふにかすがい)」「沼に杭(ぬまにくい)」などがあります。
「糠に釘」という言葉・ことわざについて詳しく調べたい時は、この記事を参考にしてみて下さい。