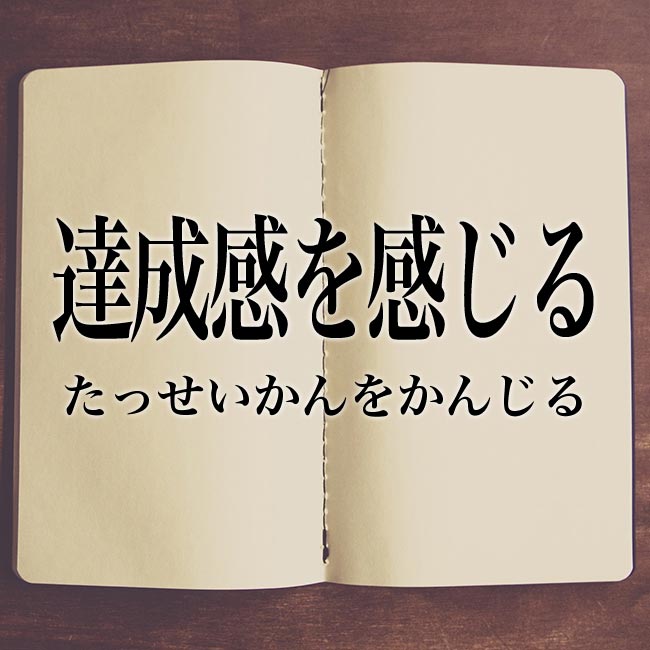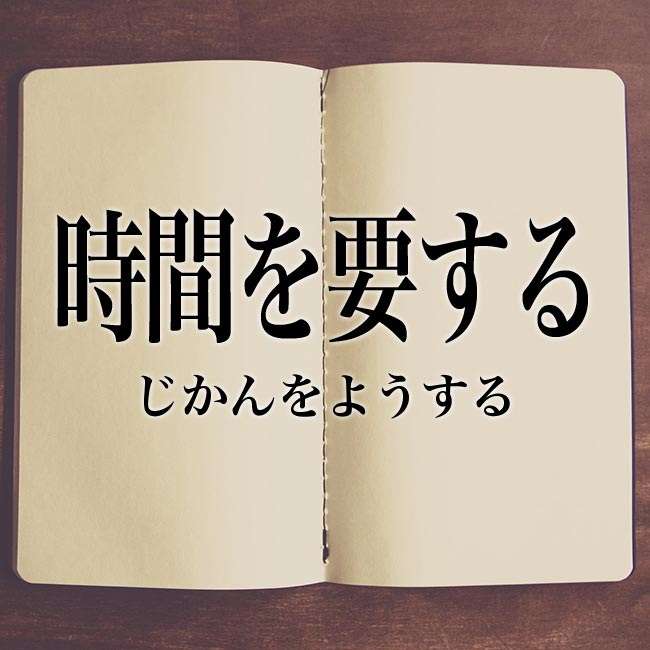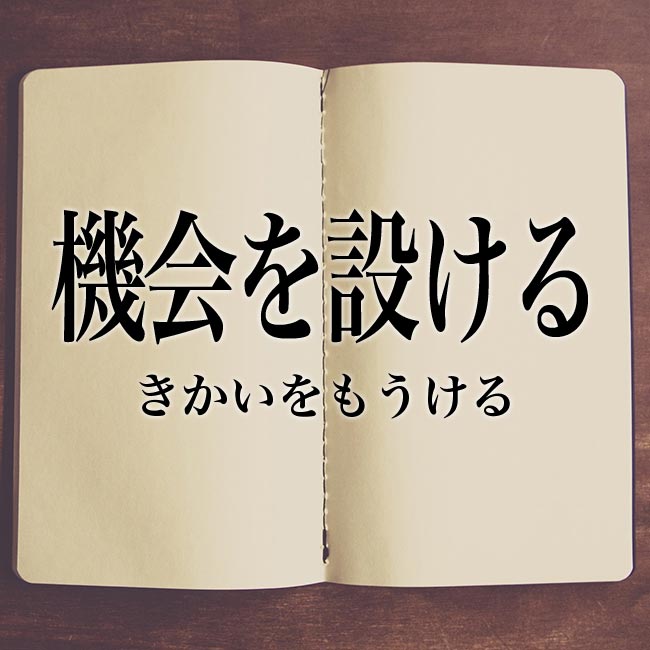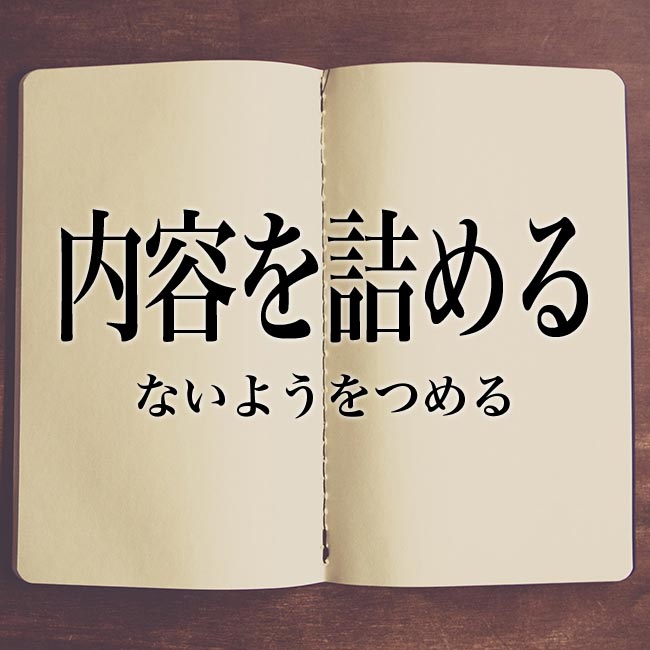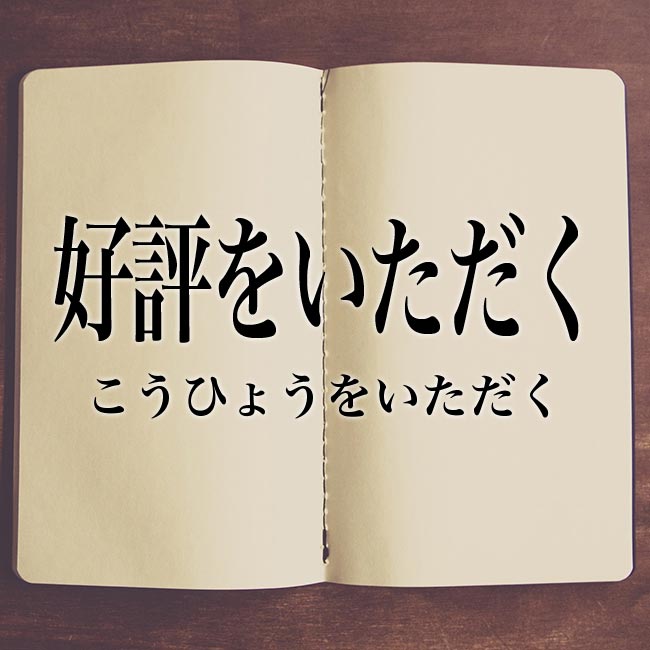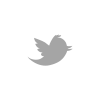「流動性の罠」の慣用句での意味とは!類語や言い換え!例文や表現の使い方
「流動性の罠」とは、「金融緩和(金利政策)の限界で名目金利をこれ以上下げられない状態」を意味する言葉です。
「流動性の罠」の「意味・使い方・例文と解釈・類語(シソーラス)や言い換え」などについて、詳しく説明していきます。
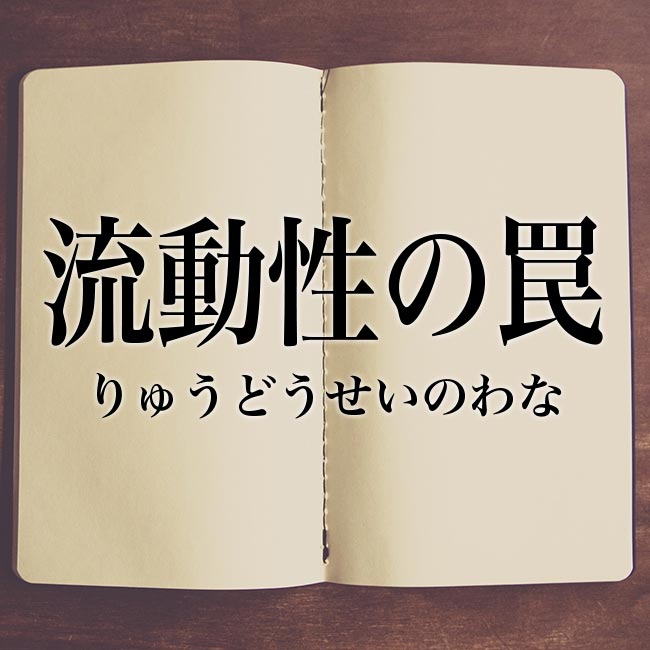
目次
- 「流動性の罠」とは?
- 「流動性の罠」の表現の使い方
- 「流動性の罠」を使った例文と意味を解釈
- 「流動性の罠」の類語や類義語・言い換え
「流動性の罠」とは?
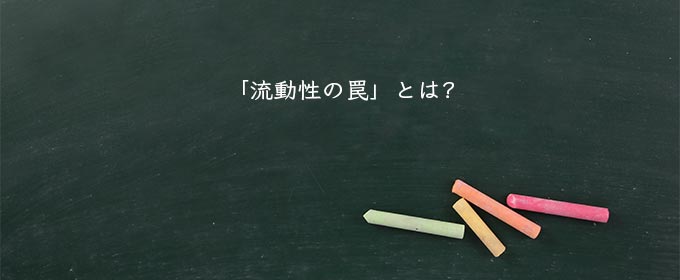
「流動性の罠」という経済用語は、「金融緩和政策(利下げによる金融緩和)の限界で、名目金利をこれ以上下げられない状態」を意味しています。
景気対策としての「金融緩和」を実施すると、一般的には利子率が低下する影響で民間投資や消費が増加することになります。
しかし、投資の利子率弾力性が低下してからも、更に利子率を下げて一定水準以下になると、資金が金融機関に滞留したまま民間に流れない「流動性の罠」が発生するリスクが高まります。
「流動性の罠」の経済用語は、ケインズ経済学を解釈した経済学者のジョン・ヒックスが考案したものです。
「流動性の罠」とは、「景気対策の金融緩和が失敗した時に起こる資金の滞留状態・金利引き下げの限界・中長期投資よりも貨幣保有を好む傾向」を意味しているのです。
「流動性の罠」の表現の使い方
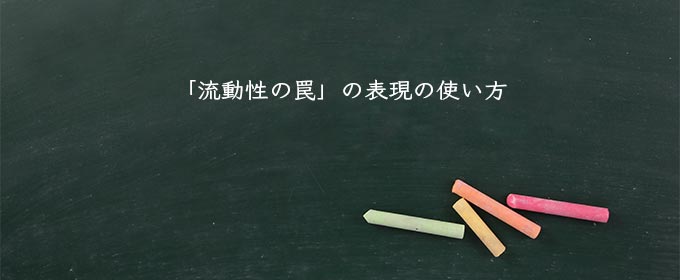
「流動性の罠」の表現の使い方は、「金利引き下げの金融緩和による伝統的な景気対策が機能しなくなった(機能しづらくなった)状態」を指して使うという使い方になります。
「流動性の罠」というのは、「金利低下で投機目的の貨幣需要が無限大になり、金融政策が概ね無効化してしまった状態」を意味して使われる経済用語なのです。
「流動性の罠」を使った例文と意味を解釈
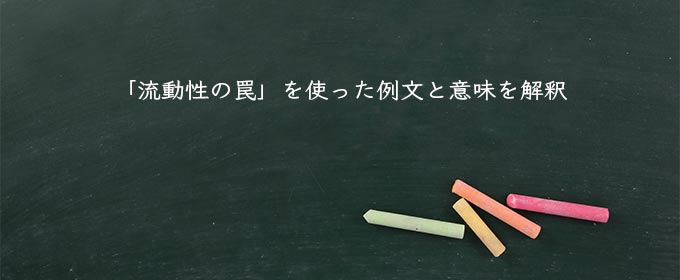
「流動性の罠」を使った例文を紹介して、その意味を解釈していきます。
- 「流動性の罠」を使った例文1
- 「流動性の罠」を使った例文2
「流動性の罠」を使った例文1
「流動性の罠にはまると、貨幣以外のゼロ金利に近い国債を持つ意義がほぼなくなります」
この例文は、「金利政策による景気対策の限界(それ以上名目金利を下げられない状態)に陥ると、貨幣以外のゼロ金利に近い国債を持つ意義がほぼなくなる」ということを意味しています。
「流動性の罠」を使った例文2
「流動性の罠という概念は、金利政策による景気底上げの限界を示しているのです」
この例文は、「貨幣需要が無限大になって国債(債権)保有の動機がなくなる流動性の罠の概念は、金利政策による景気底上げの限界を示している」ということを意味しています。
「流動性の罠」の類語や類義語・言い換え
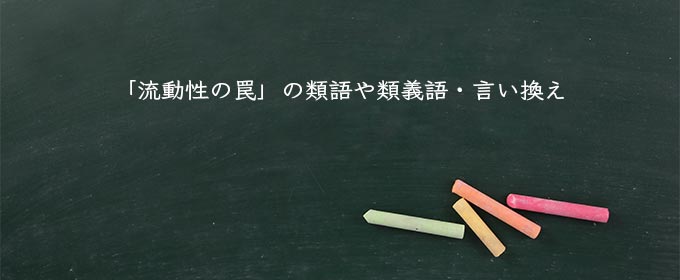
「流動性の罠」の類語・類義語・言い換えについて、分かりやすく解説していきます。
- 「名目金利引き下げの限界」
- 「貨幣需要の無限化」
「名目金利引き下げの限界」
「流動性の罠」の類語・言い換えとして、「名目金利引き下げの限界」があります。
「流動性の罠」というのは、ケインズ経済学をベースとした金融政策(金利政策)の限界を示す概念であり、「これ以上は名目金利を引き下げられない状態」を意味しています。
そのため、「流動性の罠」の表現は「名目金利引き下げの限界」という表現で言い換えることが可能なのです。
「貨幣需要の無限化」
「流動性の罠」の類義語・言い換えとして、「貨幣需要の無限化」があります。
「流動性の罠」というのは、「ゼロ金利に近づいて債券保有の動機が薄れ、投機的目的の貨幣需要が無限化する事態」を意味しています。
その意味合いから、「流動性の罠」と良く似た意味を持つ類義語(シソーラス)として、「貨幣需要の無限化」という表現を指摘することができるのです。
「流動性の罠」という言葉には、「金融緩和(金利政策)の限界で名目金利をこれ以上下げられない状態」の意味があります。
「流動性の罠」という言葉について詳しく調べたい時は、この記事を参考にしてみて下さい。