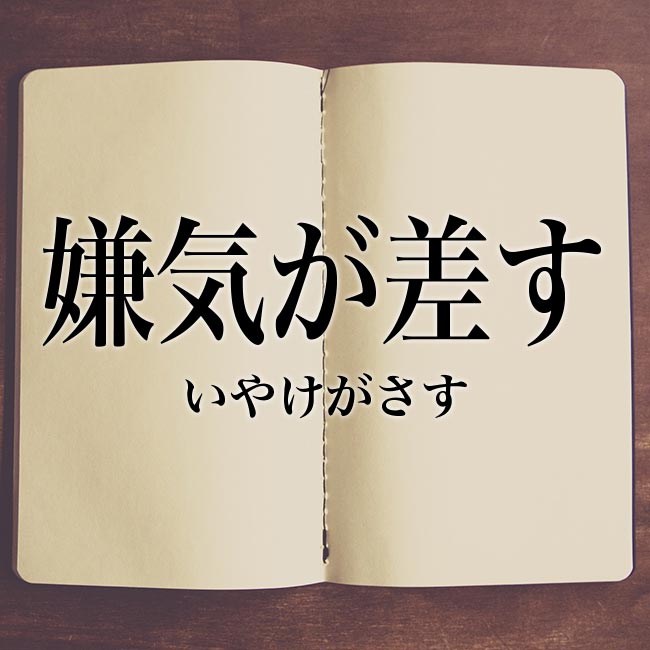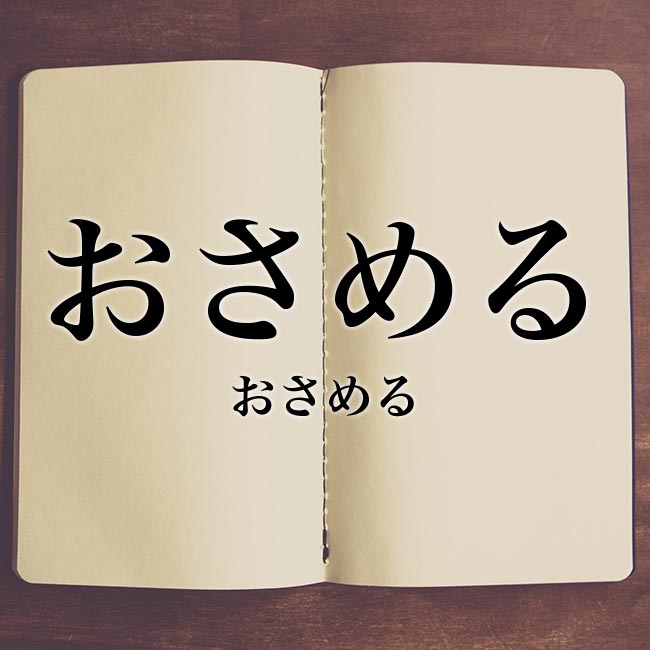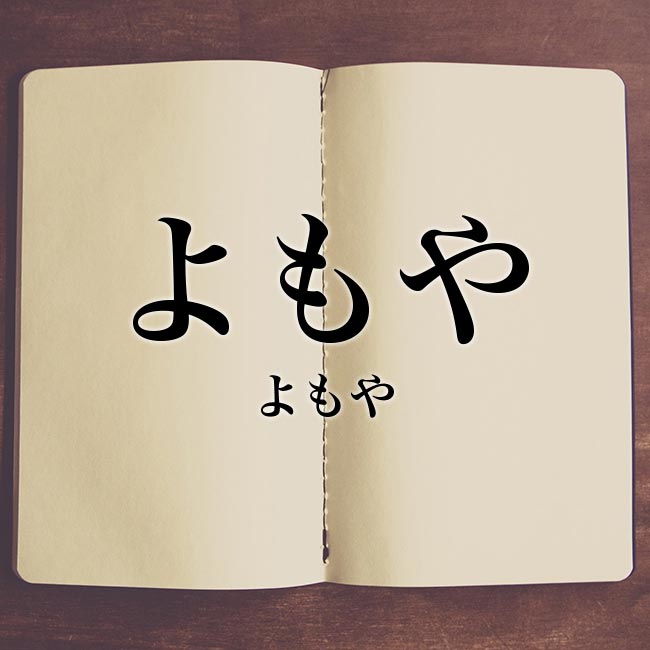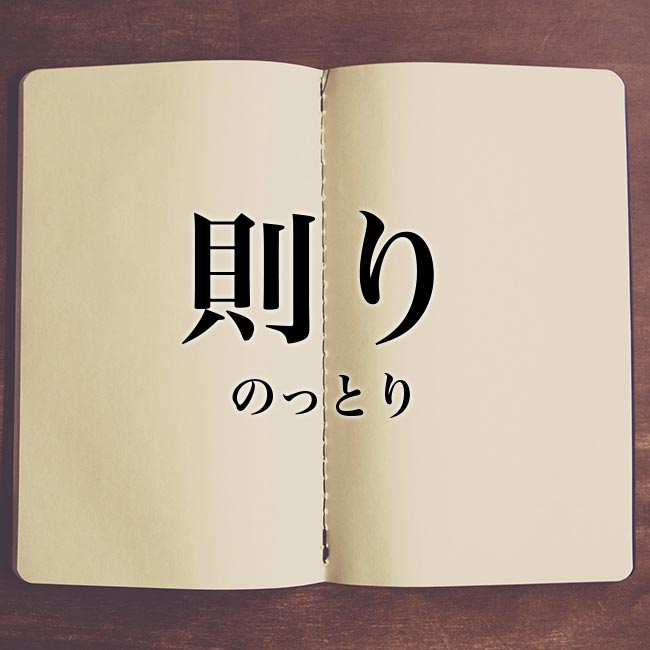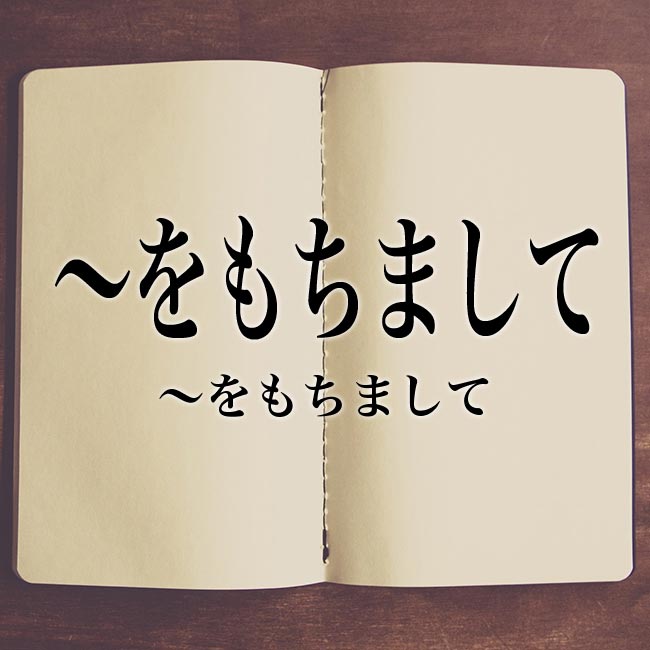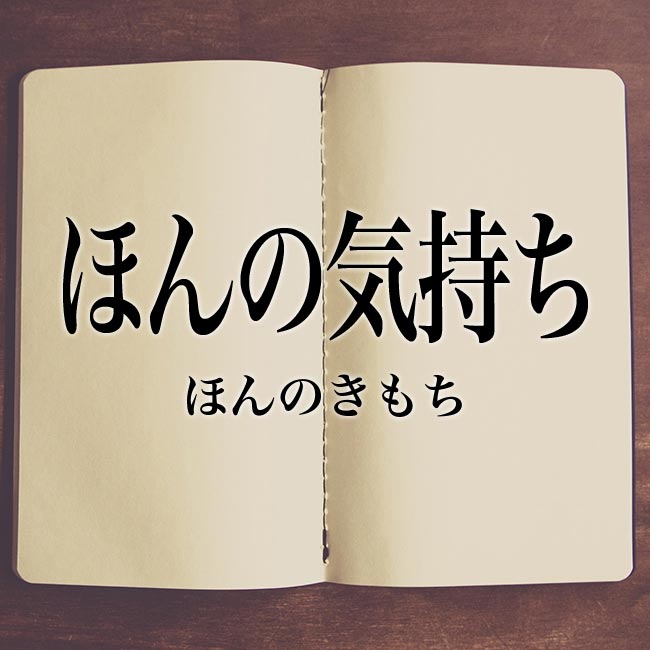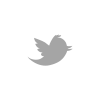「辟易」の意味とは?類語、使い方や例文を紹介!
意味は何となくわかっているけれど、いざ漢字になると読み方や書き方などが難しい言葉は沢山あります。
例えば「辟易」という言葉。
聞いた事がある方は多いかもしれませんが、正しい意味はわかるでしょうか。
今回はこの言葉について、意味や使い方などを詳しくみていきたいと思います。
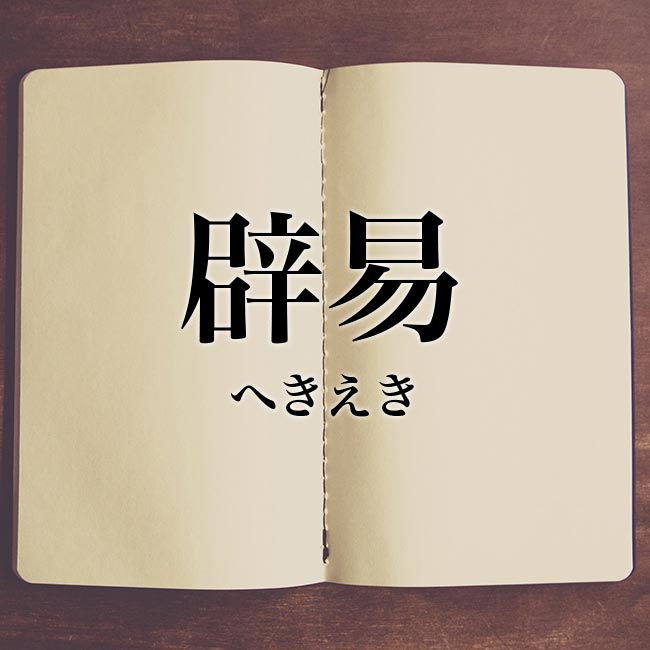
目次
- 「辟易」の意味とは?
- 「辟易」の類語や言い換え
- 「辟易」の使い方
- 「辟易」を使った例文
- 「辟易」を使った言葉
- 「辟易」の誤用
- 「辟易する」と「閉口する」の違い
「辟易」の意味とは?
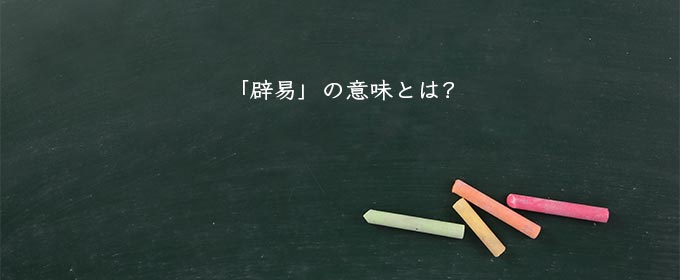
- 「辟易」の読み方や意味
- 「辟易」の語源や成り立ち
「辟易」の読み方や意味
「辟易」は【へきえき】と読みます。
意味は、
- うんざりして嫌気がさすこと
- 酷く迷惑をして閉口すること
- 相手の態度に圧倒されてたじろぐこと
などがあります。
つまり、あまりいい意味ではなく、何となく物事に対し疲れている様子がうかがえます。
「辟易」の語源や成り立ち
「辟」は音読みで【ヘキ・ヒ】、訓読みで【きみ・め-す】と読み、《重い刑罰・罪・さける》という意味があり、「易」は音読みで【エキ・イ・ヤク】訓読みで【やさしい・やすい】と読み、《かえる・へんこうする・占い・占いの書》という意味があります。
そしてこの二つを合わせ「辟易」が生まれましたが、「辟易」は中国の故事(『史記 項羽本紀』)に出てくる言葉であり、元は《道を辟(さ)けて所を易(か)える》から成り立った言葉になります。
道を避けて立ち退くという意味から→相手を嫌がり逃げ去る事→相手に尻込みする事というように転じました。
つまり、うんざりするような嫌なもの、避けたいものがあるという意味になります。
「辟易」の類語や言い換え
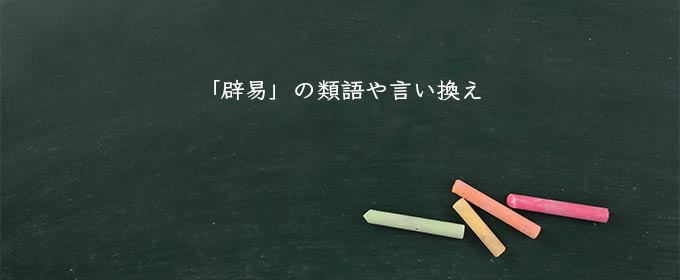
- 「嫌気が差す」【いやけがさす】
- 「食傷する」【しょくしょうする】
- 「うんざりする」【うんざりする】
「嫌気が差す」【いやけがさす】
疎ましく思ったり、面倒臭く思う事を言います。
繰り返されている物事や、続いている状況に対して鬱憤が溜まっていき、嫌な気持ちが続いている状況をいいます。
突然沸き起こった感情ではなく、継続していた感情が限界にきたといった方がニュアンス的にはふさわしい表現になります。
- 「毎日同じ小言を聞かされ、何の生産性もなくストレスは溜まる一方で、ほとほと嫌気がさす」
- 「嫌気がさして別れたけれど、あの生活は生活で楽しかったかもしれないと今は思う」
など。
「食傷する」【しょくしょうする】
同じ食べ物や食事が続いて、食べ飽きたという事、いくら好物でも毎日続いては嫌になるという事から、同じ事を何度も繰り返すと飽き飽きして嫌になる事を言います。
- 「上司の罵詈雑言に食傷気味ではあるが、今は転職が出来ないので頑張らなければいけない」
- 「また血液型占いの話題が出たので答えたが、毎回同じ事を言われるのでいい加減食傷している」
など。
「うんざりする」【うんざりする】
物事に飽き、つくづく嫌になりテンションが下がる事を言います。
「またか」と言ったなんとも言えない感情を表します。
この感情も急に沸く訳ではなく、徐々に募った感情になります。
- 「やってもやってもキリがないこの作業にうんざりする」
- 「こんな生活にうんざりしてるし、いつまで続くのかと思うと辟易とする。だけど、辞められないのも事実だ」
など。
「辟易」の使い方
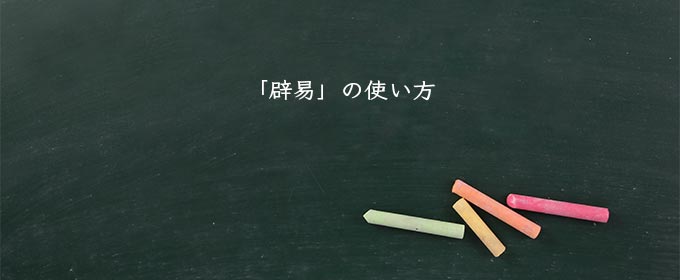
「辟易」は言葉の後ろに「させられる」「している」「?する」などと動詞をつけて使います。
「辟易」は名詞なのでそれだけでは体言止めになってしまいます。
「辟易する」「辟易して」「辟易させられる」と言った風に使い、うんざりする事があったり、嫌気がさす事が続いている時や何かにたじろいだ時に使う言葉になります。
感情としてはネガティヴになっていたり、気が進まずどんよりと疲れていたり、考えただけで疲れてしまう時の表現になります。
喜怒哀楽だけでは表現できない、腹立たしいような悲しいような複雑な人の微妙な感情だと言えるでしょう。
「辟易」を使った例文
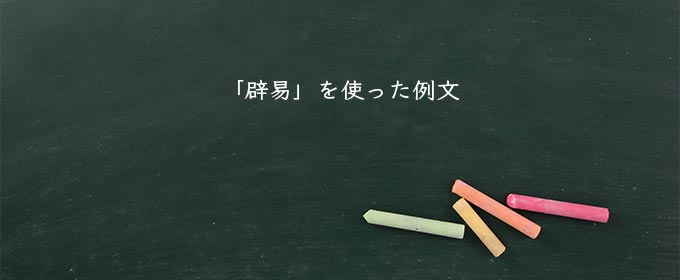
- 「辟易」の例文1
- 「辟易」の例文2
- 「辟易」の例文3
- 「辟易」の例文4
- 「辟易」の例文5
「辟易」の例文1
「家事を全く手伝わず、注文ばかりしてくる旦那に対し、辟易している妻も多いはずです」
「辟易」の例文2
「周囲を辟易させる発言でもあるので、部下の奔放な発言に気を付けておかなければいけない」
「辟易」の例文3
「恋人から職場の同僚の異性の仕事のできや、年収を聞いてもいないのに聞かされる事に、本当に辟易する」
「辟易」の例文4
「化粧品会社に一度問い合わせたら、その後契約を勧めるしつこい勧誘に辟易させられている」
「辟易」の例文5
「毎日同じ作業を繰り返し、どう考えてもおかしいのにも関わらず、誰一人としてそれについて意見を出さないので辟易している」
「辟易」を使った言葉
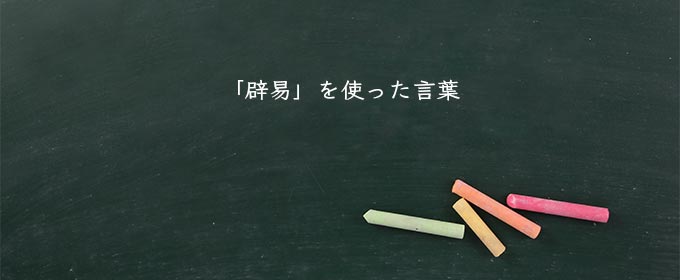
- 「辟易する」【へきえきする】
- 「暑さに辟易」【あつさにへきえき】
「辟易する」【へきえきする】
「辟易」は先述しましたが、この言葉の後に「〜する」という動詞をつけて使う事が一般的な使い方になります。
- 自慢話ばかり聞かされて辟易する。
- 体が弱いので、幼い頃から病気がちだ。
いい加減辟易する。
などと使います。
「暑さに辟易」【あつさにへきえき】
気候などのどうしようもないものに対しても「辟易」を使用することがあります。
「辟易」には勢いに押されてたじろぐこと、対応や対処のしようが無くうんざりすること、手がつけられず嫌になることなどという意味があるので、「暑さに辟易」とはそのまま暑さに対しどうしようもできず、手のつけようがなくうんざりしている事を表しています。
あまりにも気温が高くて手の打ちようがない時に使われます。
「辟易」の誤用
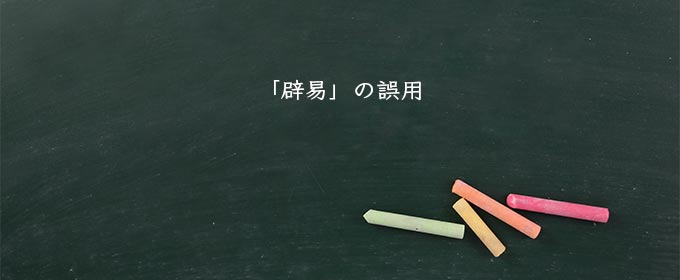
- 「辟易とする」
「辟易とする」
「辟易と」や「辟易な」などと「辟易」の後に「と」や「な」をつけて使用をしているのを見かける事がありますが、これは間違いということになります。
「と」や「な」を入れる事でニュアンスに柔らかさを出したいという気持ちが出ているのかもしれません。
もしくは一旦クッションを置く事でうんざり感や嫌気感から距離を置きたいという心理が働くのかもしれません。
「辟易する」と「閉口する」の違い
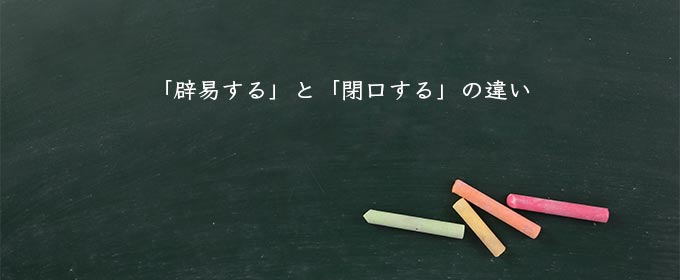
- 「閉口する」とは
- 「閉口する」の意味
「閉口する」とは
「辟易」と同じような意味を持つ言葉に「閉口」というものがあります。
この言葉も名詞なので、後に「〜する」という動詞をつけて使用する事が多く、「辟易」と同じような状況や感情の時に使います。
ですから場合によってはそれぞれの言葉を置き換える事が出来ますが、「辟易」ではないと意味がおかしくなる事もあるので使い方に気をつけなければいけません。
そもそも「辟易」の中に「閉口」という意味合いが含まれているのでニュアンスが似ていても当然だと言えるでしょう。
「閉口する」の意味
まず「閉口」には以下のような意味があります。
- 口を閉じてものを言わないこと、発言できない事
- 圧倒されたり状況が受け入れられず、口から感情が出ない事、もしくは言い負かされてしまう事
- 困り果ててしまう事
などがあります。
内容的に一番最後の意味以外は「辟易」という意味とは重なりません。
「閉口」とは漢字通り、あまりの出来事に口が閉まってしまうような状態を指すので、嫌気がさしたりうんざりするというニュアンスとは少し違います。
また「辟易」とするのは何かが継続的に起こっていたり、自分で生み出した現象に対しても使いますが、「閉口」は自分で生み出した現象にはあまり使いません。
「毎回忘れ物を繰り返す自分に閉口する」になると自分に自分で言い負かされたり困り果ててしまう事になってしまうので、このような場合は「辟易」がふさわしいといえるでしょう。
生きていると日常の中で「辟易する」ことなど沢山あると思います。
やりきれない事や、自分ではどうしようもない事、自分が撒いた種からもうんざりするような事が起こる事もあります。
似たような言葉も沢山ありますが、「辟易」という言葉をきちんと理解して使ってみて下さい。