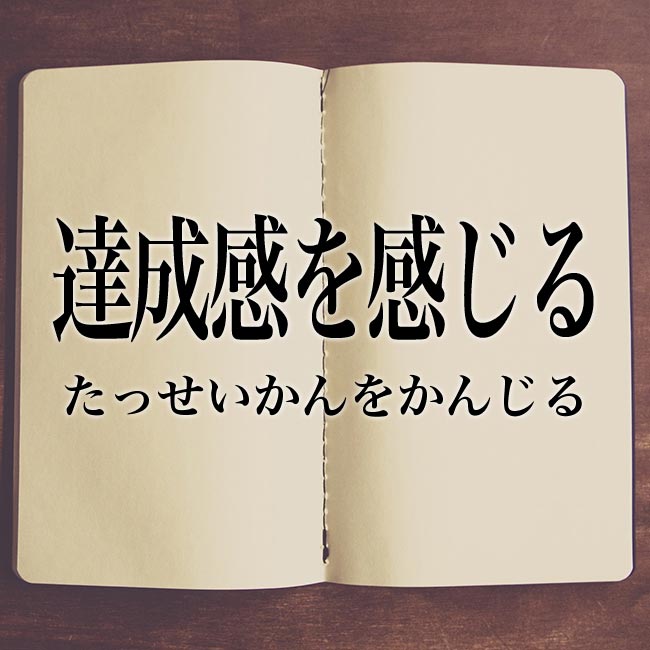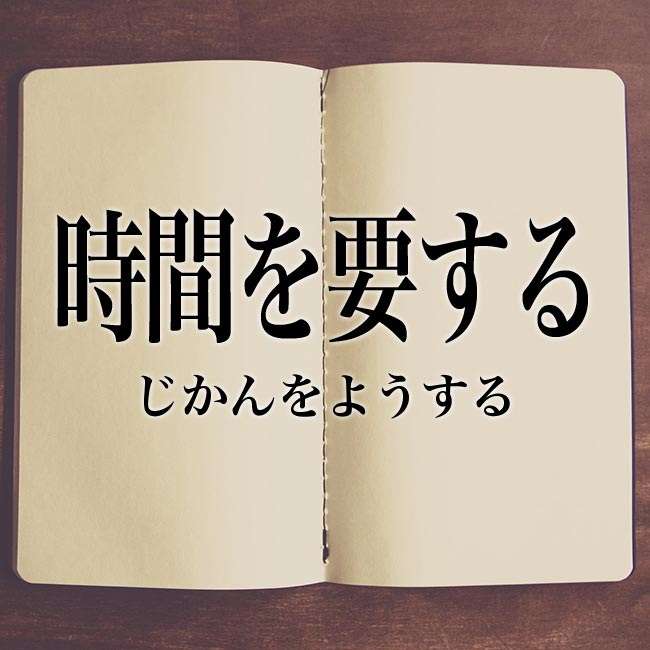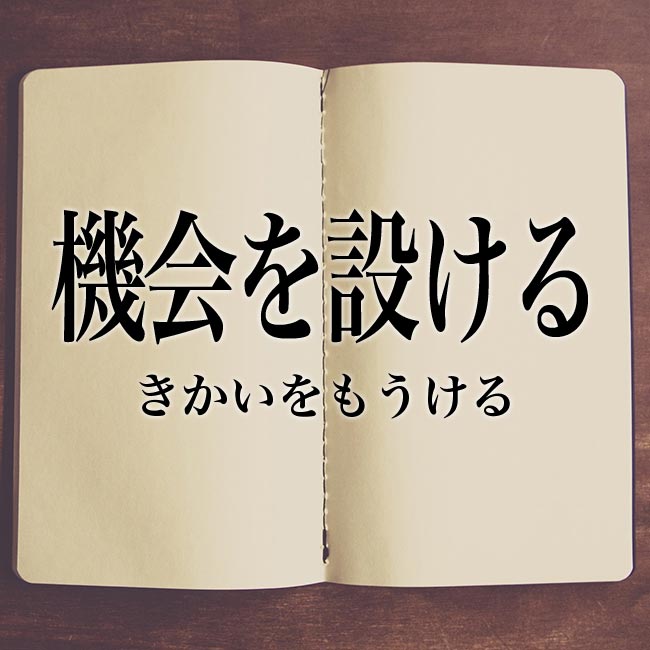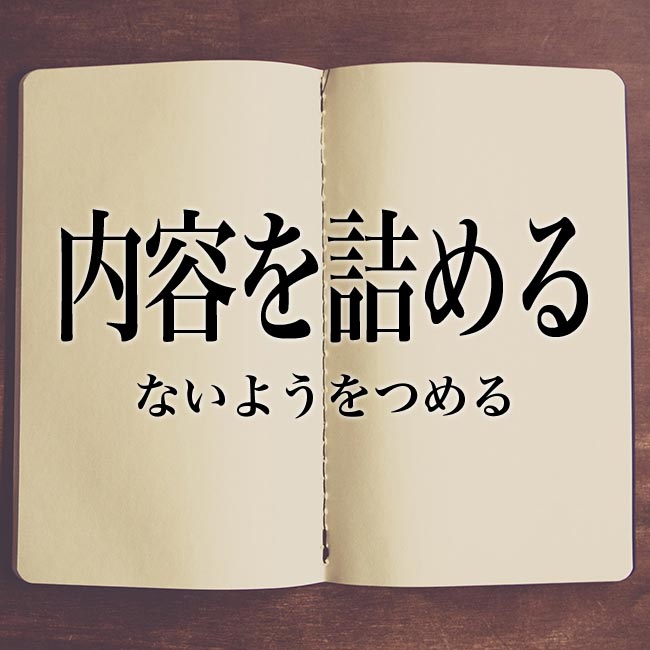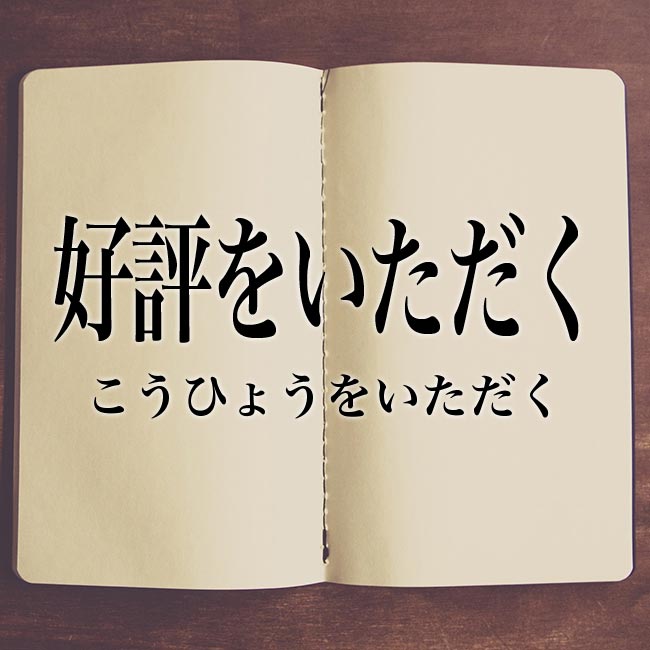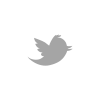「秋茄子は嫁に食わすな」の意味とは?使い方や例文を紹介!
食欲の秋で思い出すのが「秋なすは嫁にくわすな」のことわざです。
ずいぶんと激しいことわざで、お嫁さんが、かなり悪者扱いされているようなイメージです。
それも、食べさせたくないのが、トロやフォアグラなどの高級食材でなく、なすなのでしょうか。
そこには、なにかわけがありそうです。
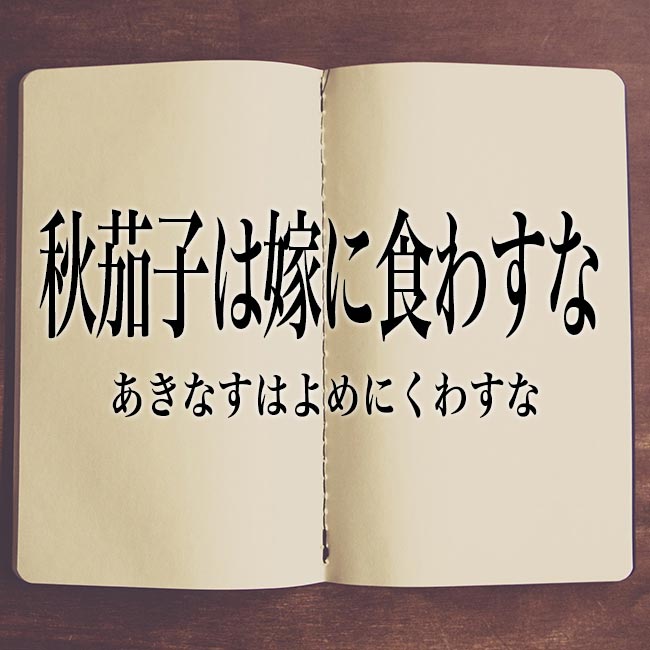
目次
- 「秋茄子は嫁にくわすな」の意味とは?
- 「秋茄子は嫁にくわすな」と類語や言い換え
- 「秋茄子は嫁にくわすな」の言葉の使い方
- 「秋茄子は嫁にくわすな」の例文
- 「秋茄子は嫁にくわすな」の対義語や反対語
- 「秋茄子は嫁にくわすな」を分解して解釈
「秋茄子は嫁にくわすな」の意味とは?
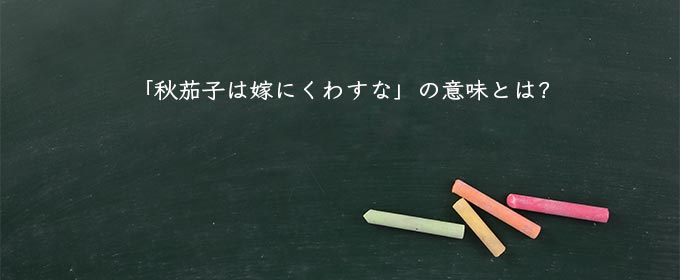
あの憎たらしい嫁には、この特別に美味しい、秋なすを食べさせるのは、もったいないとう意味です。
ただし、秋なすは、特に、水分が多く体を冷やしがちなので、大事なお嫁さんが体調を壊さないように、という思いから、食べさせないという意味の取り方もあります。
さらには、秋なすは、種が少ないという特徴をもっているので、種を子種とかけて、種が少ない→子種が少ない→子どもが産まれにくい、という言葉の解釈繋がりで、食べさせないとする意味もあります。
「秋茄子は嫁にくわすな」と類語や言い換え
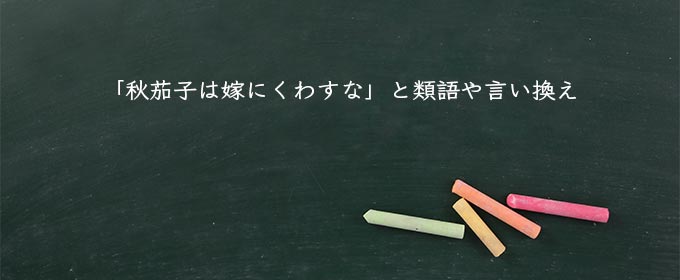
- 「秋鯖は嫁に食わすな」【あきさばはよめにくわすな】
- 「秋梭子魚は嫁に食わすな」【あきかますはよめにくわすな】
- 「五月蕨は嫁に食わすな」【ごがつわらびはよめにくわすな】
- 「秋の柴は嫁に焚かせろ」【あきのしばはよめにたかせろ】
「秋鯖は嫁に食わすな」【あきさばはよめにくわすな】
秋の鯖は、脂ものって旬を迎えます。
その美味しさは、憎らしい嫁に食べさせるには、もったいないということを指しています。
(秋なす)と(秋鯖)を入れ替えたところで、何の変わりもないことわざですが、「鯖」を使ったのでは、体調を気遣う意味は、この句からは生まれてこないことになります。
短歌や俳句と、文章が短くなればなるほど、動かない言葉、動かせない言葉が、厳選されてきますので、類語ではありますが、大きな違いがあります。
「秋梭子魚は嫁に食わすな」【あきかますはよめにくわすな】
秋が旬の梭子魚にも、嫁には食べさせるなということわざがあります。
こうなると、お嫁さんは、秋が旬となる美味しい食べ物は、何一つ、口にすることができなくなってしまいそうです。
ただ、「嫁」は、「夜目」の意味を含んだ、隠語になっているという説もあります。
「嫁」は「ヨメ」で「夜目」の「ヨメ」となり、「夜に目」がきくネズミへとつながっていきます。
こうした「嫁に食わすな」のことわざシリーズの代表である「秋なす」もその解釈に従うと、「秋なすはヨメに食わすな」つまり「秋なすはネズミに食わすな」となって、大事な美味しい茄子を、ネズミに食べられないようにしなさいという、一種の警告の意味をもったことわざになります。
「五月蕨は嫁に食わすな」【ごがつわらびはよめにくわすな】
5月に旬を迎える蕨も、お嫁さんには食べさせるなと言う、これも同じ系列のことわざになりますが、「それほど美味しい」という解釈を加えて、意味を考えていくと、イメージは、変わります。
つまり、5月に芽吹いた蕨は、わが家の可愛い、大事なお嫁さんにすら食べさせたくない、分けてあげたくないほど美味しい。
となって、味の形容が、ことわざの表したいことの主たるものになります。
「秋の柴は嫁に焚かせろ」【あきのしばはよめにたかせろ】
秋に、庭で集めた柴を、たき火にして燃やすのは、嫁にさせなさい。
という意味の言葉です。
表面的にはそれでさらりといくのですが、実は、秋の柴は、燃やすと大量の煙がでて、それが、風で、あちこちにたなびくものですから、目は痛くなるし、のどに来るしで、大変な作業なのです。
それを熟知している姑は、わが娘には、部屋の中の仕事をさせ、大変な外回りの作業を、お嫁さんにさせるという、嫁いびりの一端が、垣間見える句でもあります。
「秋茄子は嫁にくわすな」の言葉の使い方
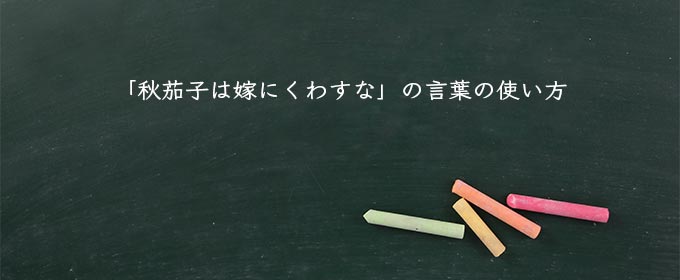
三パターンでの使い方があります。
ことわざ自体は、変わりませんが、前後の文で意味するところを変えていきます。
「きれいな秋なすをいただいたけれど、いつも一言多い、お嫁さんには「秋なすは嫁に食わすな」の言葉通り、彼女が不在の時をねらって、食卓にのせます」
「秋なすは美味しいけれども、体温を下げる作用があるので、お嫁さんの体調を気遣って、「秋なすは嫁に食わすな」の意味するところを付け加えて、食卓にのせます」
「子どものことを話題にするのは、デリケートなことだけに慎重に、慎重を期して話題にしながら、食卓にのせます」
「秋茄子は嫁にくわすな」の例文
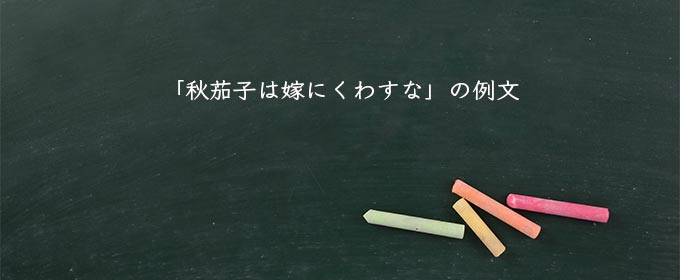
- 「秋茄子は嫁にくわすな」の例文1
- 「秋茄子は嫁にくわすな」の例文2
- 「秋茄子は嫁にくわすな」の例文3
「秋茄子は嫁にくわすな」の例文1
採れたての秋なすをいただいたけど、「秋なすは嫁に食わすな」の言葉通り、A子さんのいないお昼のうちに、焼きなすにして、食べてしまいました。
「秋茄子は嫁にくわすな」の例文2
「これ、お隣からいただいだ秋なすを焼いたんだけど、体を冷やすって言うから、悪いけどB子さん、少なめにしといたわよ」
「すみません。気を遣ってもらって」
「秋茄子は嫁にくわすな」の例文3
お隣から、見事な秋なすをもらったけれど、妊活をしているC子さんへの当てつけになるといけないので、主人に頼んで、会社の誰かに食べてもらうことにした。
「秋茄子は嫁にくわすな」の対義語や反対語
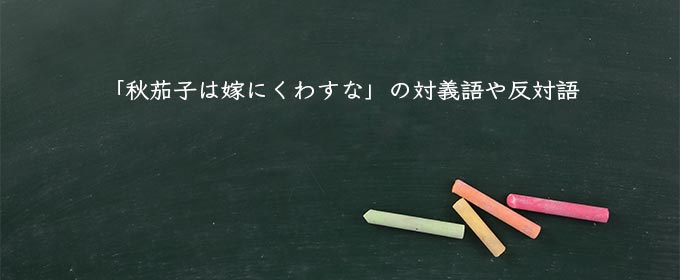
旬の食材を求めて、逆に、食べさせようとする、対義語や反対語にあたることわざには、なかなか出会いません。
それよりも、驚いたのは、まったくの逆フレーズのことわざがあることです。
いずれにせよ、お嫁さんに食べさせることわざには、皆目、出会いませんでした。
- 「秋茄子は嫁に食わせろ」【あきなすはよめにくわせろ】
- 「鯒の頭は嫁に食わせろ」【こちのあたまはよめにくわせろ】
「秋茄子は嫁に食わせろ」【あきなすはよめにくわせろ】
一瞬、目を疑いました。
全く同じつづりでありながら逆の意味を引き出しているからです。
秋なすのように、美味しいものは、独り占めにしないで、みんなで、可愛いお嫁さんも一緒になって、食べましょうという意味の言葉です。
「鯒の頭は嫁に食わせろ」【こちのあたまはよめにくわせろ】
旬のコチは、美味しい魚です。
しかし、お嫁さんが、食べるのはコチの頭のようです。
鯛の兜煮など、魚の頭は美味しいものです。
ところが、コチという魚は、頭の部分が、何かで押さえつけられたように平べったくて、しかも、ほとんどが骨で、食べる部分と言えば、ごく僅かです。
胴やしっぽの部分は、それなりに身が付いていますが、頭の部分はごく僅かです。
結局、これも嫁いじめかと思えそうですが、お嫁さんが、胴やしっぽの部分と食べ比べたら、歓声をあげるくらいに、頭部から僅かにしか取れない身は、抜群の美味しさです。
だから、お嫁さんに食べさせるのです。
「秋茄子は嫁にくわすな」を分解して解釈
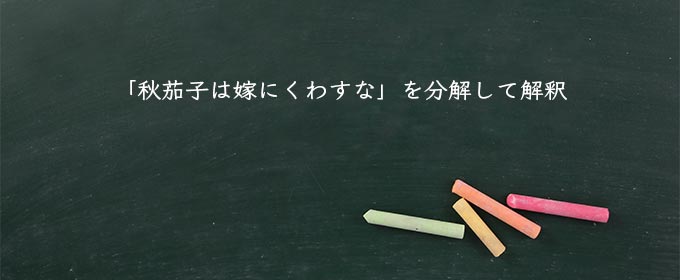
- 「秋茄子」
- 「嫁にくわすな」
「秋茄子」
秋なすという名前を見ると、朝夕が涼しくなり、木々が色づく9月から10月くらいに実るなすを想像しますが、これが、大違いなのです。
ここで言う秋とは、旧暦での秋にあたりますので、現在の暦で言えば、8月末から9月あたりになります。
「秋なす」と言うより「晩夏なす」と言う方が正しいでしょうが、食欲をそそられるのは、やはり食欲の秋の「秋なす」でしょう。
では、「嫁に食わすな」と、言われるくらいに、美味しいのはなぜでしょうか。
それは、真夏の暑い盛りには、葉や茎をぐんぐん伸ばし、成長することに、ほとんど養分を使います。
そして、少し気温が下がり始めると、今度は、実に養分を蓄え始めるのです。
この時期になると、昼夜の温度差が大きくなるので、実も引き締まってきます。
その上、皮が薄く、酸味の基となるカリウムを多く含み、種も少ないので、このなすを使った料理の幅も広がり、「あの嫁には食わせたくない」と思うほど、独り占めしたくなる美味しさに、なるのです。
このように美味しいなすですが、なすびとも言います。
どちらでも同じものですが、はるか昔の奈良時代には、すでに存在していて「奈良比(なすび)」と書いていたようです。
それを、宮中では、女房言葉で、略して「なす」と言っていたようです。
ただし、名前の由来には、諸説あります。
夏に実をつけるので、(ナツミ)→(ナスビ)、中が、すっぱい実なので(ナスビ)、中国名「茄子」チェズが、なまって(ナズ)、実が次々に成り進むので
(ナリススミ)→(ナスミ)語呂合わせでの、後付け説もあるようですが、なすは、逆に、「成す」「為す」に通じる縁起の良い語として、初夢の仲間にも加わっています。
「嫁にくわすな」
文字通り、あのお嫁さんには、食べさせるなと言う、ある面、意地悪で、しかも、結構、強い言葉です。
どうして、食べさせないのでしょうか。
この食べさせないには、いくつかのとらえ方があります。
一つには、あの可愛いお嫁さんにさえも、分けてあげたくないほど美味しくて、どうしても、独り占めしたいので、お嫁さんを初め、誰にも食べさせたくない。
という、わがままからの言い分です。
二つには、あの憎くき嫁なんかに、食べさせてたまるかという、お嫁さんをターゲットにしたメッセージです。
お嫁さんをどう受け入れているかで、当然のことですが、口調やトーンも、変わってきます。
これが、エスカレートして、なすだけに留まらず、ケーキやお饅頭などのデザート類や、くだものなどにまで、「嫁のいない、今のうち、今のうち」と、みんなが、平気で食べるようになっては、二世帯、三世帯での生活は、もう無理のようです。
家庭崩壊が、目前です。
加えて、普通でも90%が、水分からできているなすですが、秋なすには、その上に、利尿作用に効果のある、カリウムを多く含んでいます。
そのために、体温が下がりがちで、お腹に赤ちゃんでもいるお嫁さんなら、体を冷やしたら一大事です。
それで、体を大切にしなさいの願いを込めた、前述の内容とは、真反対の嫁を思う気持ちからの食べさせないというメッセージです。
「嫁姑仲良くはもっけの不思議」と、あるように、全くの他人同士、それも、愛する息子が、突然連れてきた、どこの馬の骨だか分からない若い女と、パートにすら行っていないなら、一日中、顔をつき合わせているわけですから、何もない方が不思議なくらいです。
お風呂、トイレ、洗濯、干し方、配膳、食器の使い方、洗い方、電気のon・off、チャンネル権、スマホの使い方、あげていけば、切りがないくらい、気になる、気にくわないことは、山とでてきます。
しかし、相手は、若くて、肌もつやつやしている上に、服装も大胆で、いくら若作りしても、とても、勝ち目はありません。
作る料理も今風で、「豚肉のピカタ」など初めて聞く名前に、驚いていると、「A子さん、こりゃうまいね」と、旦那は目尻を下げっぱなしで、息子同様に、お嫁さんにデレデレ、これでは怒り心頭になるのも分かるような気がします。
嫁と姑、仲良くいくには、お互いの我慢比べかもしれません。