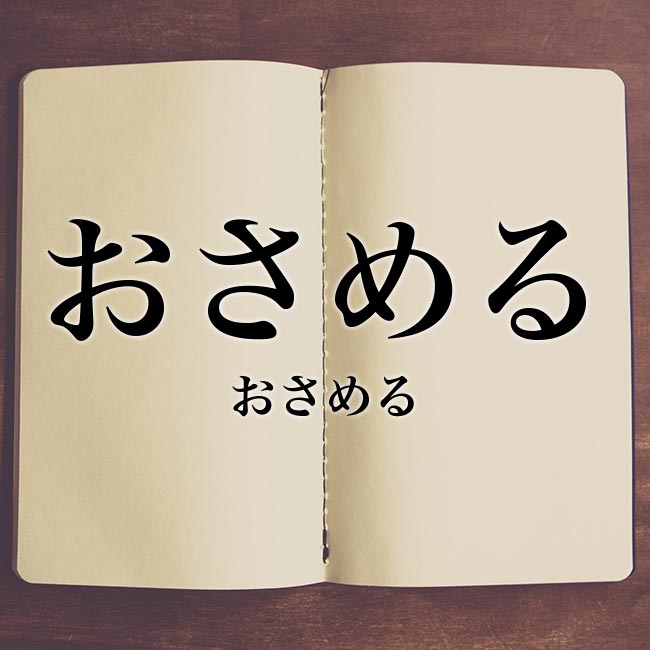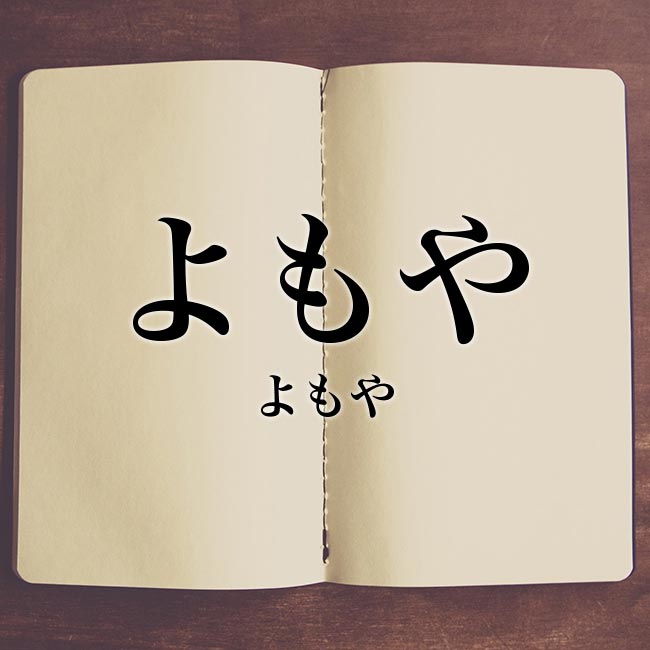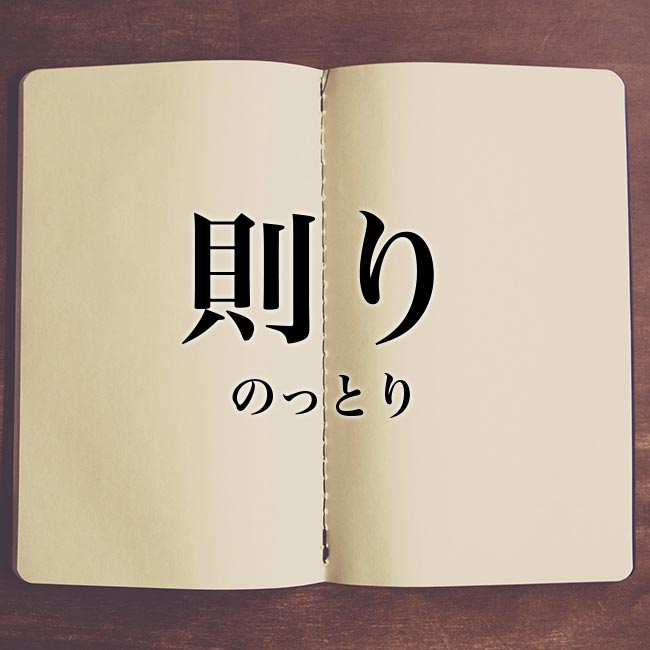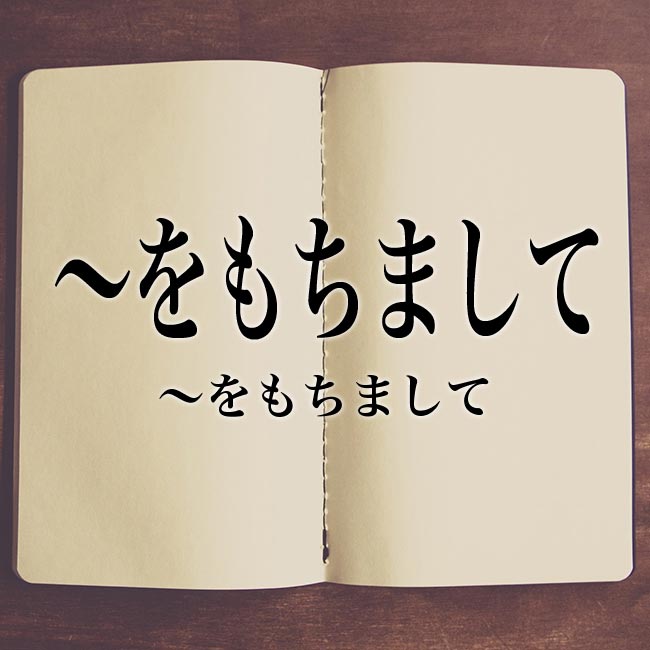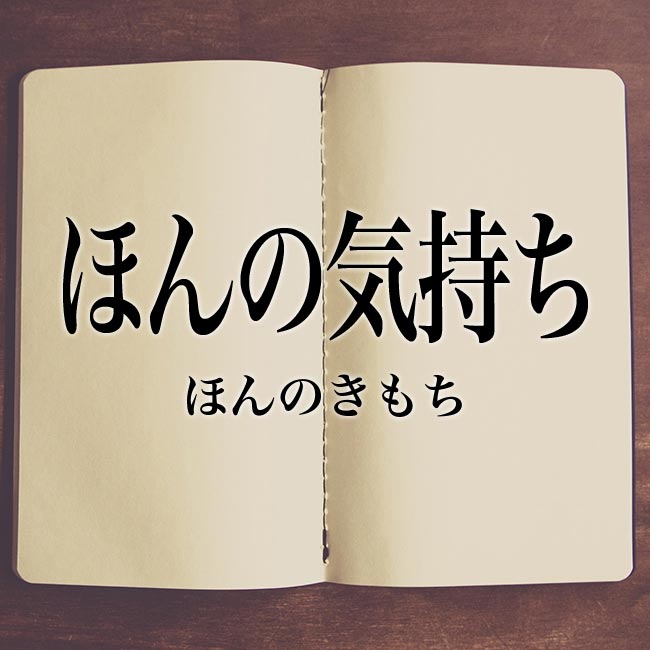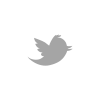「雑味がない」の意味とは!類語や例文など詳しく解釈
「雑味がない」という言葉はどのような意味があり、使い方をするのかご存知でしょうか。
ここでは言葉の意味、使い方、例文などを詳しく解説しています。
では一緒に「雑味がない」という言葉の理解を深めていきましょう。
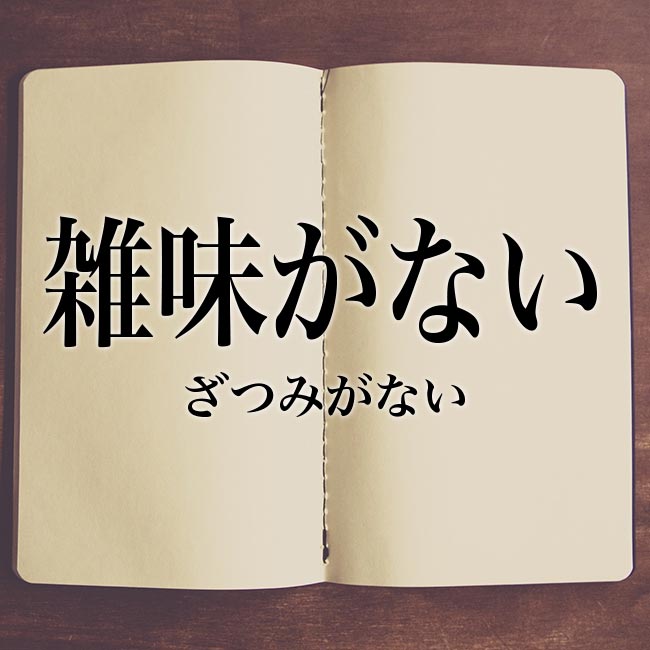
目次
- 「雑味がない」の意味
- 「雑味がない」の表現の使い方
- 「雑味がない」を使った例文と意味を解釈
- 「雑味がない」の類語や類義語
「雑味がない」の意味
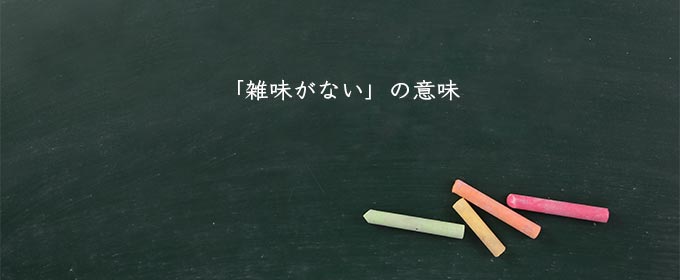
「雑味がない」とは、飲み物や食べ物に、不純物が混じっていなくて本来の味が活きていることを言います。
- 「雑味がない」の読み方
「雑味がない」の読み方
「雑味がない」の読み方は、「ざつみがない」になります。
「雑味がない」の表現の使い方
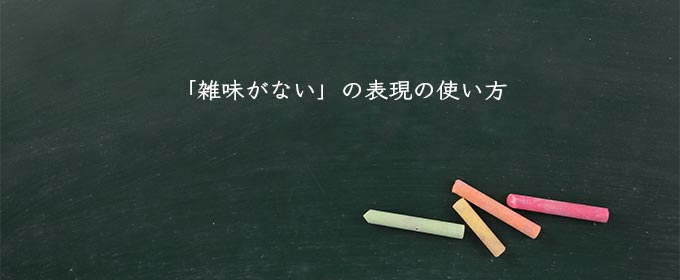
「雑味がない」を使った表現を紹介します。
「雑味がない」の「雑味」とは、本来の味を損なうものという意味です。
ですから「雑味がない」とは本来の味そのもの、本来の味が活きているという意味になりますので「美味しい」ということになります。
余計な味が混ざっておらず美味しいとは、ようするに褒め言葉としても使えます。
「雑味がない日本酒で、大人気です」「雑味がないビールが飲みたい」などと使います。
「雑味がない」とはそれほど難しい言葉ではなく「素材の味が活きていて、美味しい」「余分な味が混ざらず、すっきりしている」という意味で覚えておくといいでしょう。
「雑味がない」を使った例文と意味を解釈
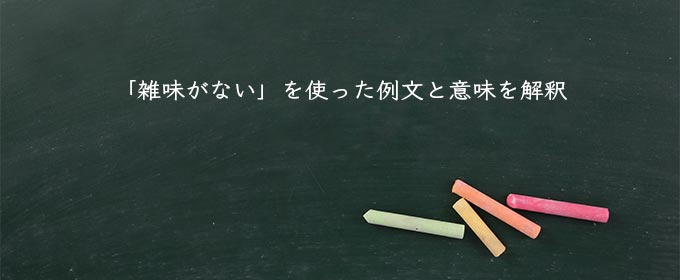
「雑味がない」を使った例文とその意味を解釈していきます。
- 「雑味がない」を使った例文1
- 「雑味がない」を使った例文2
「雑味がない」を使った例文1
「これは本当に、雑味がないコーヒーなので、ブラックで飲むことをおすすめする」
「雑味がない」とは、本来の味を損なうようなものが混ざっていないという意味になります。
例文の場合は「雑味のない」コーヒーとありますので、とても良い豆で味が良いので、砂糖やミルクを入れないでそのままの味を楽しんで下さいと言っているのです。
「雑味がない」を使った例文2
「あまりにも、雑味がないとちょっとあっさり過ぎて物足りなくないか」
「雑味」とは本来の味を損なうものを言います。
しかしそれが「くせ」となり味わいたいという場合もあります。
「雑味がない」がすっきりした本来の味であるのですが、何かを足して「雑味」をつけた方がいいと例文は言っているのです。
「雑味がない」の類語や類義語
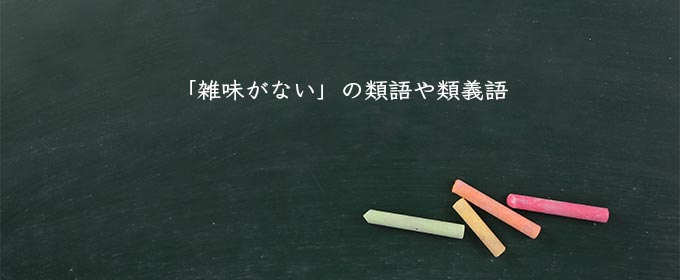
「雑味がない」の類語や類義語を紹介します。
- 「本来の味が活きている」【ほんらいのあじがいきている】
- 「風味が良い」【ふうみがよい】
「本来の味が活きている」【ほんらいのあじがいきている】
「本来の味が活きている」とは、飲み物、食べ物の、そのものの良い味が出ていることを言います。
「塩だけで十分だ、本来の味が活きているのだから、あれこれ調味料はいらない」などと使います。
「風味が良い」【ふうみがよい】
「風味が良い」とは食べ物などの味が良いことを言う言葉です。
逆に言うならば「風味が落ちる」となります。
「これは本当に風味が良くて、沢山食べたくなる」「風味が良いうちに、召し上がってください」などと使います。
いかがでしたでしょうか。
「雑味がない」という言葉の意味、使い方、例文などまとめてお伝えしました。
それでは言葉の意味を正しく理解して使いこなしてください。