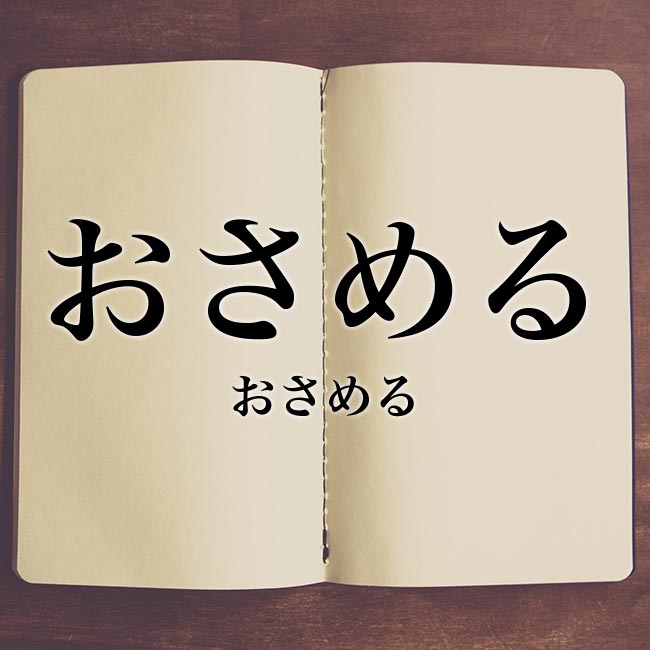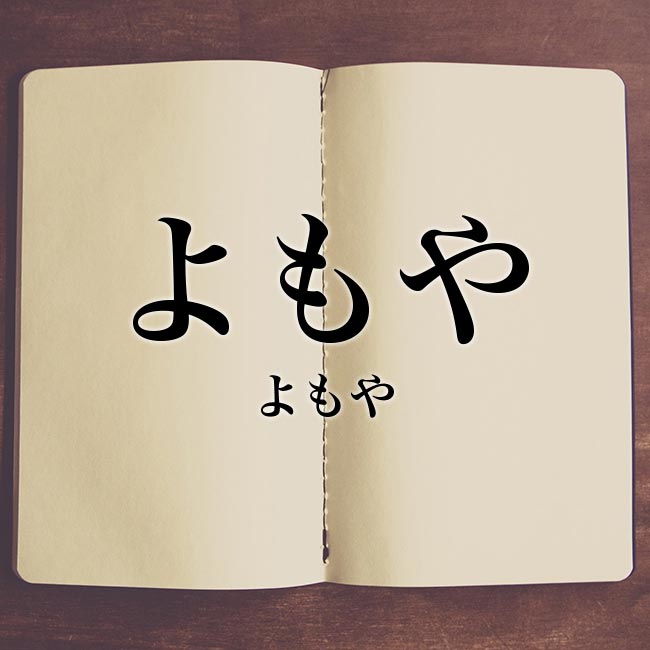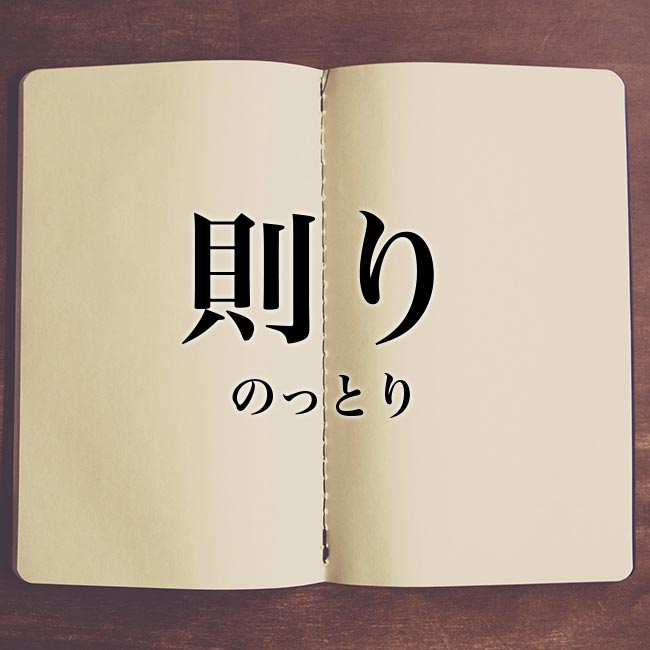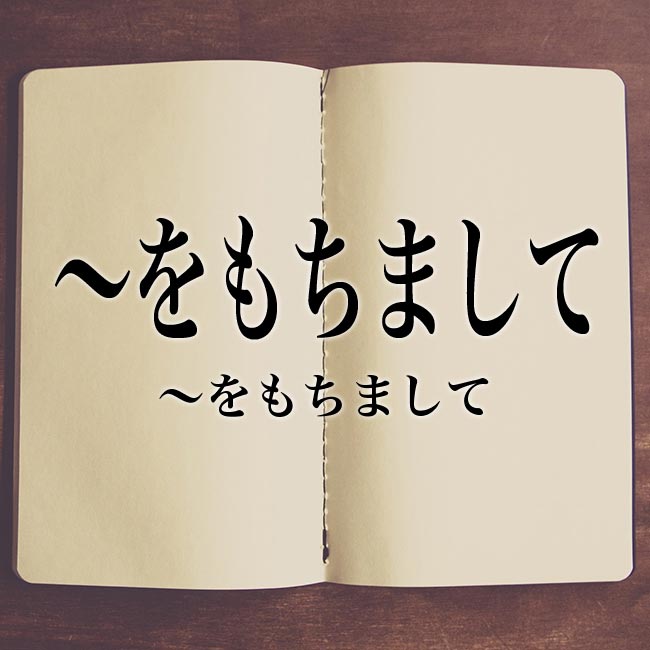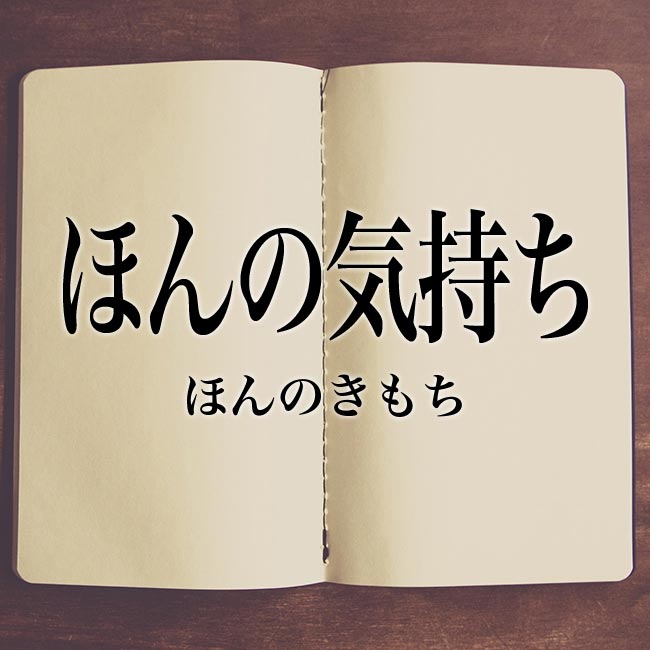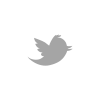「中締め」の意味とは!類語や例文など詳しく解釈
会社の飲み会などで「中締め」という言葉が使われることがあります。
一体どの様な意味なのか、タイミングなどについても紹介します。
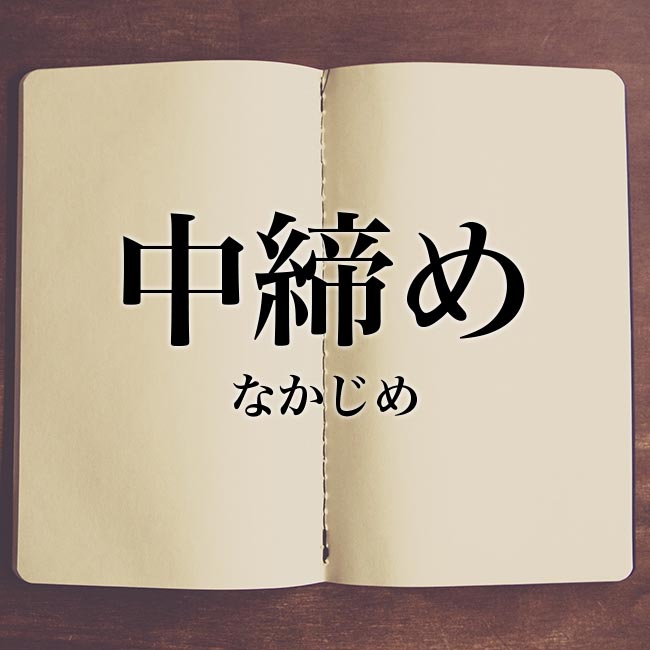
目次
- 「中締め」の意味
- 「中締め」の表現の使い方
- 「中締め」を使った例文と意味を解釈
- 「中締め」の類語や類義語
「中締め」の意味
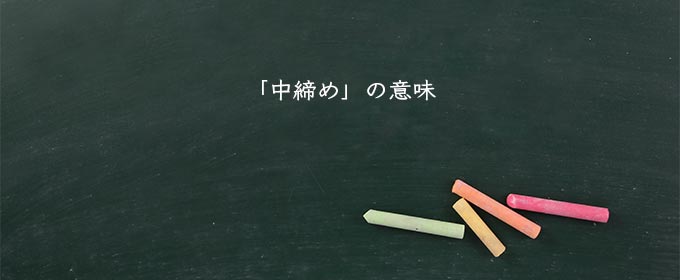
「中締め」とは、「宴会の終わりを告げる為の挨拶や儀式のこと」という意味です。
宴会や食事会などを開いた時に、「そろそろ終わりですよ」ということを知らせる為に、上司のスピーチをしたり、手締めをすることを言います。
一般的には「中締め」をした後は退出しても良く、一般参加の人はお店の外に出ます。
少しずつ時間をかけて皆が外に出て、帰宅する人はそのまま帰り、幹事や身内のスタッフが引き上げたところところで「本締め」になます。
- 「中締め」の読み方
- 「中締め」をするタイミングと意義
「中締め」の読み方
「中締め」の読み方は、「なかじめ」になります。
「ちゅうじめ」と読み間違わない様にしましょう。
「中締め」をするタイミングと意義
「中締め」は、宴会にけじめを付ける意義があり、2時間コースで予約をしていた場合、2時間になるタイミングで行われます。
これは「1度けじめをつけて、帰宅する人、2次会に行く人が行動し易くする」という意義があります。
その為に、上司がきちんとしたスピーチをしたり、1本締め・3本締めなどをして、「これで終わり」ということを示すのです。
忘年会シーズンになると、夜に飲食店の前で立ち話をしている集団を見掛けますが、「中締め」をして一旦外に出て、二次会の指示を待っている人達です。
「中締め」の表現の使い方
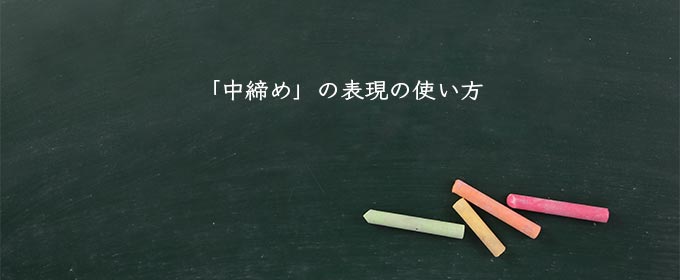
「中締め」の表現の使い方を紹介します。
- 文法的な使い方
- お客さんに対して使われる
文法的な使い方
「中締め」は名詞であり、文末に使う時には動詞を伴って「中締めする・した」になります。
使い方が限られているので、特に変化形などはありません。
お客さんに対して使われる
「中締め」は、お客さんを招いて宴会を開いた時に、お客さんが速やかに行動できる様にするものです。
「中締め」をしてお客さんが全員退出した後、5分~10分後に閉会をします。
つまり、通常はメンバーのみ、社内の宴会などでは「中締め」はしないのです。
「中締め」を使った例文と意味を解釈
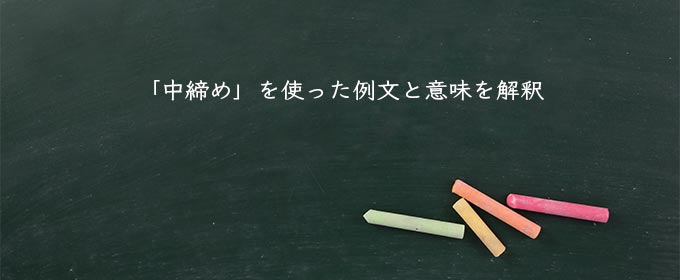
「中締め」を使った例文とその意味を解釈していきます。
- 「中締め」を使った例文1
- 「中締め」を使った例文2
「中締め」を使った例文1
「中締めの挨拶が終った後1本締めをした」
宴会で、終わりを伝える挨拶をした後に、1本締めをしてけじめを付けたことを表しています。
「中締め」を使った例文2
「中締めの後で2次会参加者を募って移動した」
2次会が終った後で、希望者が集まって2次会に行ったことを表しています。
「中締め」の類語や類義語
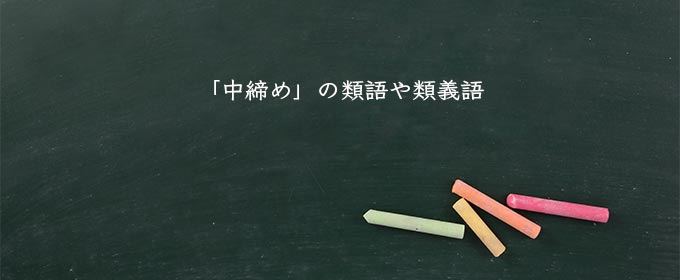
「中締め」の類語や類義語を紹介します。
- 「お開き」【おひらき】
- 「手仕舞い」【てじまい】
「お開き」【おひらき】
「会合や宴会などを終わりにすること」という意味です。
「手仕舞い」【てじまい】
「それまで続いていたものをそこで終わりにすること」という意味です。
「中締め」は「宴会の終わりを告げる為の挨拶や儀式のこと」という意味です。
外部の人を招いて宴会を開いた時に使いましょう。