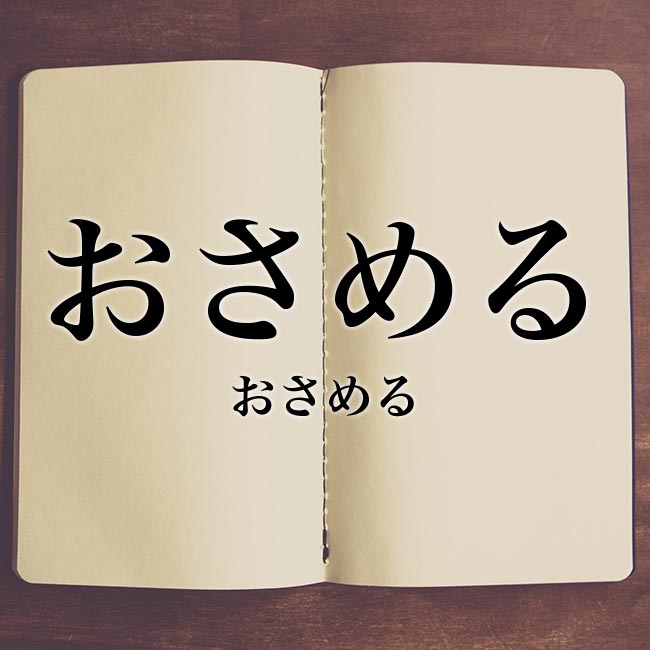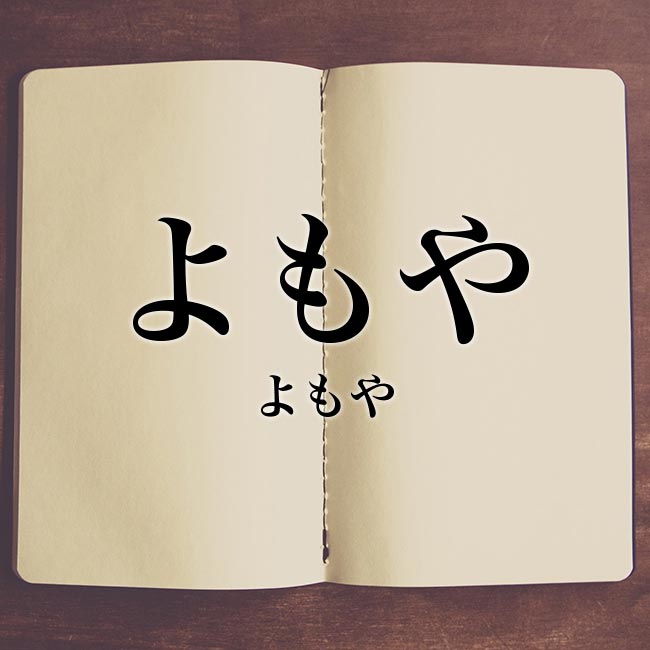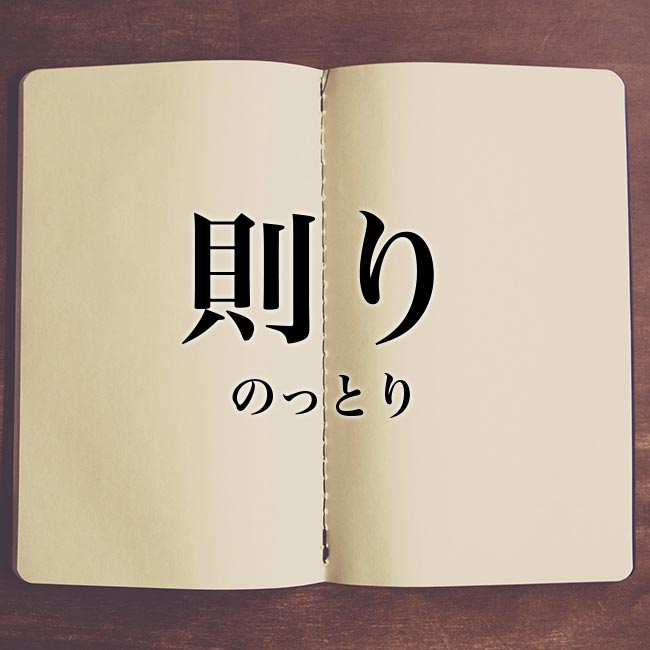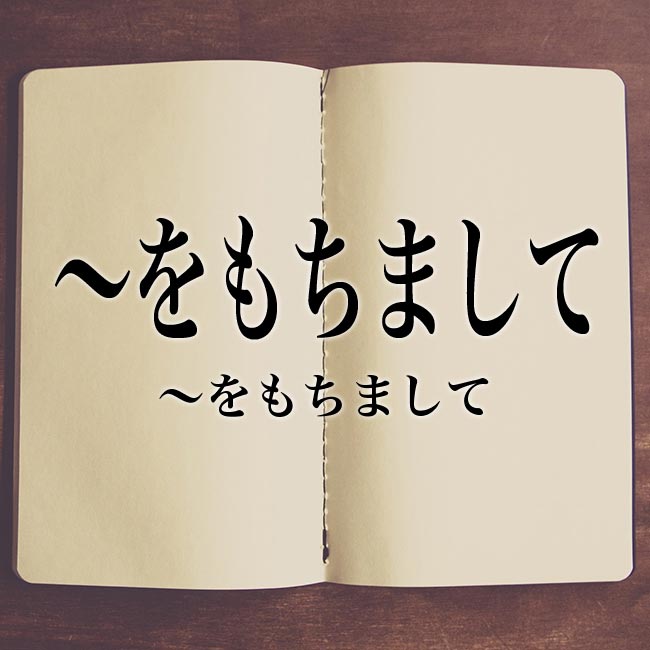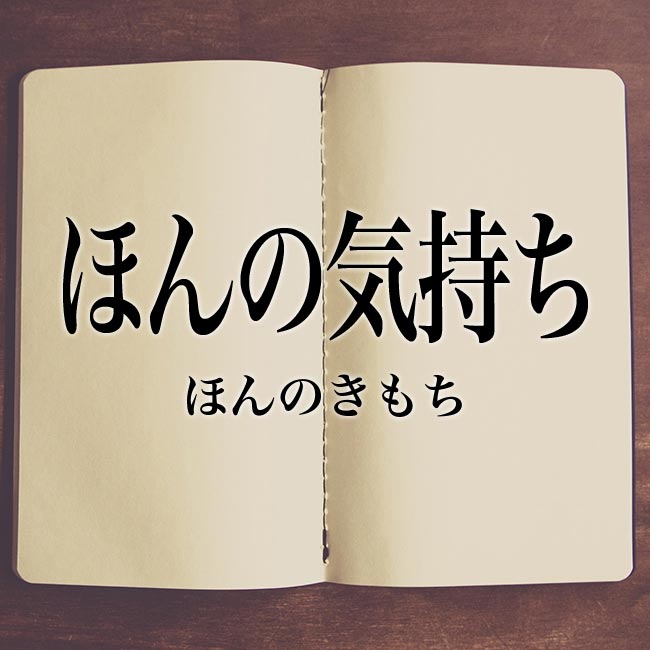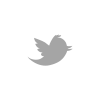「相互扶助」の意味とは!類語や例文など詳しく解釈
皆さんは「相互扶助」という言葉をご存知かと思います。
この言葉は、人同士が助け合う理想的な姿を実現させる素晴らしい言葉の1つと言えるでしょう。
そこで今回は、この「相互扶助」にフォーカスして、言葉の意味・使い方などを見ながら、考察していくことにします。
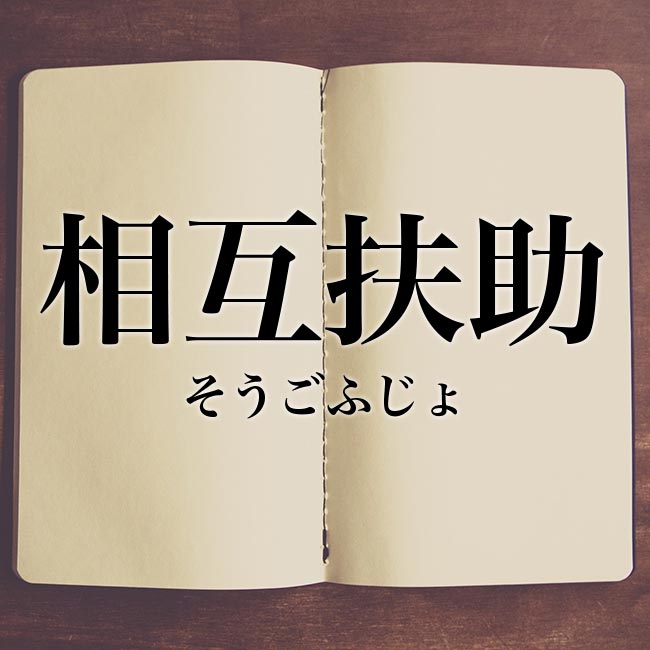
目次
- 「相互扶助」とは?意味
- 「相互扶助」の表現の使い方
- 「相互扶助」を使った例文と意味を解釈
- 「相互扶助」の類語や類義語
「相互扶助」とは?意味
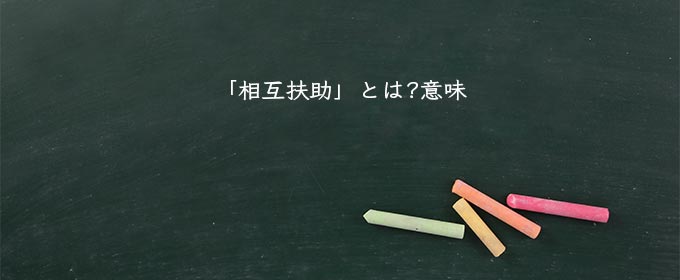
「相互扶助」には、「社会・組織に所属しているメンバー同士が互いに助け合うこと」という意味があります。
世の中に存在する生物やあるいは社会・組織は、競争や闘争によって発達するのではなく、自発的に協同していくことによって進歩するという考え方があります。
そのことが「相互扶助」の真の解釈であり、意義として受け止めることができます。
- 「相互扶助」の読み方
「相互扶助」の読み方
「相互扶助」は「そうごふじょ」と読みますが、「相互」も「扶助」も少し難しい漢字になるので、読み方をキチンと押さえておくようにしてください。
「相互扶助」の表現の使い方
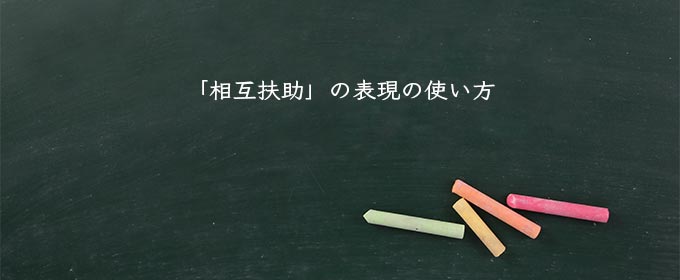
「相互扶助」は「メンバーや仲間同士が助け合い協力して生きていくこと」という意味合いがありますので、災害に遭った被災者同士が助け合うケースや平素においては、保険に関することで使われることになります。
「相互扶助」を使った例文と意味を解釈
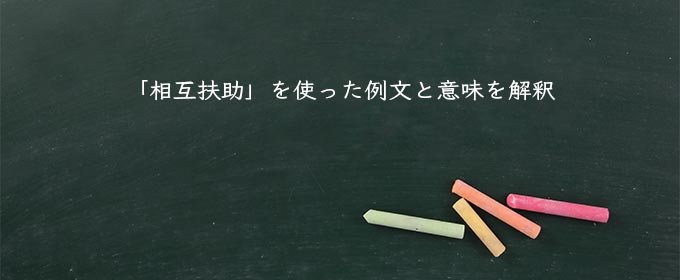
では、ここで「相互扶助」を使った例文を見ながら具体的な活用シーンをイメージしてみることにしましょう。
- 「相互扶助」を使った例文1
- 「相互扶助」を使った例文2
「相互扶助」を使った例文1
「共済組合は、地元住民の相互扶助を目的とした団体であり、人々の暮らしの安心・安全を実現している」
共済組合こそ「相互扶助」の精神を具現化した典型的な事例と言えるでしょう。
人は、困った的に1人では何もできないことが少なくありません。
そのような時にはお金にまつわることで苦労するのですが、保険的な機能を果たしてくれるのも、共済組合です。
最近の若い世代の人々にとっては、共済組合に対する意識は希薄になっているようですが、この年代のうちに「相互扶助」の意義を理解しておくことが大切です。
「相互扶助」を使った例文2
「防災無線は、近隣相互扶助のための連絡通報システムとして、非常時だけでなく、日常生活の中でも貢献しています」
防災行政無線というと、非常事態時における近隣相互扶助を目的としたの連絡通報システムとして活躍しています。
しかし、平常時でも、日常生活に役立つ情報を伝えるためにも使われることがあります。
「相互扶助」を目的としたシステムであり、地元住民の生活に密着した設備でもあります。
「相互扶助」の類語や類義語
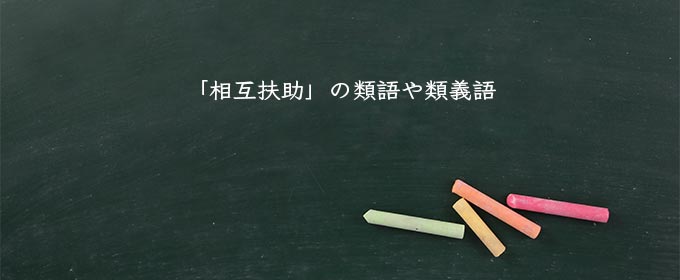
「相互扶助」を他の言葉で言い換えるとするなら、他にどのような言葉があるかを見ていくことにしましょう。
- 「肩を寄せ合う」【かたをよせあう】
- 「協力し合う」【きょうりょくしあう】
「肩を寄せ合う」【かたをよせあう】
「肩を寄せ合う」という言葉が、「相互扶助」乗る意義に当てはまることと思います。
「弱い者同士が助け合い、結束して生きていく」という意味があり、「幼い子供達が肩を寄せ合って生きてきた」というような使い方をしています。
「協力し合う」【きょうりょくしあう】
「協力し合う」も「相互扶助」の類義語として扱うことができます。
「お互いに助け合っているさま」という意味で使われます。
「相互扶助」という言葉の意味や使い方を紹介してきましたが、やはり私達が安全に暮らしていくためには、この精神が必要不可欠です。
常日頃からこの気持ちを忘れないようにしたいものです。