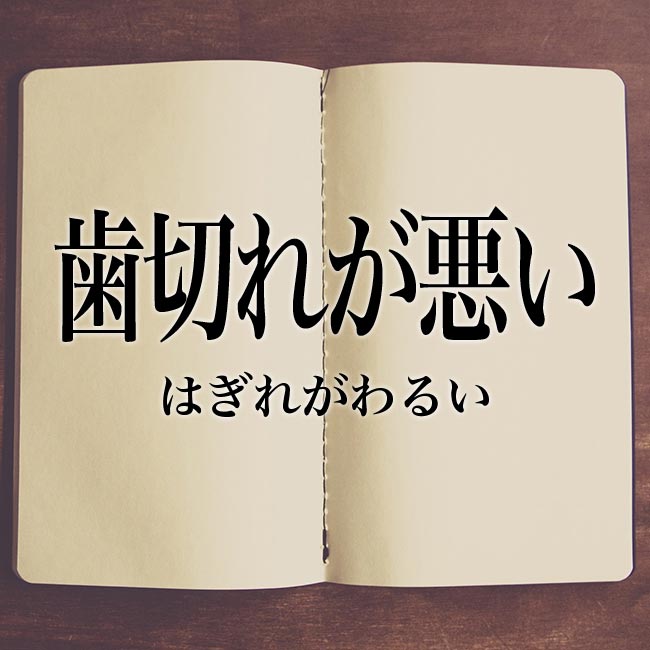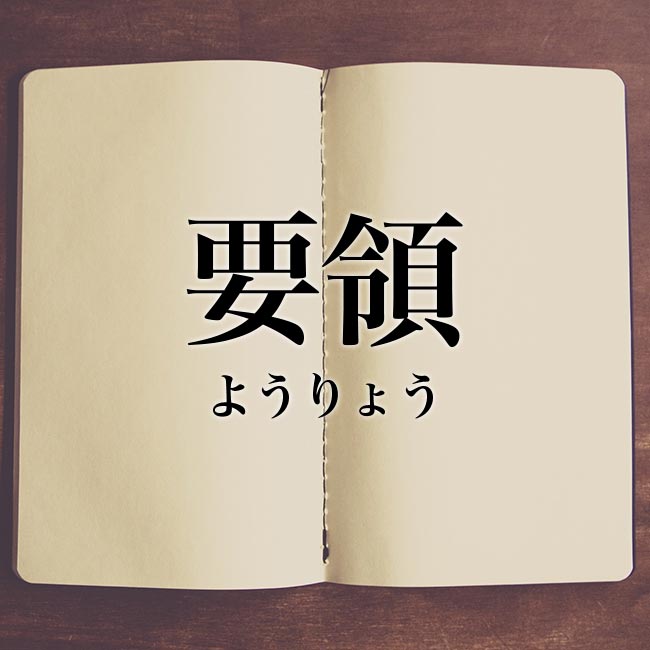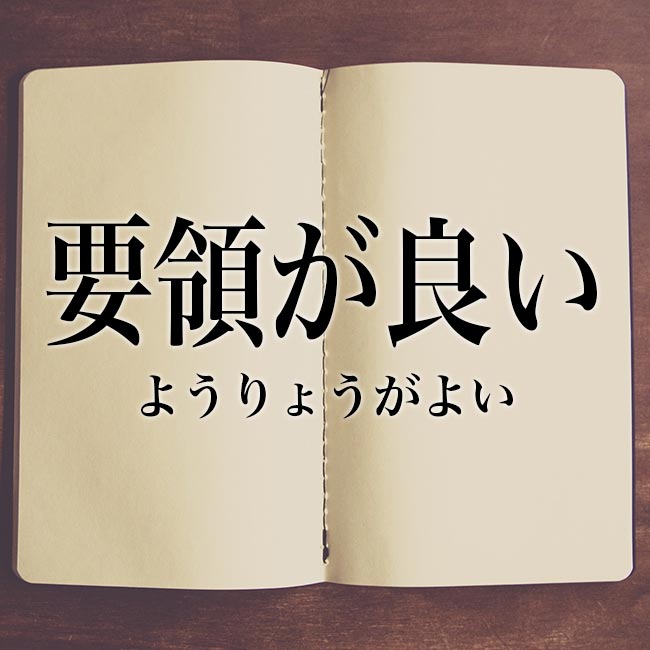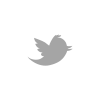「要領を得ない」とは?意味や類語!例文や表現の使い方
「要領を得ない」という表現を使ったことがあるでしょうか。
誰かに話をする時、ぜひこうならないように気をつけたいものです。
ここでは、この表現の意味について解説していきます。
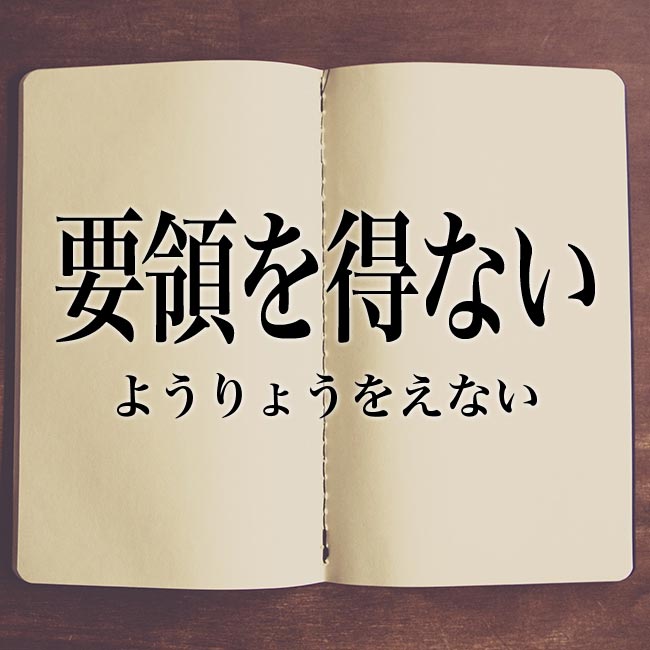
目次
- 「要領を得ない」とは?
- 「要領を得ない」を分解して解釈
- 「要領を得ない」の表現の使い方
- 「要領を得ない」を使った例文と意味を解釈
- 「要領を得ない」の類語や類義語・言い換え
「要領を得ない」とは?
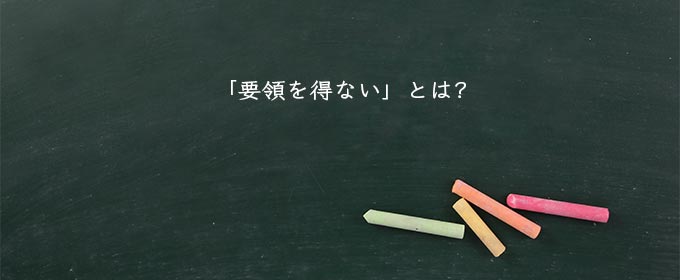
この表現には要点がわからない、主要な点がはっきりしない、本質が見極めにくい、という意味になります。
誰かから話を聞いたときなど、後から「結局何が言いたかったんだろう」「それで、何が言いたいの?」などと思った経験を持つ人もいるのではないでしょうか。
自分が話をした後、「結局何が言いたいのか伝わらなかったかもしれない」と反省した経験を持つ人もいるかもしれませんね。
歯切れが悪い、何が言いたいのかわからない、などという場合にこの表現が使われます。
仕事をする時など、「要領を得ない」と指摘されたら気をつけなければいけません。
- 「要領を得ない」の読み方
「要領を得ない」の読み方
「要領を得ない」という表現は「ようりょうをえない」と読みます。
特に職場でよく使われる言葉ですので、ぜひ覚えておきましょう。
「要領を得ない」を分解して解釈
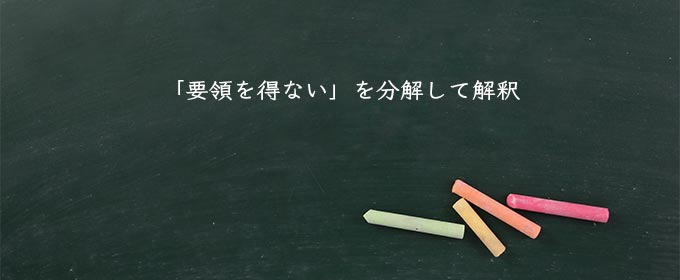
ここではこの表現を分解して紹介していきます。
- 「要領」
- 「得ない」
「要領」
要領という言葉には物事の最も大事な点、要点、という意味があります。
物事の主要の部分であり、大切な部分という意味になります。
「得ない」
得ないという言葉には、この前に来る単語に対してそれがない、それができていない、という意味になります。
つまり「要領を得ない」という事は物事の主要な部分が捉えられていない、という意味になるのです。
「要領を得ない」の表現の使い方
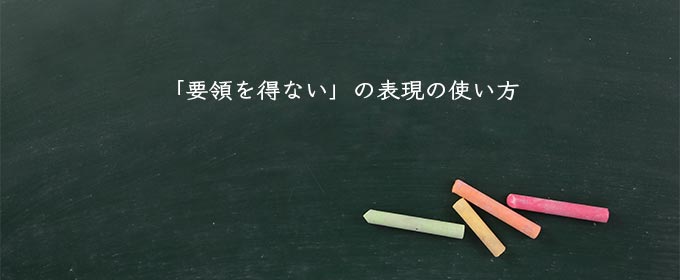
誰かと話をしているとき、「この人は一体何が言いたいのかよくわからない」と感じた経験を持つ人もいるのではないでしょうか。
これ以外にも、例えば理解しているのか理解していないのかわからないなどという場合も「要領を得ない」という表現が使われます。
「要領を得ない」を使った例文と意味を解釈
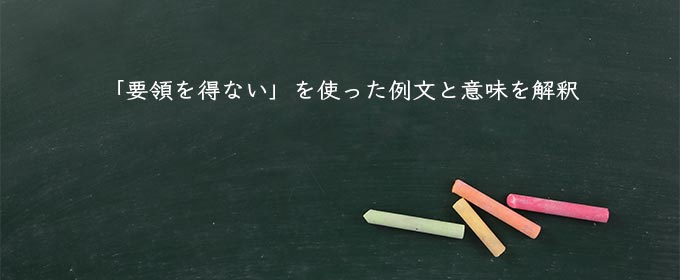
ここでは、「要領を得ない」という表現を使った例文を紹介します。
- 「要領を得ない」を使った例文1
- 「要領を得ない」を使った例文2
「要領を得ない」を使った例文1
「彼女の返事はいつも大体要領を得ないので、きちんと理解をしているのかどうか判りません」
特に職場においては、ちゃんと理解をしているかどうか相手に示すということも大切です。
わからないことがあるならば、しっかりと質問をしなければいけません。
「要領を得ない」返事をし、後から「よくわかりません」ということでは社会人としても失格です。
また、「要領を得ない」返事をするのではなく、わかったならばわかった、わからないならばわからない、とその場ではっきりいう癖をつけることも大切です。
「要領を得ない」を使った例文2
「彼の話はいつも要領を得ないため、嫌になってしまいます」
誰かの話を聞いていても、要領の得ない話は時間の無駄だと思ってしまうこともあるのではないでしょうか。
結局何を言いたいのかわからない、話のポイントがわからない、それを聞いてもわからない、などという場合は「何が言いたいのか話の筋道を立ててから来てくれ」と思うこともあるかもしれません。
誰かの時間を無駄にしないためにも、「要領を得ない」話し方は避けなければいけません。
「要領を得ない」の類語や類義語・言い換え
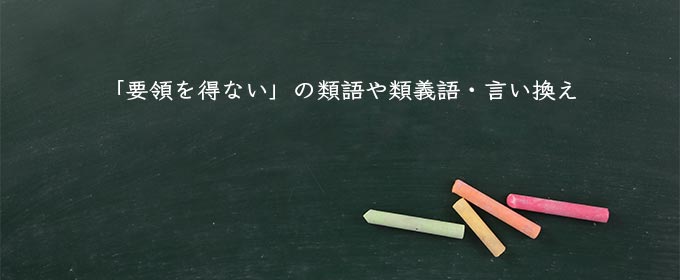
ここでは類義語を紹介します。
- 「歯切れが悪い」【はぎれがわるい】
- 「何が言いたいのかわからない」【なにがいいたいのかわからない】
- 「不得要領の」【ふとくようりょうの】
「歯切れが悪い」【はぎれがわるい】
歯切れが悪い、というのはいい様がはっきりしないという意味です。
言い方がはっきりせず、言葉を濁しているようなときに使われます。
「何が言いたいのかわからない」【なにがいいたいのかわからない】
何が言いたいのかわからない、というのはその表現の通り、一体何が言いたいのか要領がつかめない、主要点がハッキリしない、という意味になります。
何が言いたいのかそもそもわからない場合、まず言いたいことをはっきりさせてから話す癖をつけましょう。
「不得要領の」【ふとくようりょうの】
不得要領というのは「要領を得ない」という意味です。
「ふとくようりょう」と読み、要点がはっきりしない場合にこの表現が使われます。
「要領を得ない」という表現は日常的にも使える言葉ですのでぜひ覚えておきましょう。
何かを発言するときには要点をはっきりさせ、話相手の時間を無駄にしないということも大切です。