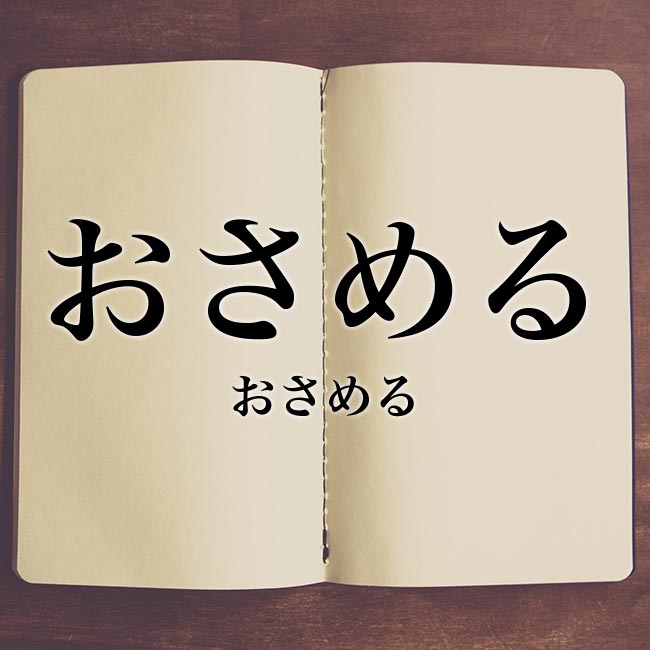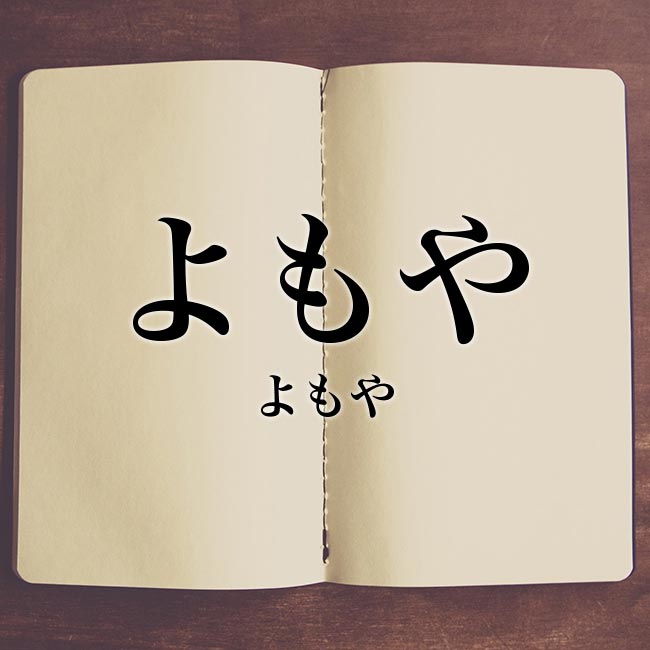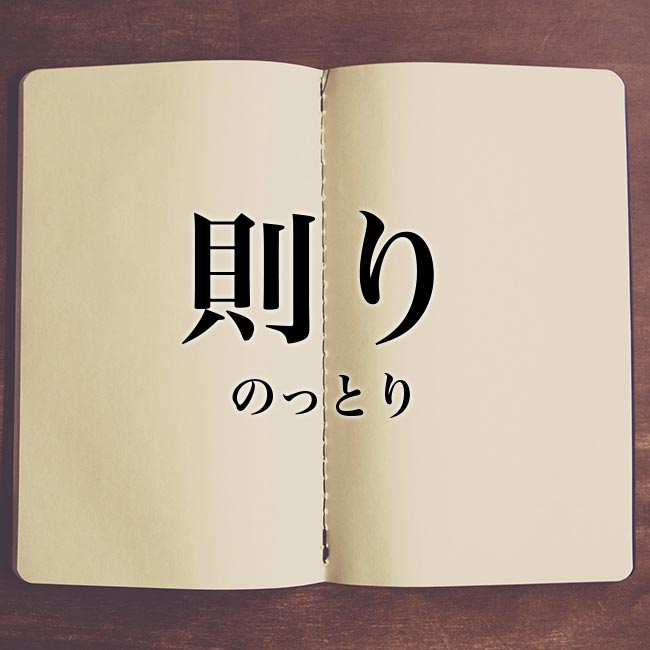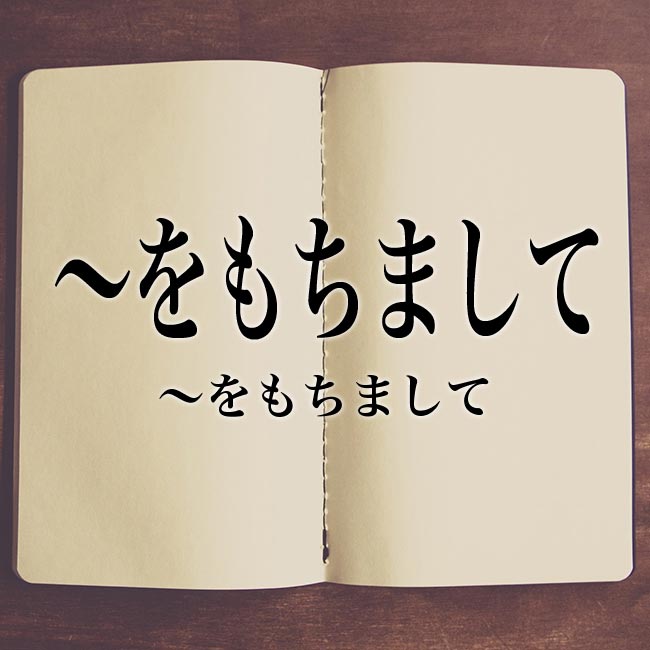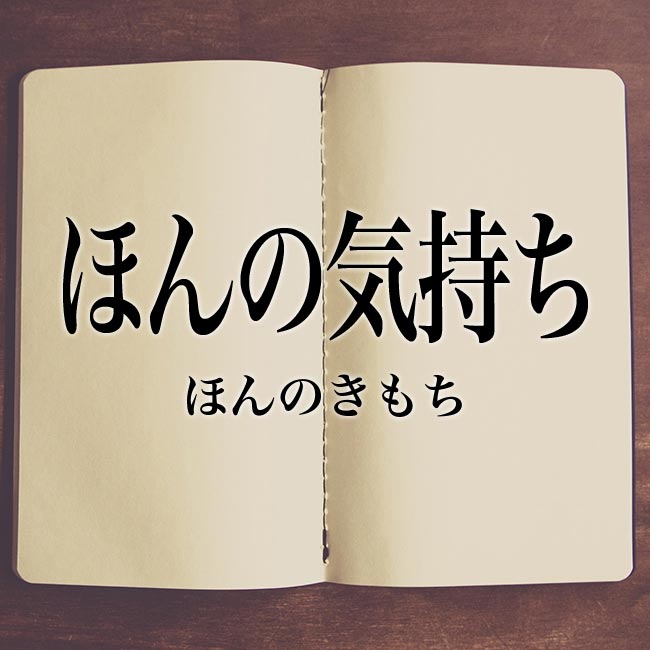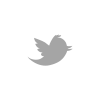「薩奸」とは?「薩賊」、「奸賊」も解釈!
現在の鹿児島県や山口県は、かつて薩摩(さつま)や長州(ちょうしゅう)と呼ばれていた時代がありました。
この時代で有名なのは、西郷隆盛と桂小五郎による薩長同盟です。
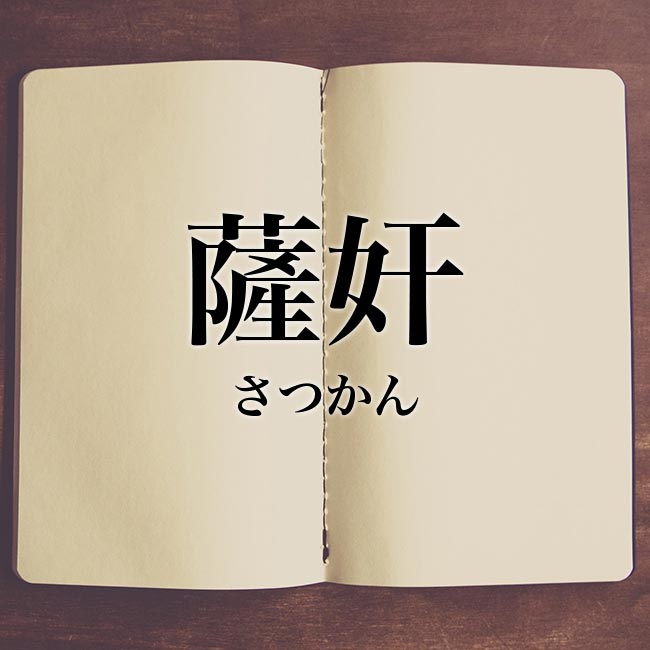
目次
- 「薩奸」とは?
- 「薩摩」とは?
- 「奸賊」とは?
- 「薩賊」とは?
「薩奸」とは?
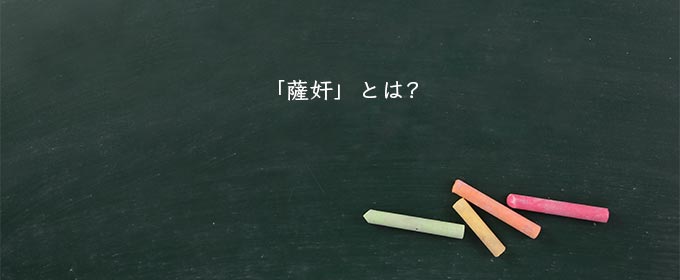
薩長同盟は、1866年に結ばれた倒幕の為の密約です。
6ヶ条からなる約束事で、この締結に尽力したのが薩摩藩の西郷隆盛、及び長州藩の桂小五郎でした。
この薩長同盟が歴史的に有名な為、薩摩藩と長州藩はそれ以前からそれほど悪い関係ではなかったと思われているかも知れませんが、実はお互いに、最大の敵である幕府と同様の存在ほどに嫌い合っていたのです。
その頃には長州藩は薩摩藩のことを「薩奸」(さつかん)という蔑称で呼ぶことがありました。
「薩摩」とは?
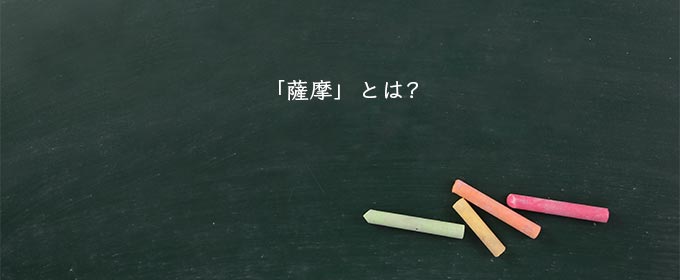
薩摩は、先の説明のように、現在の鹿児島県(の西地方)に当たります。
江戸時代の令制国(現在の都道府県に該当します)により、薩摩藩と呼ばれていた行政地域の1つです。
現在でも、鹿児島県で作られる焼酎に「薩摩焼酎」というブランドが付いているように、廃藩置県によって薩摩藩が消滅した後も、この「薩摩」という表現を聞くことがあります。
「奸賊」とは?
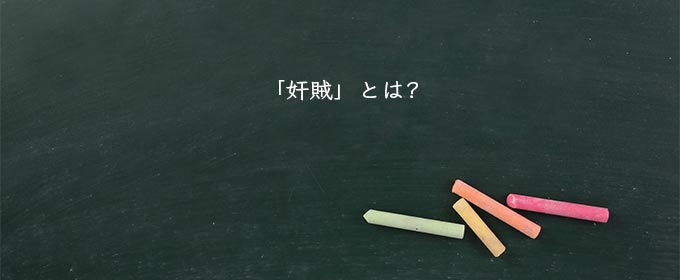
「奸賊」(かんぞく)とは、心から憎む相手に対する蔑称として用いられます。
その相手が○○であれば、この言葉を略して「○○奸」と使うことがあります。
ただ憎んでいるだけでなく、対象が自分たちの志の邪魔をしている、尊敬の対象の敵であるといった場合によく用いられる表現です。
現在ではあまり見聞きしませんが、政治の世界ではたまに使われることがあります。
長州藩が薩摩藩と敵対していた頃、長州は薩摩のことを「薩摩」の方も略して「薩奸」と呼んでいたのは前述の通りです。
「薩賊」とは?
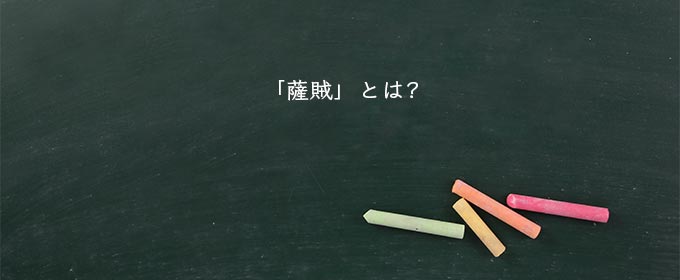
上の「薩奸」は、「薩」摩と「奸」賊から作られた言葉ですが、こちらの「薩賊」(さつぞく)は、「薩」摩と奸「賊」を組み合わせた言葉です。
つまり、「奸賊」のどちらの漢字を使っているかの違いで、意味は同じく「心から憎むべき薩摩」だと考えてください。
尚、長州藩は会津藩とも敵対関係にあった為、「薩賊会奸」(さつぞくあいかん)とまとめて「会津」も「奸賊」だと表現していた時期がありました。
この「薩奸」という言葉は、その時代を描いた歴史小説や漫画でそれなりに見掛けることがある言葉です。
一般にはまず聞きませんが、このような成り立ちで作られたと覚えておいてください。