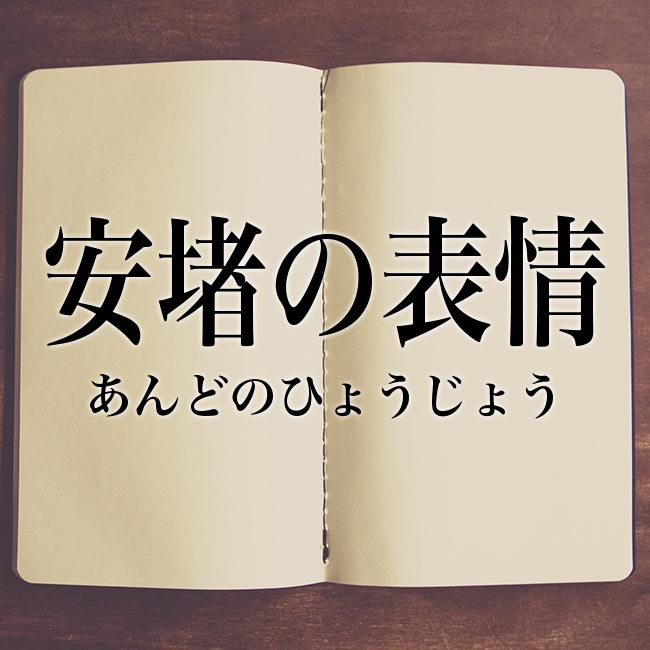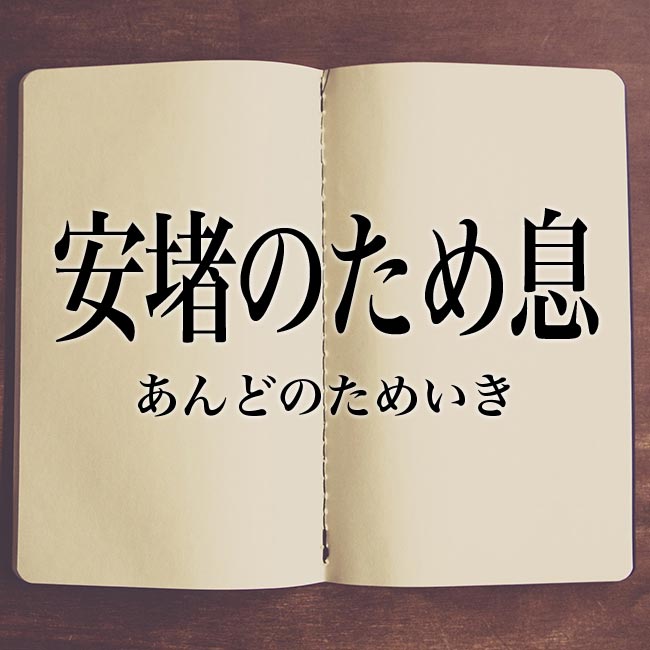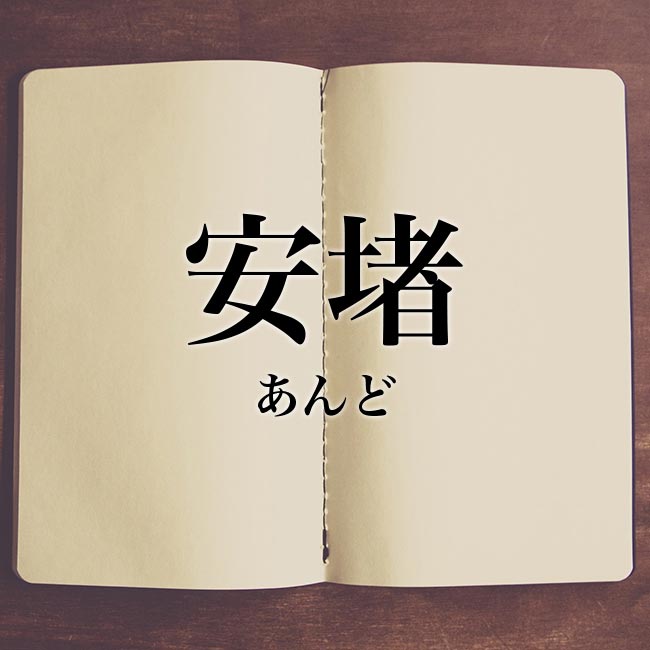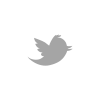「安堵の息」とは?意味や例文など解釈
「安堵の息」、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
「安堵の息を漏らす」、「安堵の息を吐く」、などという表現がありますが、これらは一体何を表す表現なのでしょうか。
ここでは「安堵の息」、という言葉について紹介します。
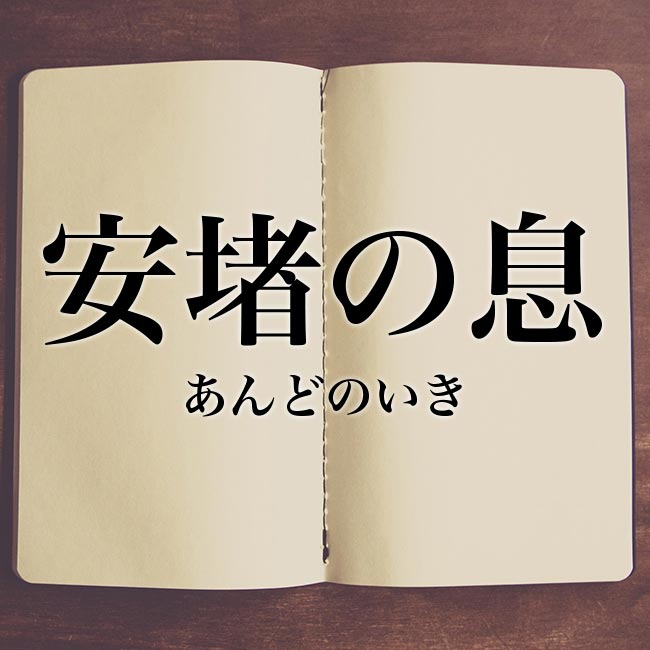
目次
- 「安堵の息」とは?
- 「安堵の息」を使った例文や短文など(意味を解釈)
- 「安堵の息」の類語
- 「安堵の息」の英語や例文(解釈)など
「安堵の息」とは?
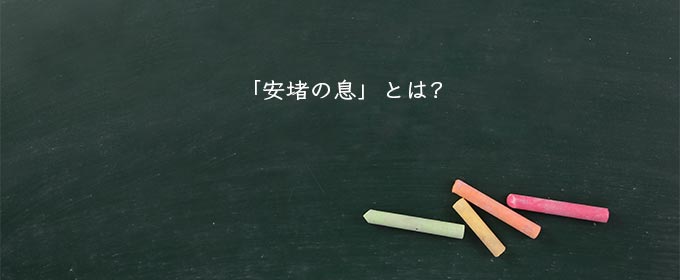
「安堵の息」という表現は心を落ち着かせること、ほっと安心する、ほっとする、という意味があり、安心のため息をつくこと、という表現があります。
何かを心配していた時など、良い結果を聞いて安心することがありますよね。
例えば家族が手術を受けていた時に無事に手術が終わったという知らせを聞いたり、子供の進学を心配していたら志望校を合格したという話を聞いたり、そのようなときには安心するのではないでしょうか。
もしもうまくいかなかったらどうしよう、などという深刻なことを考えていたときには特に、良い結果を聞くと安心するものです。
- 読み方
読み方
「安堵の息」という言葉は「あんどのいき」と読みます。
安堵するという表現は気がかりなことが覗かれて安心することという意味がありますので、この表現もしっかり覚えておきましょう。
「安堵の息」を使った例文や短文など(意味を解釈)
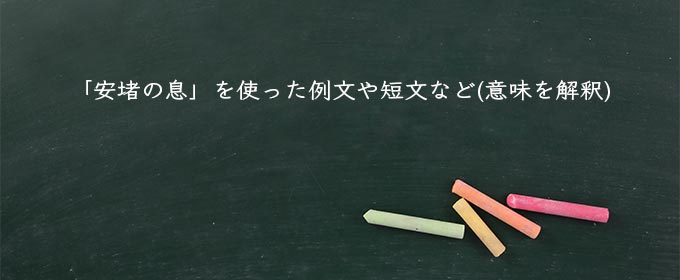
ここでは「安堵の息」という表現を使った例文を紹介します。
- 「安堵の息」を使った例文1
- 「安堵の息」を使った例文2
「安堵の息」を使った例文1
「祖母の手術が無事に終わって、安堵の息を漏らした」
祖母の手術が無事に終わると安心ですよね。
年齢ということもあり、病気で手術をすることもありますし、怪我で手術をするということもあります。
歳をとると、転んだだけで腰の骨を折ってしまうなどということもありますので気をつけなければいけません。
今までどれだけ元気だったとしても、転んでしまったところから動けなくなり、そのまま寝たきりになっていくということもあります。
いつまでも元気でいるためにも、健康はとても大切です。
健康でいるためには食事なども気をつける必要があります。
「安堵の息」を使った例文2
「息子の転校を心配していたが、初日から友達ができたようで安堵の息を吐いた」
親の生活の変化で子供が転校しなければいけなくなると、子供の性格は大きく変わります。
子供によってはあまり心配しない場合もありますが、慣れた友達から離れて1人で違うところに行く、というのはなかなか勇気が要ることでもあるのです。
そのため、自分の息子が学校に行き、初日から友達ができた、などという良い話を聞くと安心する、という人も多いのではないでしょうか。
「安堵の息」の類語
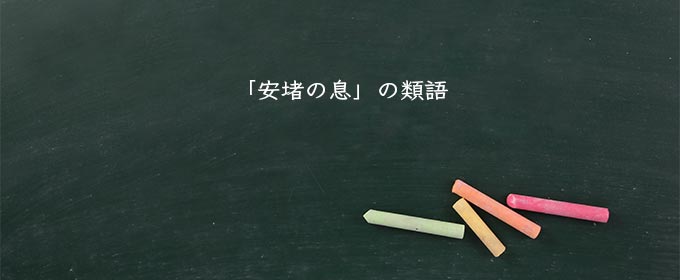
ここでは「安堵の息」という表現の類義語を紹介します。
- 「胸を撫で下ろす」
- 「胸のつかえがとれる」
「胸を撫で下ろす」
胸を撫で下ろすという表現は安心することという意味です。
不安に感じてもいた物事が解決、肩の荷が降りる、ほっとする、という意味になります。
何か不安があった時など、問題が解決すると安心してほっとしますよね。
そのような時には胸を撫で下ろすという言葉が使えます。
「胸のつかえがとれる」
胸のつかえが取れる、というのは不安に感じていた物事が解決して肩の荷が降りる、悩み事や考え事がなくなって気持ちが軽くなる、清々しい気分になる、という意味になります。
胸のつかえが降りるという表現もあります。
「安堵の息」の英語や例文(解釈)など
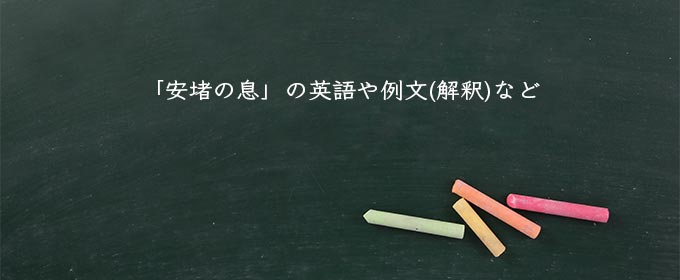
「安堵の息」という表現を“breath of relief”や“sign of relief”などと訳せます。
「彼女は安堵の息を漏らした」、ということであれば“She gave out a sign of relief.”になります。
「安堵の息」、という表現は日常的にも使える言葉ですのでぜひ覚えておきましょう。
安心した時にはほっとできる生活がしたいですね。