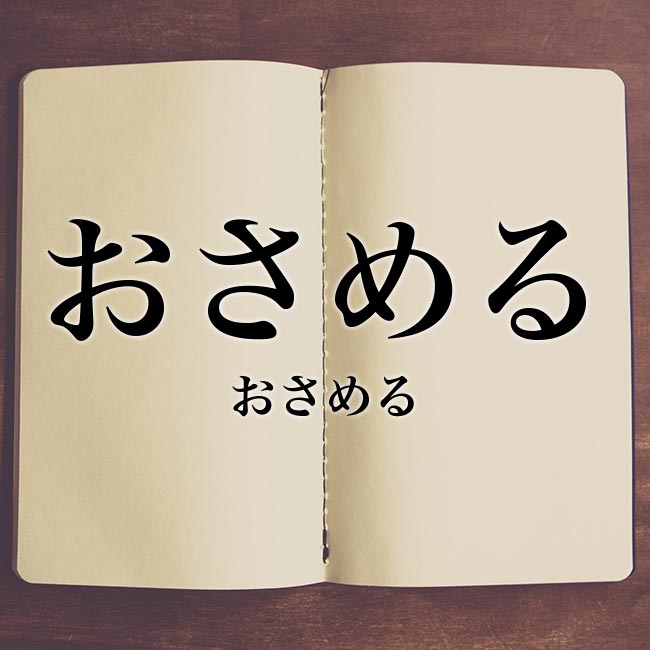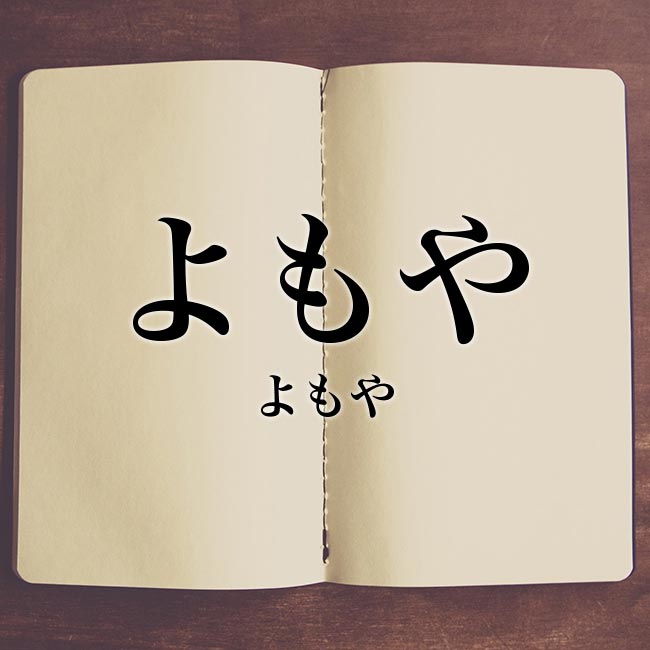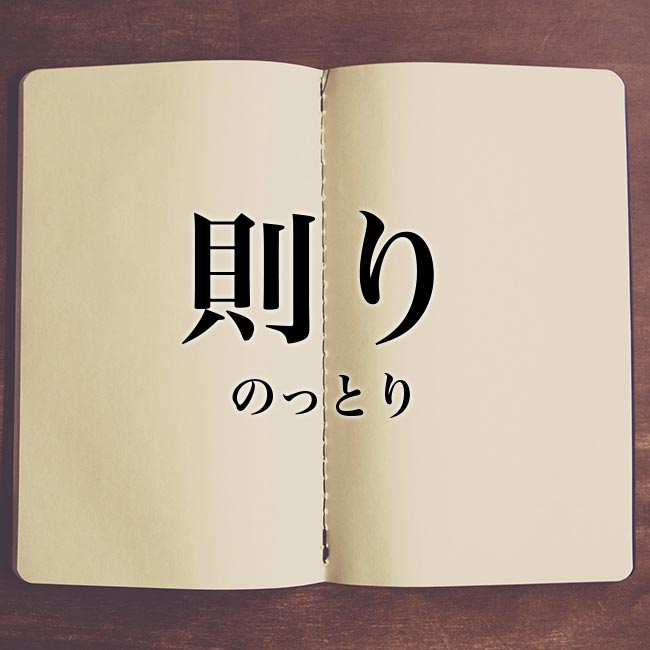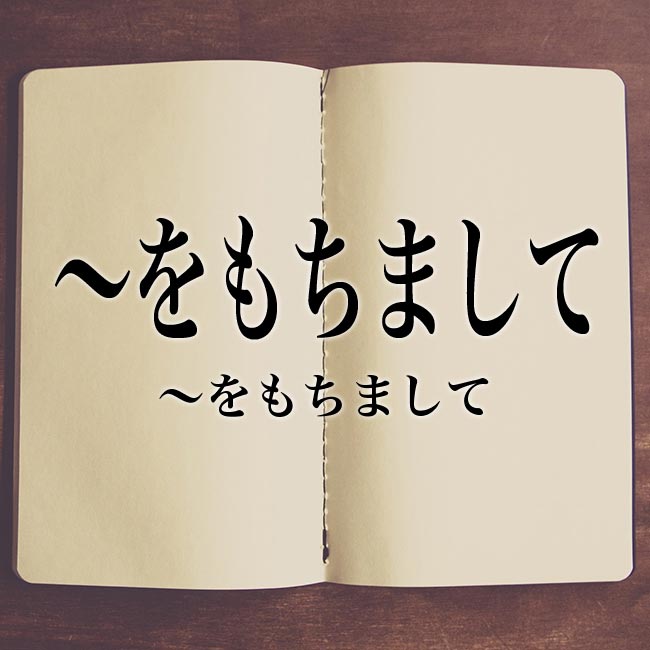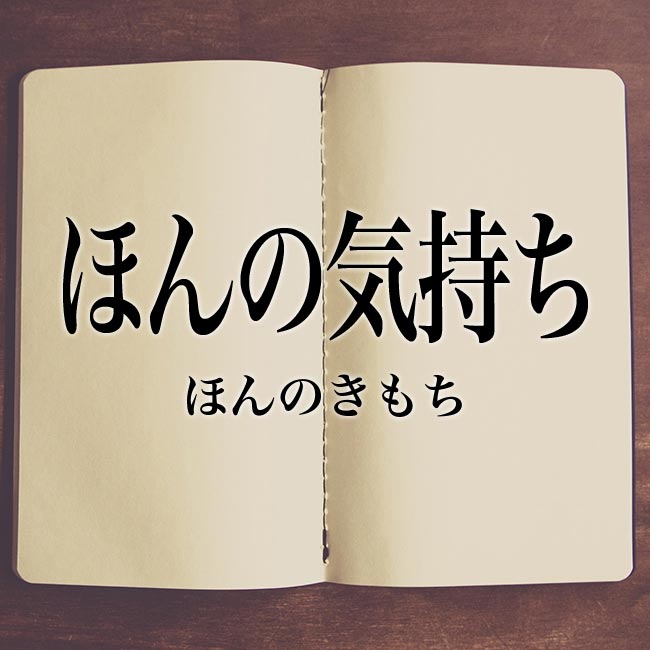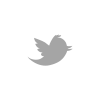「述懐」とは?意味と使い方!例文と類語
少し硬い内容の小説を読んでいると「述懐」という言葉が出てくることがあります。
どの様な意味があるのか、例文や類語などと併せて紹介します。
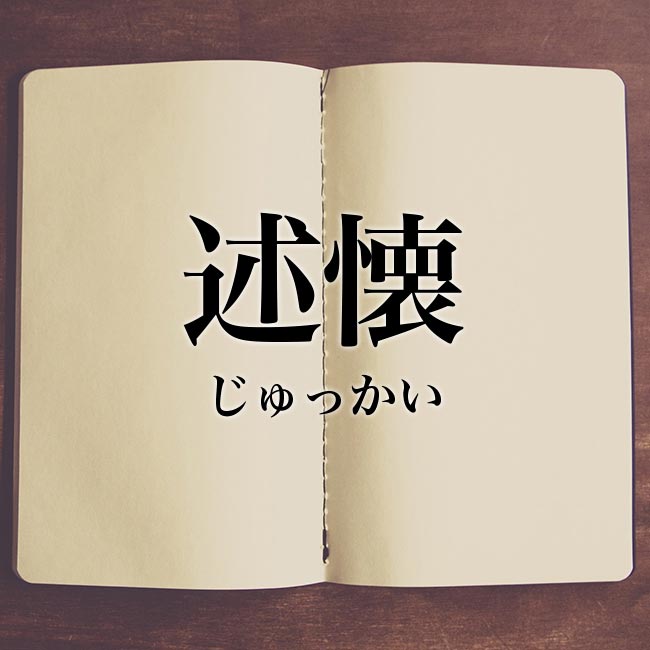
目次
- 「述懐」の意味とは?
- 「述懐」の読み方
- 「述懐」と「回想」の違い
- 「述懐」の言葉の使い方
- 「述懐」を使った例文や短文など(意味を解釈)
- 「述懐」の類語や言い換え
- 「述懐」の英語や例文(解釈)など
- 「述懐」の対義語
「述懐」の意味とは?
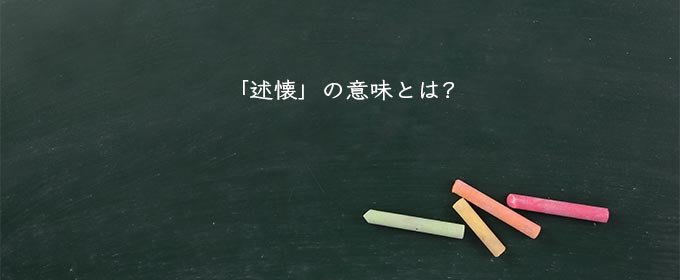
「述懐」の意味と言葉の成り立ちについて紹介します。
- 「自分の思いを述べること」の意味
- 「過去の出来事や様子を述べること」の意味
- 「愚痴や不満、恨みなどを述べること」の意味
- 「述懐」の言葉の成り立ち
「自分の思いを述べること」の意味
自分の気持ちや考えていることを述べることです。
ただ世間話のついでに口にするのではなく、きちんとセッティングされて聞き手がいる時に使われることが多くなります。
今迄あまり人に話す機会がなかった人が何かのきっかけで自分が今思っていることを話す時に使われます。
「過去の出来事や様子を述べること」の意味
過去に起きたことを誰かに訊かれて、改めて思い返して話すことです。
その人しか知らない出来事があり、聞きたいと思う人に対して話すことを言います。
何かの事件に関係していたり、貴重な体験をした人が当時の様子を話す時に使われます。
「愚痴や不満、恨みなどを述べること」の意味
何かに対して愚痴や不満を持っている人が、改めて思い返して文句を言うことです。
強い不満や恨みを持っていると、後から幾らでも文句が出てくるものです。
腹に据えかねていることを吐き出す時に使われます。
「述懐」の言葉の成り立ち
「述懐」の意味をより理解する為に、言葉の成り立ちについて紹介します。
「述」は「のべる・いう」という意味があり、「口述」「供述」などに使われています。
「懐」は「おもう・なつかしい・ふところ・なつく・身にもつ」という多くの意味がありますが、この場合は「おもう」という意味です。
これらの漢字が組み合さり「思っていることを述べる」という意味で使われる様になりました。
「述懐」の読み方
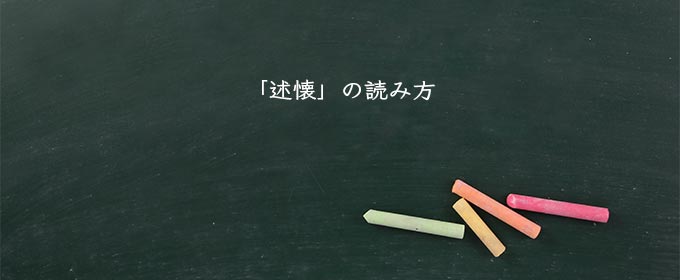
「述懐」は「じゅっかい」と読みます。
「じゅつかい」と読む方が難しいので、素直に覚えてしまいましょう。
江戸時代には「愚痴や不満を言うこと」の意味で使う時には「しゅっかい」と読まれていましたが、現在では全て「じゅっかい」になっています。
「述懐」と「回想」の違い
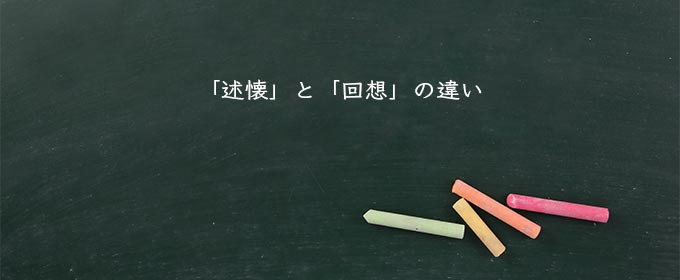
「述懐」と「回想」の違いについて紹介します。
- 「回想」の意味
- 「述懐」と「回想」の違い
「回想」の意味
「回想」の意味は「過去に経験したことを改めて思い起こすこと」です。
昔見たことや聞いたことなどを共に当時の自分を振り返ることを言います。
基本的にかなり昔のことを思いめぐらす時に使われます。
「述懐」と「回想」の違い
「述懐」と「回想」の違いは「言葉に出して述べるかどうか」という点です。
「述懐」は「過去の出来事や自分の思っていることを口頭で述べること」です。
「回想」は「過去の出来事や経験を思い返すこと」です。
どちらも「過去のこと思い出す」という点では同じですが、「言葉にすること」が「述懐」で、「自分の内面で思いめぐらす」のは「回想」です。
「述懐」の言葉の使い方
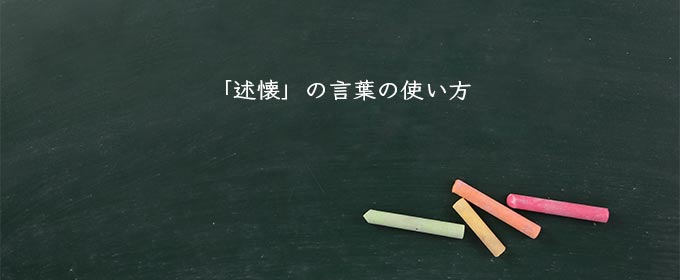
「述懐」の言葉の使い方には以下のポイントがあります。
- 硬い言葉である
- 聞き間違いされる可能性がある
硬い言葉である
「述懐」は硬い表現であり、小説や文学、新聞などの文章で使われることが多くなります。
日常会話で使うと若い人の中には理解できない人もいるので、シンプルに言い換えた方が良いでしょう。
聞き間違いされる可能性がある
「述懐」は「じゅっかい」と読みますが、建物の「十階」、回数の「十回」、モーゼの「十戒」と聞き間違えられる可能性もあります。
コミュニケーションをスムーズにする為には会話の中で紛らわしい使い方は避けた方が良いでしょう。
因みに「十階・十回・十戒」はいずれも正しくは「じっかい」と読むことを覚えておきましょう。
「述懐」を使った例文や短文など(意味を解釈)
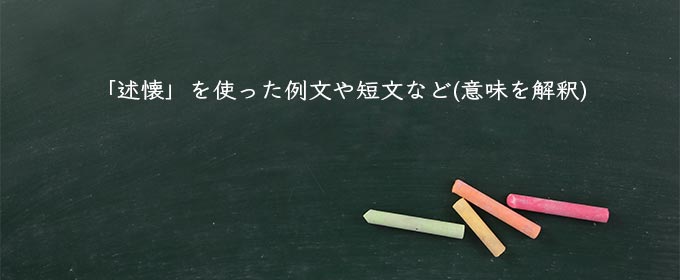
「述懐」を使った例文と解釈を紹介します。
- 「述懐」を使った例文1
- 「述懐」を使った例文2
「述懐」を使った例文1
「祖父は戦争中のことをよく述懐したものだった」
段々と戦争を知っている人が少なくなってきています。
この高齢者も既に故人ですが、生前はよく戦争中に起きたことやその時に自分が思ったことなどを家族にく話していたことが伝わります。
「述懐」を使った例文2
「同窓会の二次会ではそれぞれが当時のことをしみじみと述懐していた」
久しぶりに同窓会を開くと、あまりにも変わった姿に皆驚きます。
一次会では近況報告や共通のエピソードなどで盛り上がるのですが、二次会になるとそれぞれの人が思い出や印象に残っている出来事をしみじみと語る様になるのです。
「述懐」の類語や言い換え
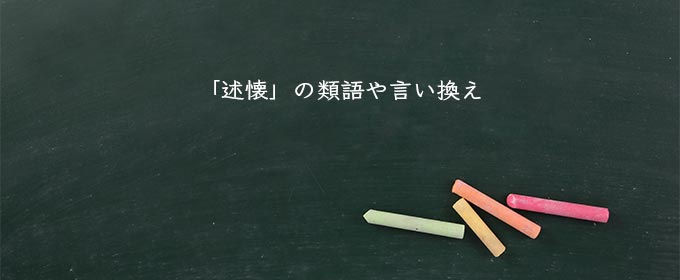
「述懐」の類語を紹介します。
- 「懐古」
- 「吐露」
「懐古」
「かいこ」と読みます。
意味は「古き昔をなつかしく思うこと」です。
自分が経験したことを「なつかしい」「あの頃は良かった」と思いめぐらすことを言います。
こちらの場合、過去の出来事が良い思い出として残っている時に使われます。
また、古き良き時代のものに興味を持つことを「懐古趣味」とも言います。
「吐露」
「とろ」と読みます。
意味は「自分の気持ちや知っていることを全て隠さずに話すこと」です。
「吐」は「はく・口から出す」という意味で、「露」は「露に濡れる場所=屋根がない場所=包み隠さないこと」という意味です。
こちらの場合は過去の思い出に限らず、あらゆる自分の気持ちを話すことを表しています。
「述懐」の英語や例文(解釈)など
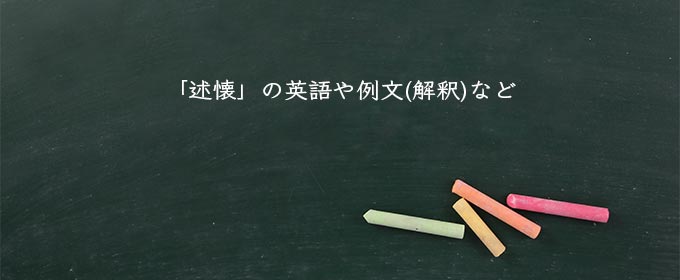
“He reminisced about his youth and spoke it was happy.”
「彼は若い頃を述懐して『幸せだった』と言った」となります。
“reminisce”は非常に難しい単語で「追憶する」「思い出して懐かしむ」という意味があります。
英語には「述懐」という表現はないので「speak」で「述べる」という意味を補うと意味が近くなります。
「述懐」の対義語
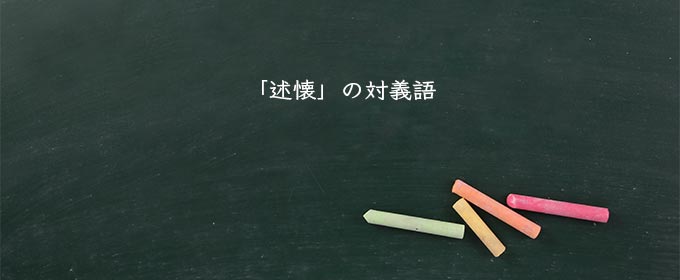
「述懐」には特に対義語はありません。
意味合い的に近い表現は「墓場まで持って行く」でしょう。
「自分が見聞きしたこと、思ったことを全て胸のうちにしまい込み、最後まで誰にも言わずに通すこと」という意味です。
「述懐」には「愚痴や不満を述べる」という意味もあるので、良いことも悪いことも黙ったまま一生を終えるという意味では対義語に近くなります。
「述懐」は「昔あった出来事や自分の気持ちを思い返して述べること」です。
硬い表現なので、文章やスピーチなどで使った方が良いでしょう。
過去のことを思い返すだけではなく、誰かに話してスッキリさせたいと思った時に使うと良いでしょう。