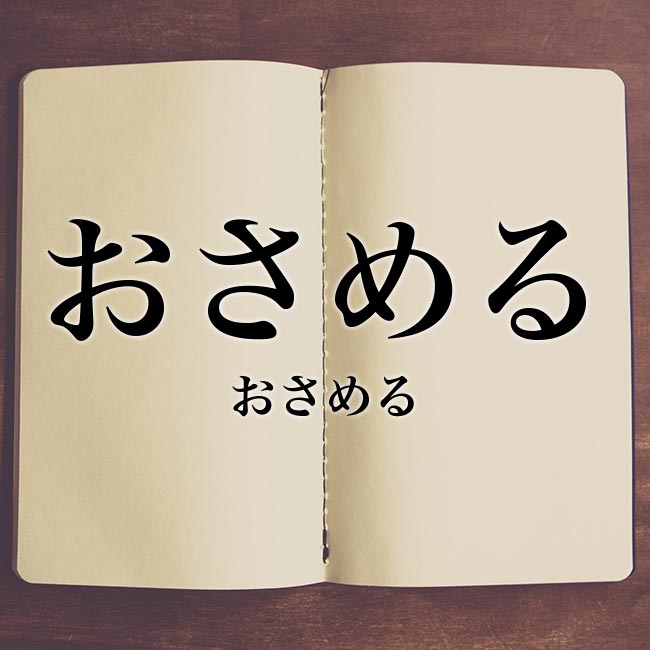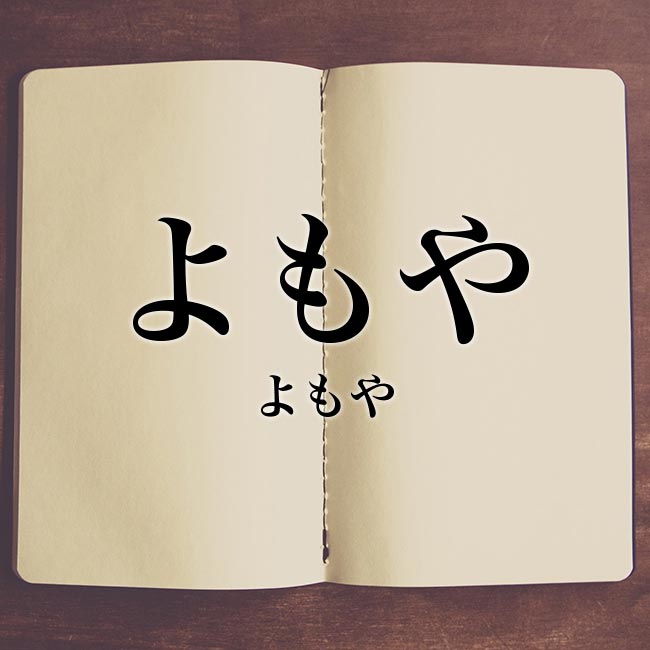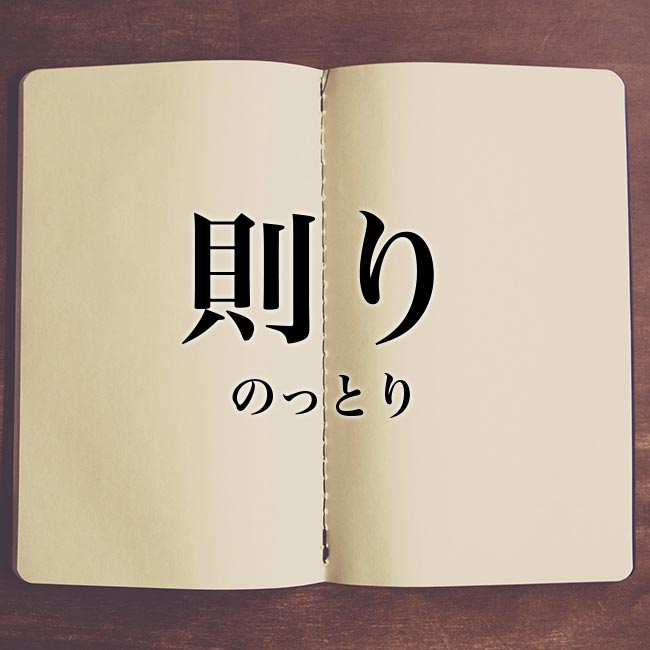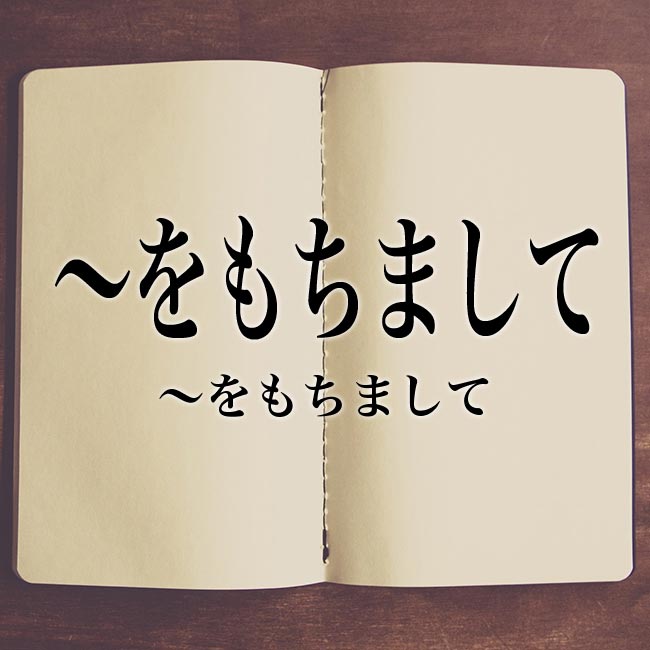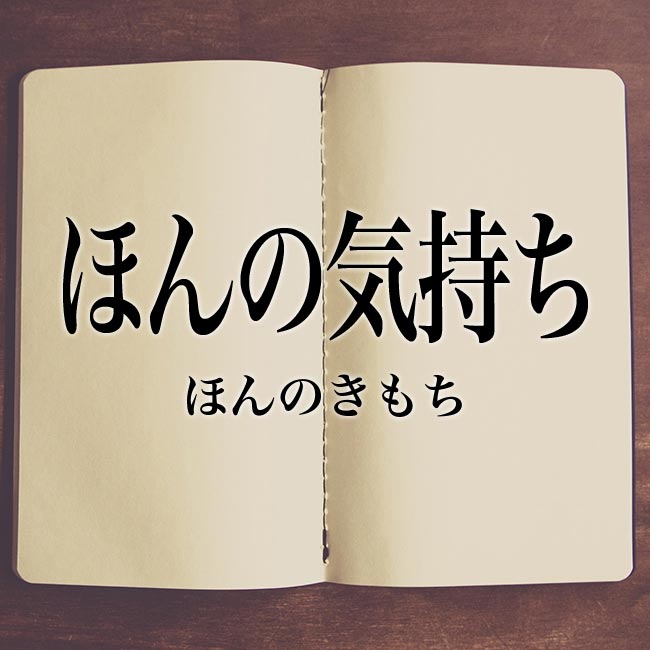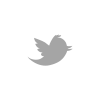「裁量」の意味とは?「裁量」と「常識」「非凡」「常識がない」の違い・英語・類語
昨年から仕事環境が大きく変わってきていますが、「働き方改革」という名の下に、ワークスタイルが多様化しています。
朝早くから満員の通勤電車に潰されるように乗り込んで、オフィスに着く頃には、もうヘトヘト。
夜も定時退社することもできず、深夜まで残業するというパターンはかなり変わり、就業時間内で効率良く仕事をすることが求められています。
IT活用、フレックスタイムの活用、在宅勤務など様々な取り組みが各企業で行われており、少しずつ働く環境が改善されています。
このような環境で出てくる言葉が「裁量」という言葉かもしれません。
少し前であれば、限られた人の中でしか使われていなかった言葉の印象があるのですが、今ではかなり浸透している感じがあります。
今回は、この「裁量」について説明をしていくことにします。
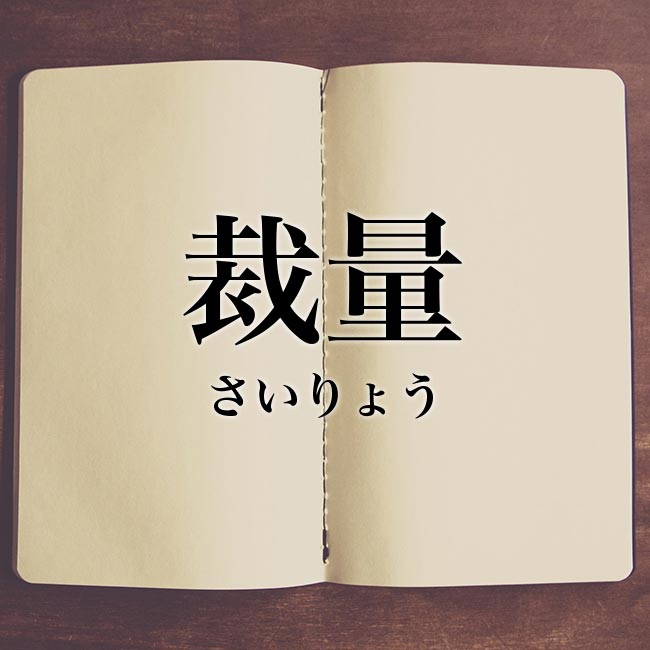
目次
- 「裁量」の意味とは?
- 「裁量」の読み方
- 「裁量」の英語(解釈)
- 「裁量」と「采配」の違い
- 「裁量」の言葉の使い方
- 「裁量」を使った言葉・慣用句や熟語など(意味を解釈)
- 「裁量」を使った例文や短文など(意味を解釈)
- 「裁量」と「一任」の違い
- 「裁量」の類語や類義表現
「裁量」の意味とは?
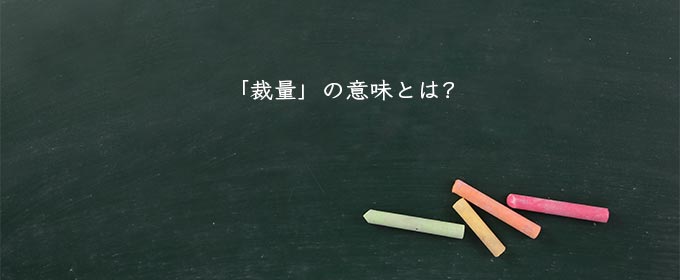
「裁量」とは、「自分の意見で物事を取扱い、こなしながら処置すること」という意味がある言葉で、シンプルに言うと、「自分で自由に決めてよい」ということ解釈ができるでしょう。
元々は、行政・法律分野で頻繁に出てきていた言葉なのですが、この数年でビジネスの業界でも、意思決定に関わるジャンルやワークスタイルに関連して用いられることが増えています。
「裁量」の読み方
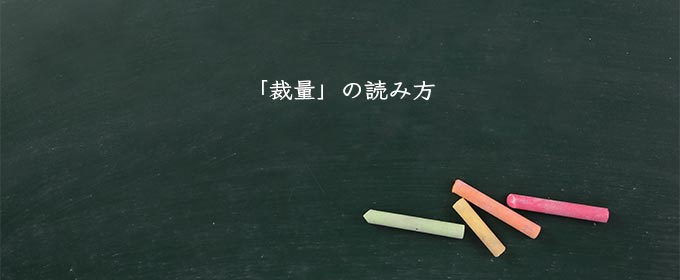
「裁量」は「さいりょう」という読み方になります。
「裁量」の英語(解釈)
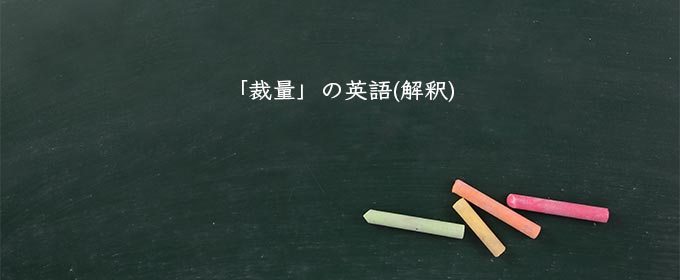
「裁量」を営業で表現すると、“discretion”という訳になります。
「裁量」と「采配」の違い
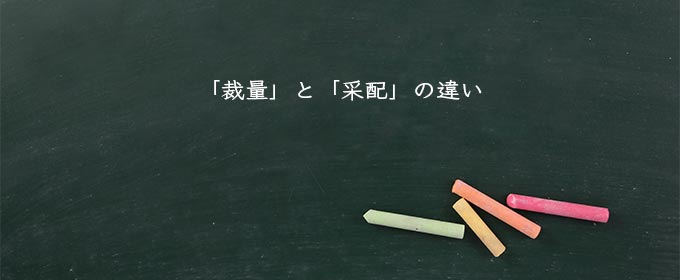
「裁量」という言葉が身近場面で使われることが多くなってきましたが、一報で「采配(さいはい)」という言葉も目立ってきています。
「采配を振るう」といったような表現で使われていますが、「采配」とは「指図、指揮」という意味のある言葉です。
スポーツやビジネスシーンでも出てくるフレーズで「今年シースンはA監督がチームの采配を振るうことなった」や「田中部長が仕事の采配を取ることになっている」といったような使われ方をしています。
「采配」は「戦場で大将が家臣を指揮する際に振った道具」が言葉の由来で、この道具を振りながら、命令して人を動かすことから「采配」「指揮、指図」という意味に転じていったのです。
「采配」は「目上の人」が「下の人」を指示する場合などに使う言葉なので、「裁量」の対義語という位置付けになるかもしれません。
「裁量」の言葉の使い方
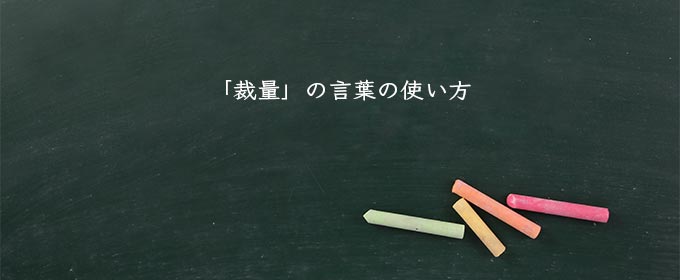
「裁量」は現代の様々なビジネスシーンで使われることが多いのですが、自分1人で物事を決めるような際に使うことになります。
「裁量」を使った言葉・慣用句や熟語など(意味を解釈)
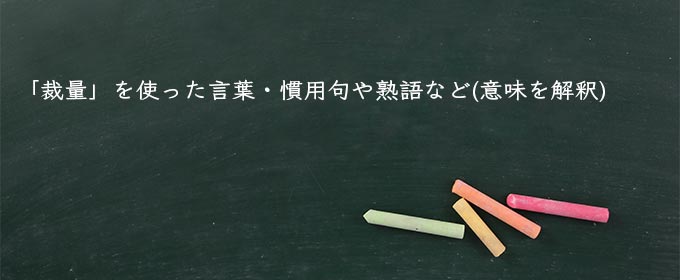
では、ここで「裁量」使った言葉の意味を見ていくことにしましょう。
- 「裁量で決める」
- 「裁量を持たせる」
- 「裁量が狭い」
- 「裁量労働制」
「裁量で決める」
「裁量で決める」とは、「自分の考えや見通し、能力も元に、仕事時間配分や進め方を自由に決める」という意味になります。
ビジネスの世界では、「自由裁量権」や「個人の裁量に任せる」というようなキーワードで耳にすることが多くなってきました。
「裁量を持たせる」
「裁量を持たせる」をビジネスシーンに当てはめて解釈してみると、部下に「裁量の範囲を持たせること」、あるいは「与えること」という意味になるでしょう。
何かプレゼン資料作成を指示した時に、資料の活用目的や大まかな流れは伝えても、具体的な作成については、部下本人に任せるような場面で使われます。
但し、任せるにしても、「任せっぱなし」ではなく、時折、チェック&フォローが入ることもあります。
「裁量が狭い」
逆に「裁量が狭い」となると、「裁量を持たせる」=「自由にさせる」ことではなく、細かく指示を出すように、本人に判断をさせないような仕事をさせる時に出てくる言葉です。
かなり、行動が制約されてしまうので、「裁量が狭い」仕事は窮屈で面白みのないものに感じてしまうことが多くなります。
「裁量労働制」
「裁量労働制」とは。
労働時間制度の1つで、「労働時間を実労働時間ではなく、一定の時間と労働時間とみなす制度」のことを指しています。
現代の企業では、この制度を導入してきており、出退勤時間の制限が無くなり残業時間も少なくなっています。
全ての勤務者、労働者に当てはまるものではありませんが、「働き方改革」の一環ではワークスタイルの変化の代名詞的な勤務体系と言えるでしょう。
「裁量」を使った例文や短文など(意味を解釈)
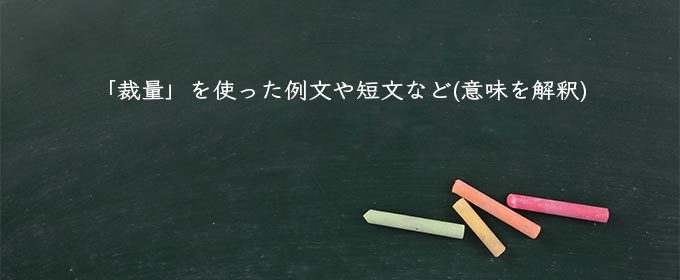
では、ここで「裁量」を使った例文を見ていくことにしましょう。
- 「裁量」を使った例文1
- 「裁量」を使った例文2
「裁量」を使った例文1
「我が社では店舗毎に店長の運営の裁量権を与えているので、店毎のオリジナリティのある魅力が生まれてきており、どの店舗も売上が好調だ」
流通小売業や飲食チェーンでは、画一的なマニュアルに基づいた店舗運営が、成功するビジネスモデルでしたが、顧客の嗜好の多様化もあり、このように店長に「裁量権」を与えることで、地域毎、店舗毎の魅力ある運営が増えています。
「裁量」を使った例文2
「IT企業を始めとするベンチャー企業は、社員1人ひとりに裁量権が与えられているので、大企業とは異なる強みがある」
この例文のようにIT企業、ベンチャー企業と大企業の運営方法が比較されることがよくあります。
ここで大きな違いは「裁量権」が社員に与えてられているかどうかですが、大企業も社員の「裁量」が大きくなりつつあるようです。
「裁量」と「一任」の違い
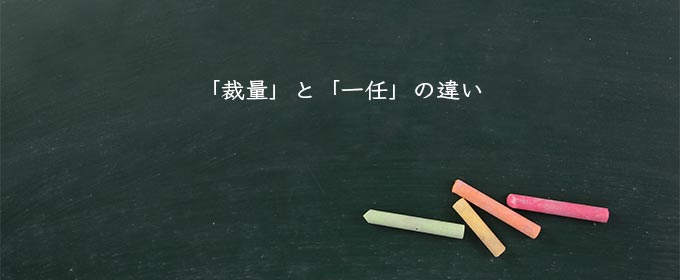
「一任」とは「物事の処理や決定を全て任せる」という意味がある言葉で、「裁量」とは、「自分の思いや判断で行える権利や範囲」という意味があります。
このことから、「自分の思いや判断で行える権利(=裁量)」を「全て任せる(=一任)」という形で「裁量を一任する」という慣用句として使われることになります。
したがって、「裁量」と「一任」とは、言葉の意味が似ていても、言葉の位置付けが異なるのです。
「裁量」の類語や類義表現
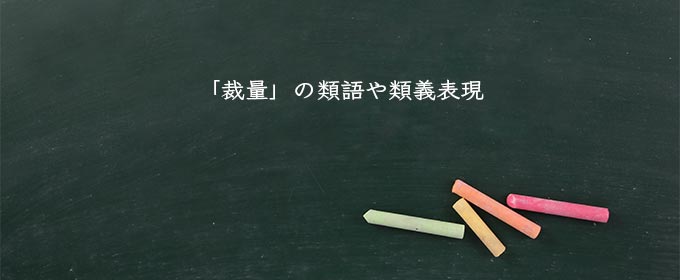
では、「裁量」の類語も見ておきましょう。
- 「任意」
- 「フリーハンド」
「任意」
「任意」とは、「その人の意思に任せること」、「そうするかどうか、あるいは、どれにするかを勝手に選べること」という意味で使われています。
「フリーハンド」
「フリーハンド」という言葉も「裁量」の類語としてありますが、「他からの制約や束縛を受けないこと」という意味を持つ言葉です。
「裁量」という言葉は、この1、2年の間で耳にすることがとても多くなってきました。
それも前述のように社会の労働環境が大きく変化してきたことによりますが、それだけに私達のライフスタイルに合わせた働き方が実現できるようになってきたということです。
しかし、自由に働けるだけに成果をしっかりと出さなければならないことは言う間でありません。