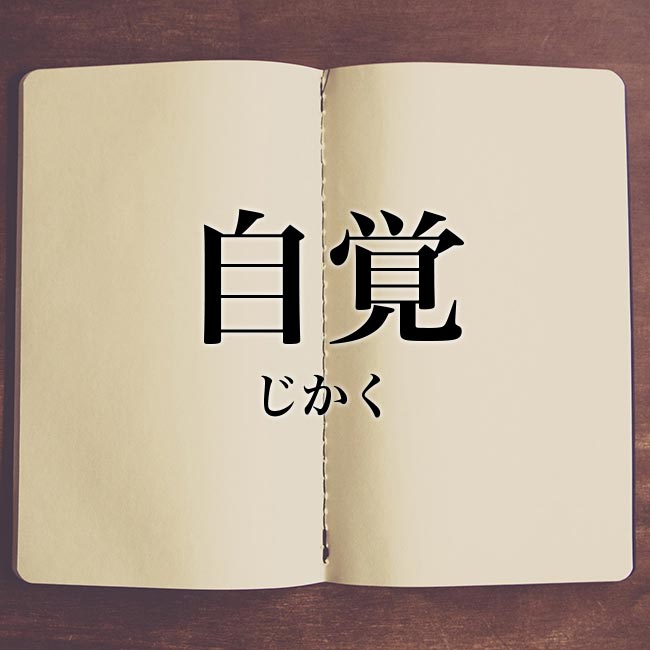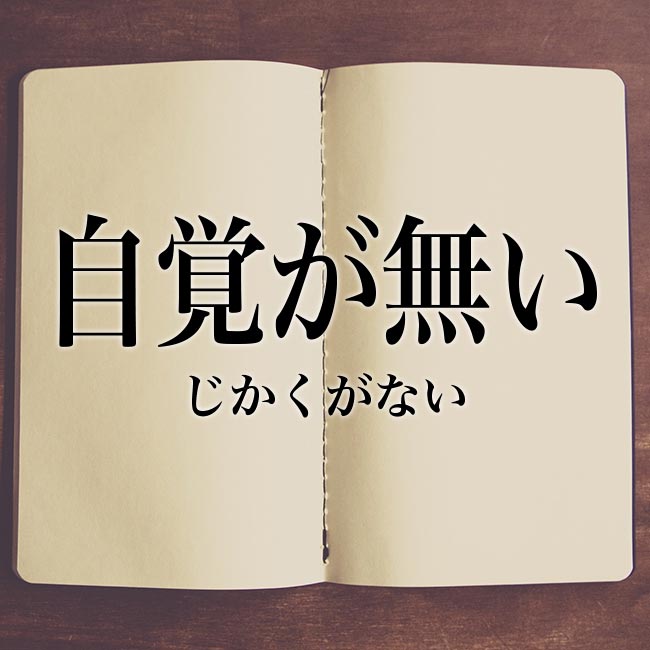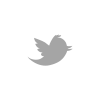「自覚が足りない」の意味とは?例文や使い方を紹介!
人は何かをする際、立場や責任が伴いますが、それを考えない・十分に感じていないときなどに「自覚が足りない」という言葉を用いることがあります。
日常的に用いる言葉ですが、正しくはどのような意味か紹介していきます。
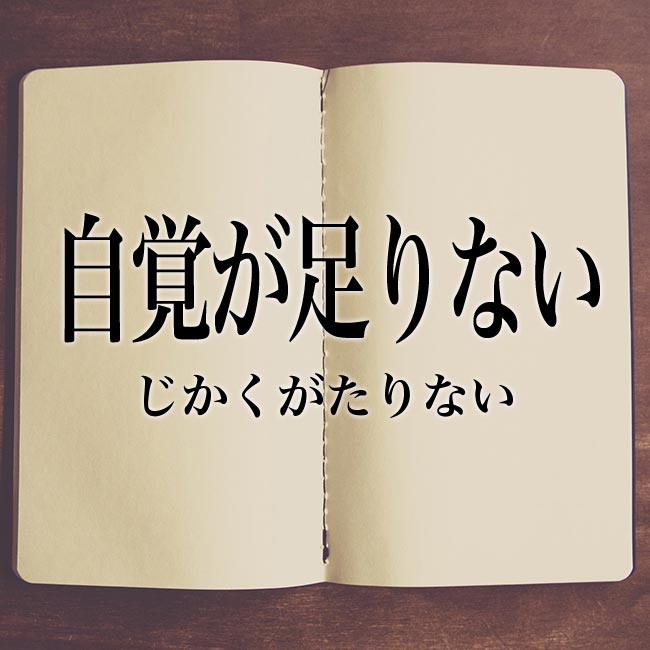
目次
- 「自覚が足りない」とは?
- 「自覚が足りない」の類語や言い換え
- 「自覚が足りない」を使った例文や短文など(意味を解釈)
「自覚が足りない」とは?
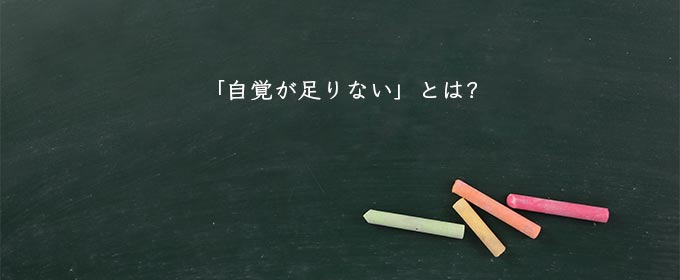
「自覚が足りない」という言葉の意味として、自分の状態を認識していないことを意味します。
「足りない」という言葉は不足していることを表しており、その対象は「自覚」になります。
そして「自覚」とは自分の置かれている状況・状態・位置関係や価値などを知る・認識することを意味しています。
そのため自分のことをわかっていないとなります。
しかし実際に使う場面では仕事上や責任の大きい立場・状況であることが多く、自分のことをわきまえるといった解釈もされます。
- 「自覚が足りない」の読み方と漢字について
「自覚が足りない」の読み方と漢字について
「自覚が足りない」という言葉はそのまま「じかくがたりない」と読みます。
そして「自覚」という感じは元々仏教用語から由来しており、精神的な側面が強く反映されます。
そして「自覚」の「自」は「自ら」のように当事者のことを意味します。
そして「覚」には「覚える・覚る」といった使い方もされています。
そのため自ら気づく・悟ことをから「自覚」という言葉が生まれました。
「自覚が足りない」の類語や言い換え
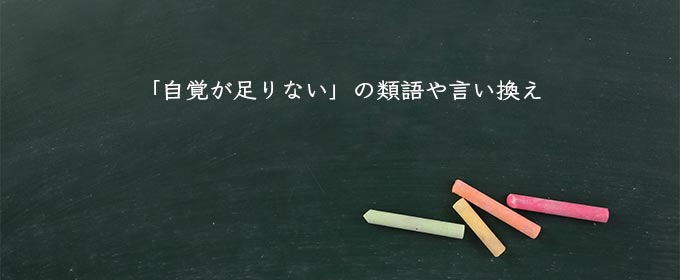
「自覚が足りない」という言葉は学生の頃よりも社会人になってから用いられる機会が多いです。
その分類語や言い換えた言葉も多く存在しています。
それぞれ意味を混同しないようにどのような言葉があるか例を紹介していきます。
- 「意識が甘い」【にんしきがあまい】
- 「不用心」【ぶようじん】
- 「高を括る」【たかをくくる】
「意識が甘い」【にんしきがあまい】
「意識が甘い」という言葉は対象に対して注意・厳しさなどが足りないことを意味しています。
ここでの「甘い」とは味覚ではなく油断や慢心を意味しています。
そして「意識」は対象に対しての認識を表すため、「自覚が足りない」のとされています。
「不用心」【ぶようじん】
「不用心」とは用心を怠ることを意味しておりその背景には警戒心の薄さ・油断・準備不足などが挙げられます。
そのため不足しているという部分は「自覚が足りない」と同義であり、その対象が「自覚」のように自分ではなく用心を必要とする周囲に対してかの違いとなります。
「高を括る」【たかをくくる】
「高を括る」という言葉の意味として安易に予測・想定して大ごとではないとまとめてしまうことを意味します。
しかし実際にはとても重大なこともあるため対象の重要性を認識しておらず十分な思考・判断が足りていないということから類語とされています。
「自覚が足りない」を使った例文や短文など(意味を解釈)
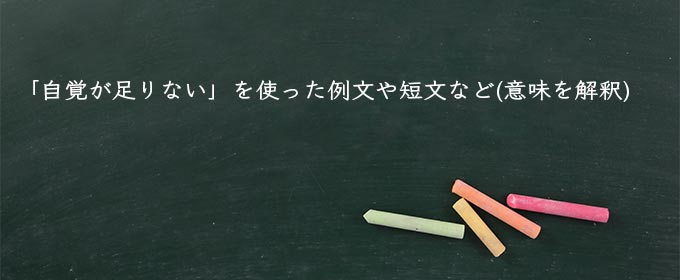
「自覚が足りない」という言葉について、初めは聞くことも多いですが立場が上がるにつれて自分で使うことも増える傾向にあります。
そして常用後にもあたるため、使い方を間違えないようにどのような使い方になるか例を紹介します。
- 「自覚が足りない」を使った例文1
- 「自覚が足りない」を使った例文2
「自覚が足りない」を使った例文1
「部下に『遅刻ばかりで君は社会人としての自覚が足りない』と指導した」
この場合、部下に対して社会人としてどうあるべきかの認識が至らないことを指摘しています。
その原因としては頻回な遅刻にあり、社会人としては適切でないことを伝えるために用いています。
「自覚が足りない」を使った例文2
「私は今まで好き放題してきた。だが結婚してから夫婦として生きていく自覚が足りないと痛感した」
この場合、結婚したことで独身の頃と比べて自由気ままには生活できなくなったが、結婚してからも自分を変えることができていなかったと認識しています。
その当時のことを振り返り、「自覚が足りない」と言っています。
「自覚が足りない」という言葉はビジネス上・プライベートともにいつでも使う機会のある言葉です。
そのため使う場面・使い方を誤らないためにも正しく使う・理解しておくことと、言い換えた表現も知っておく必要があります。