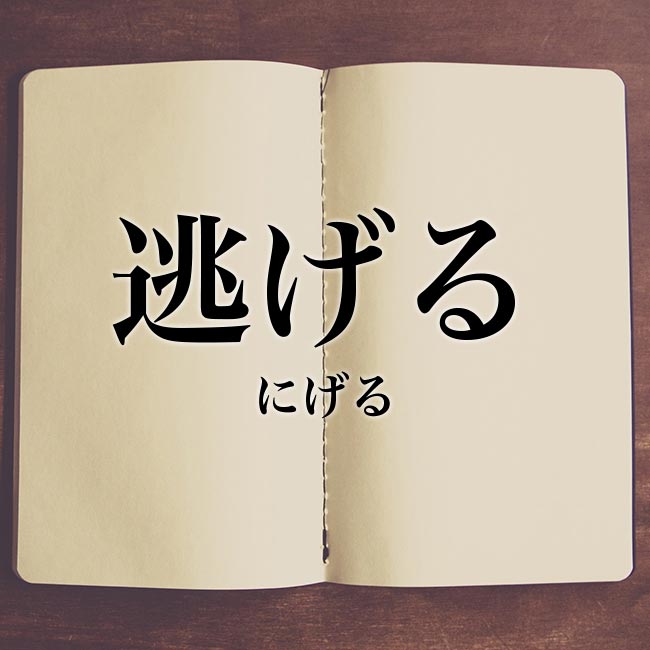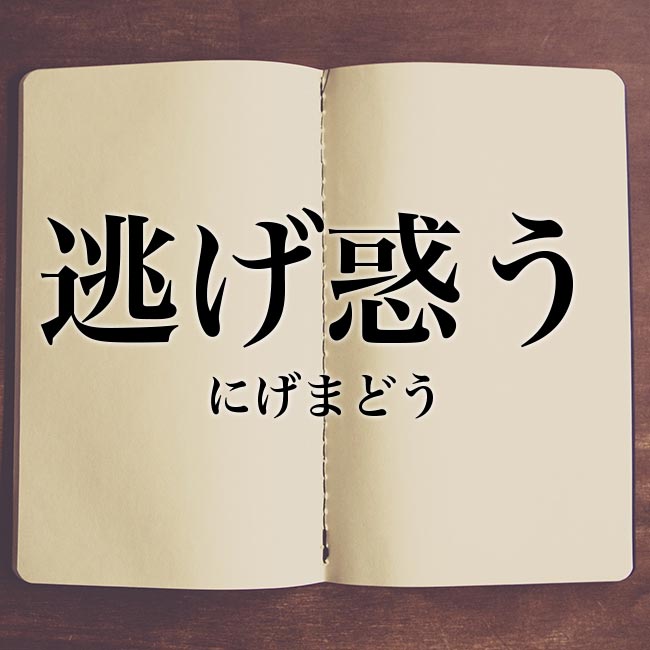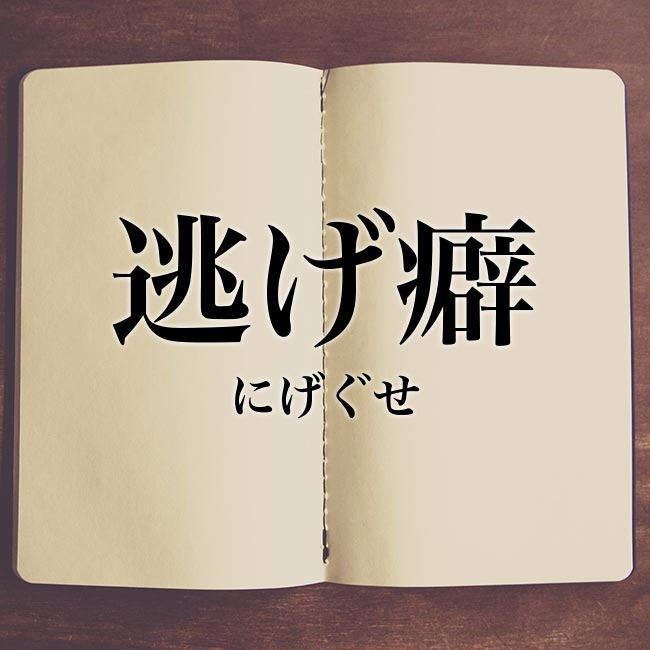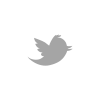「逃げを打つ」の意味とは?類語、使い方や例文を紹介!
「人生は戦いの連続だ!」と言う人がいたりします。
確かにせちがない世の中になってくると、そんなふうに言いたくなるのも無理はありません。
幼い頃から小学校受験で競争の世界に身を置いて、気付くと高校進学、大学受験、そして就職。
社会人になっても、何時までも競争することが、人生のテーマのようになっている人がたくさんいます。
常に攻めのスタンスで、戦いの世界に身を投じていることが当たり前になっているのかもしれませんね。
しかし、人生は必ずしも攻めるばかりが、脳ではありません。
時には、引くことも必要です。
よく言うじゃありませんが。異性を口説く時は、「押すだけでは、ダメだ」という言葉を。
「押したり、引いたりすることで、相手の気持ちを引き寄せる」ことも、人生の面白いところです。
しかし、「逃げを打つ」という言葉は、そのようなことにそぐわない言葉かもしれません。
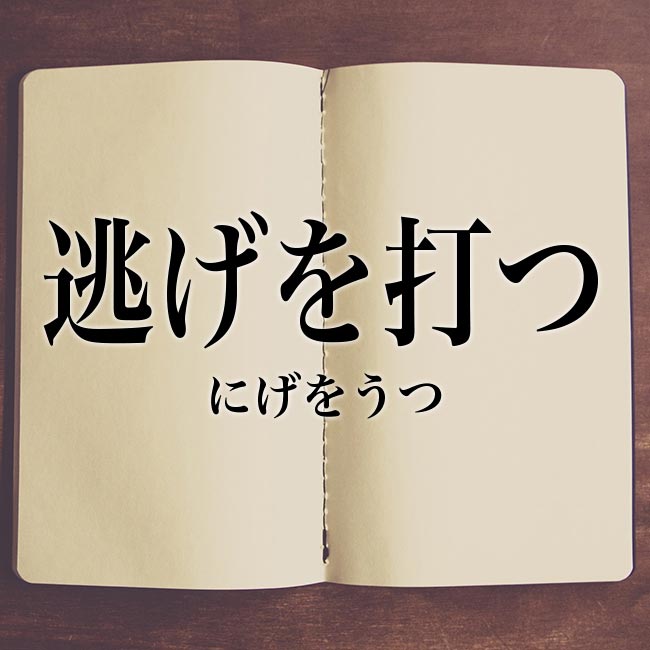
目次
- 「逃げを打つ」の意味とは?
- 「逃げを打つ」の言い換え
- 「逃げを打つ」の類語
- 「逃げを打つ」の使い方
- 「逃げを打つ」を使った例文
- 「逃げを打つ」を分解して解釈
- 「逃げを打つ」の対義語
「逃げを打つ」の意味とは?
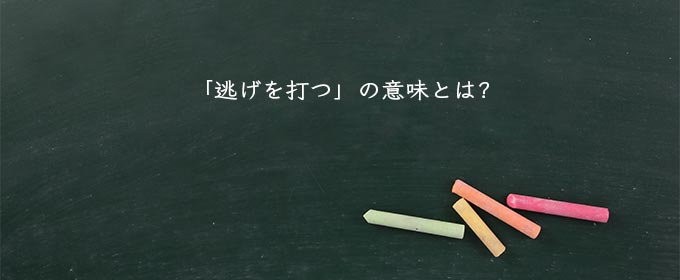
「逃げを打つ」という言葉を皆さんは聞いたことがないでしょうか?
「あいつめ。俺らの知らない間に逃げを打っていた」
このようなセリフをドラマや映画のワンシーンで見たり、聞いたことがあるのではないかと思います。
この「逃げを打つ」という表現には、どのような意味があるのでしょうか?
「逃げを打つ」には、「逃げる用意をすること」や「責任などを逃れるための策を講じる」という意味が込められています。
「責任の追及などを逃れようと手段を講じる」というと意味を聞くと、とても卑怯な行動を取るずる賢い人間のタイプを思い浮かべます。
でも、本当にそうなのでしょうか?
- 「逃げを打つ」の読み方
「逃げを打つ」の読み方
「逃げを打つ」とは、「にげをうつ」と読むので、俗にいう、慣用句やことわざ、四字熟語のように難しい読み方はしません。
素直に読めば済む表現です。
「逃げを打つ」の言い換え
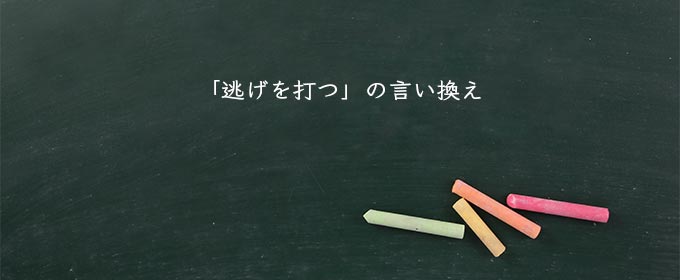
「逃げを打つ」とは、「逃げる準備をすること」や「責任を免れる策を練って準備をしておく」という意味ですが、他に、どのような言葉で置き換えたり、言い換えることができるでしょうか?
「逃げを選ぶ」や「逃げに転じる」という言葉が、「逃げを打つ」に近い表現かもしれません。
「逃げを打つ」の類語
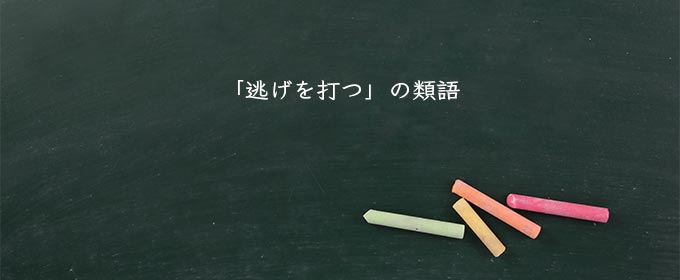
では、「逃げを打つ」の類語を見ていくことにしましょう。
- 「逃げに転じる」
- 「逃げを選ぶ」
「逃げに転じる」
「結局的に攻撃をしていた敵軍が、急きょ、逃げに転じて行ったので、とても助かった」
「逃げに転じる」とは、このような時に、使うことばでしょう。
意味としては、「次の一手として、逃げを選ぶこと」という意味になります。
相手には、弱い面を見せずにひそかに逃げる準備をしているような感じです。
これはビジネスの世界でも、使われるケースがあります。
「ライバル会社はとても積極攻勢をかけていたけど、価格競争になったとたん、逃げに転じた」
ビジネスの世界でも、やはり戦いの連続です。
戦でも、そうですが、できるだけ相手に弱味を悟られないようにして、逃げに転じることも、ケースによっては必要なのです。
できるだけ被害を小さくするためにです。
「逃げを選ぶ」
「逃げを選ぶ」も、「逃げを打つ」と同じような意味を持っています。
「昨日まで威勢の良かった彼も不利な状況になると分かったのか、逃げを選んだ」
これも、自分の負けを予想してか、逃げる姿勢に転じたということになるでしょう。
「あいつは、あれだけ格好いいことを言っていたのに、自分に火の粉が降りかかることが予想されると、逃げを選んだ卑怯者だ」
これも責任回避をするために、ずる賢く逃げる選択をしたのでしょう。
まさに責任逃れをするための行動です。
「逃げを打つ」の使い方
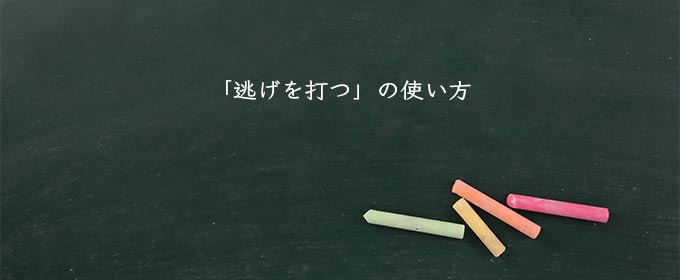
「逃げを打つ」という言葉を使うシーンとしては、いくつかありますが、大きくは2つあります。
戦争でもビジネスの場面でもそうですが、積極的に攻めているようでも、状況が不利になってきたり、それまで勝ちムードだったのが、形成逆転になることで、逃げる(退却)する姿勢に転じたり、大きな失敗で自分の責任を追及されないように、対策を打っていたことです。
このような場面は、今の時代でも日常茶飯事です。
「逃げを打つ」を使った例文
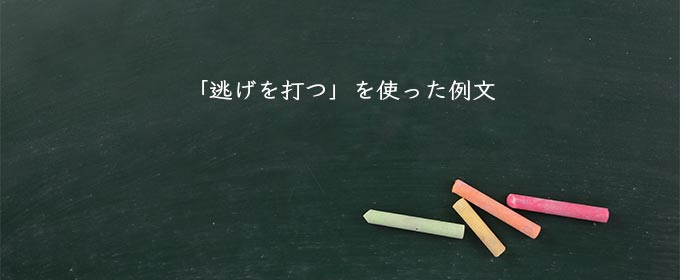
では、この言葉を使うケースを例文で見てみましょう。
- 「逃げを打つ」の例文1
- 「逃げを打つ」の例文2
- 「逃げを打つ」の例文3
「逃げを打つ」の例文1
「この期に及んで逃げを打つとは卑怯だ」
これこそ、「逃げを打つ」という表現の例文としては、典型的な用法でしょう。
土壇場になってから窮地に立たされ、逃げることにした相手に対して、放たれた言葉ですね。
確かに卑怯かもしれません。
幕末の戦で鳥羽伏見の戦いで、徳川慶喜が江戸に逃げ戻った時の様が、このセリフで表現されるかもしれません。
「逃げを打つ」の例文2
「取引先が、予算がないと、逃げを打って、全く相談に応じない」
ビジネスでも、このようなケースで泣かされた営業マンがいないでしょうか?
それまで大きな商売で継続的な取引をしていたのが、急に「予算がない」
と、逃げを打つ担当者に悩まされた人も少なくないでしょう。
「逃げを打つ」の例文3
「あれだけ強硬だった敵軍が、今朝になって。逃げを打っていなくなっていた」
このようなことが昔の戦でも、あったはずです。
できるだけ自軍の被害を小さくしようと、攻撃をするふりをしつつ、逃げる選択肢を採ったのです。
「逃げを打つ」を分解して解釈
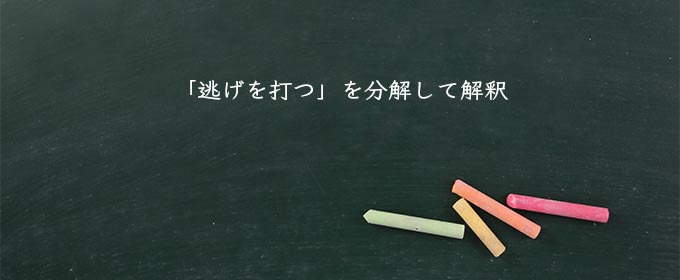
「逃げを打つ」という表現を分けて意味を解釈上してみることにします。
- 「逃げ」
- 「打つ」
「逃げ」
「逃げ」とは、「退散すること」や「不利な状況から、立ち去る」ということになります。
「逃げ」は、齢立場の人が使う方法と思われがちですが、決してそうではありません。
強い立場の者が、戦術の1つとして、「逃げ」を選ぶこともあるからです。
例えが悪いですが、世の中で「喧嘩上手」や「玄関のプロ」と呼ばれている人達は、敵にいきなり攻撃をして、怯んだ隙にその場から、「逃げ」ることを得意としているようです。
あまりに深追いすると、自分にも被害が及ぶために、必要最少限の力や行動で、脱出することを最優先にしているのかもしれません。
このように考えると、「逃げ」も1つの戦い方と言えるでしょう。
「打つ」
「打つ」と言うと、「打撃」や「叩く」と言う意味になります。
しかし、「逃げを打つ」の「打つ」は、「策を講じる」と言う意味になります。
「策を打つ」や「プランを打つ」と言う使い方もあります。
ビジネスでも、「対策を打つ」と言う表現をすることがありませんか?
「逃げを打つ」の対義語
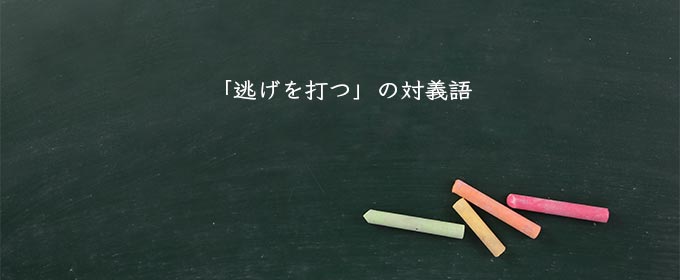
「逃げを打つ」の反対の意味を持つ表現としては、「打って出る」という言葉が挙げられます。
「打って出る」とは、「攻撃に転じる」という意味です。
「今から、打って出るぞ」
こんなセリフが大河ドラマの戦国時代のシーンのセリフで聞いたことがあるでしょう。
積極的姿勢で相手に飛び込んでいく様が想像できると思います。
「逃げを打つ」という言葉の意味を調べていくと、「責任逃れのために作を講じること」という意味合いが、目に付いてしまいます。
この意味だけを見ると、このような行動をする人は、とてもずるい卑怯な輩としか思えないでしょう。
しかし、果たしてそれだけの理解でいいのか、迷ってしまうこともあります。
戦でも、ビジネスの競争世界でも、ケースバイケースで、「逃げを打つ」ことがあってもいいのではないかと思うからです。
「押したり、引いたり」というアプローチの方法も、仕事ではあってもいいと思うのです。
攻める一方では、正確な状況判断ができないこともあります。
戦局を冷静に睨みながら、逃げることもありです。